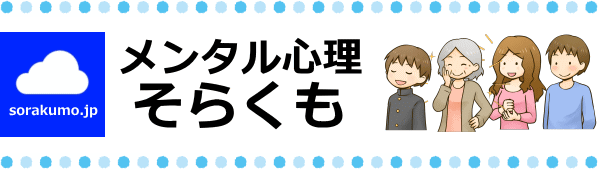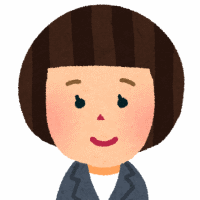-Yさん:滋賀県40代女性-

※クライアントさんからお送りて頂いたアフターフォローメールを了承を得たうえで体験談として掲載しています。
体験談:もっと柔軟に寛容になれると私は確信します。
おはようございます。
私は3月に、1日カウンセリング&セラピーを受けさせていただいた、滋賀県のYと申します。
その節は、送迎に長時間、本当にありがとうございました。
お疲れ様でございました。
本日はお礼の気持ちを伝えたくて、メール差し上げました。
いやぁ、未だに不思議、です。
あのようなカウンセリング&セラピーで、なぜ、自分の見方が変わるのか、
自分が30%程変わることが出来る方向性に持っていけるのか、本当に不思議です。
自分自身は何一つ、変わってないのに。
自らの苦しみを助長するようなちょっとした自分の見方のクセ、みたいなものを、
セラピーによって修正していただいたんでしょう。
未だに不思議。
でもセラピーを受けてからの自分のほうが、しなやかで、断然に好き、ですね。
自分自身が、自分の味方でいてくれることの安心感、信頼感は、最高です。
私にしたら、こんなに良い女が私の味方だなんて、最強(笑)。
私は、ホームページの情報だけの寺井さんを、何一つ保留をつけることなく信じることにして、申し込みました。
もともとの自分の性格だったら、信じられない、と一蹴したかもしれません。
でも、その時は、藁にもすがりたいくらい苦しかった。
自分の心の磁石の揺れが、あまりにも激しくて、自分を保っていられなかった。
たとえ、騙されたとしても、苦しい今よりは5万円分ましなはず、と信じることにしました(笑)。
そして5万円分払うんだったら、素直に先生の言うこと、やることを受け入れたい、と思いました。
セラピーを受けてから、気付いたことがあります。
今までの心の磁石の揺れは、周囲という自分以外の磁石に、振り回されていた、ということ。
セラピー後の今は、針の留め金のところに自分自身の磁石を置いたら、振り回されにくくなっていることに気がつきました。
自分の磁石が強ければ強いほど、外の要因には、振り回されることが少なくなるのでしょう。
これからでも、苦しいことはあります。誰にでも。
それでも、人生の半分で、自分の見方を変えることが出来たことは、
これからの半分の人生が、これまでより豊かな見方が出来て、
自分にも他人にも事柄にも、もっと柔軟に、寛容になれる、と私は確信します。
先生が、苦しんで、それでも資格をとられて、求める患者(?)さんにやってこられたことは、
確実に、求める患者さんを救ってくれています。
少なくとも私は、先生の技術で、救われました。
先生のおかげ、です。
先生、心からありがとうございました!!
先生からいただいた、30%新しい自分を調和させながら、
これからの苦しい人生を、それなりに楽しみながら、生きて参ります。
長々とお読みいただき、ありがとうございました。
先生の、底辺にある苦しみから生まれたものが、
これからも求める誰かを救う一助となりますように。
先生のますますのご活躍と、先生を見守るご家族さまのご健勝を心からお祈り申し上げます。
うん、最後に・・・信じる者は救われる(笑)!!
そらくも@寺井談

こちらこそこんにちは。
まずはじめに、先日は遠いところからお越しくださり長い時間をお付き合いいただき、こちらこそありがとうございました。そして大変にお疲れさまでございました。
「本当に不思議です。」
「自分自身は何一つ、変わってないのに。」
「自らの苦しみを助長するようなちょっとした自分の見方のクセ、みたいなものを、セラピーによって修正していただいたんでしょう。」
Yさんがお聞かせ下さっている心理療法に対する感覚と捉え方がとても素晴らしい感じ方だなと私は感じて嬉しいですし、こうして自分の気持ちを正直に表現できていることがなにより素晴らしい心持ちだなとも私は感じて嬉しいです。
不思議なことは不思議だと表現できている、、、自分自身は何一つ変わっていないと正直に認めることができている、、、
不思議とは新しいということでしょうし、自分を自分以上に鍛えて変える必要も自分を自分以下に抑えこむ必要もないんだ…ということに気づけた。ということなのでしょうね(^-^)
そして、「自らの苦しみを助長するようなちょっとした自分の見方のクセ、みたいなもの…」と表現してくださっております通り、同時に、「自分の見方を変えることが出来たことは…」と表現してくださっております通り、自分が自分に対して抱いてきた印象をYさんと私の二人で捉えなおしてみることで、YさんがYさんの一番の味方に転じてホッと楽な気持ちが広がり始めたんですよね。
「未だに不思議。でもセラピーを受けてからの自分のほうが、しなやかで、断然に好き、ですね。」
「自分自身が、自分の味方でいてくれることの安心感、信頼感は、最高です。」
「私にしたら、こんなに良い女が私の味方だなんて、最強(笑)。」
しなやかで断然に好き、、自分が自分の味方でいてくれることの安心感、、YさんがYさんとのあいだで感じてくださっておりますお気持ちこそが、「自」分と「自」分との「信」頼感=自信という幸せ感なんですよね(^-^)
もともとの自分の性格だったら、信じられない、と一蹴したかもしれません…とご利用前にはいろいろな疑いや慎重さや怖さも感じながらも、でも、その時は、藁にもすがりたいくらい苦しかった…というお気持ちも大切にしてくださり、Yさんは期待も不安も両方とも大切に感じてくださりながら遠方からご来訪くださいましたね。
そして、今&今まで苦しんでいる自分を自分で助けてあげたい!自分が自分の味方になってあげたい!とYさんがカウンセリング&セラピーに真摯に取り組んでくださったからこそ、結果、セラピーを受けてからの自分のほうが、しなやかで、断然に好き、、、自分自身が、自分の味方でいてくれることの安心感、信頼感は、最高です、、、と今現在のYさんが感じることができている。
それは、誰も巻き込まず誰にも邪魔されず自分で自分を幸せにしていきたい!=自立&自助&自尊を育む機会である当方のカウンセリング&セラピーにとっても素晴らしい成果となったなと私は大変に嬉しく思っております。
くわえて、私と私の家族にたいしてまでもお心遣いをいただき誠にありがとうございます。
それでは、こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。
メンタル心理そらくも 代表 寺井啓二より(^^)
上記以外の「対面カウンセリング体験談」は、以下のページにまとめていますのであわせて紹介します。
関連情報まとめページ