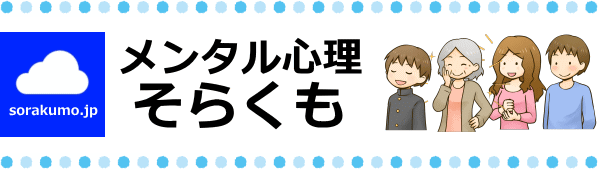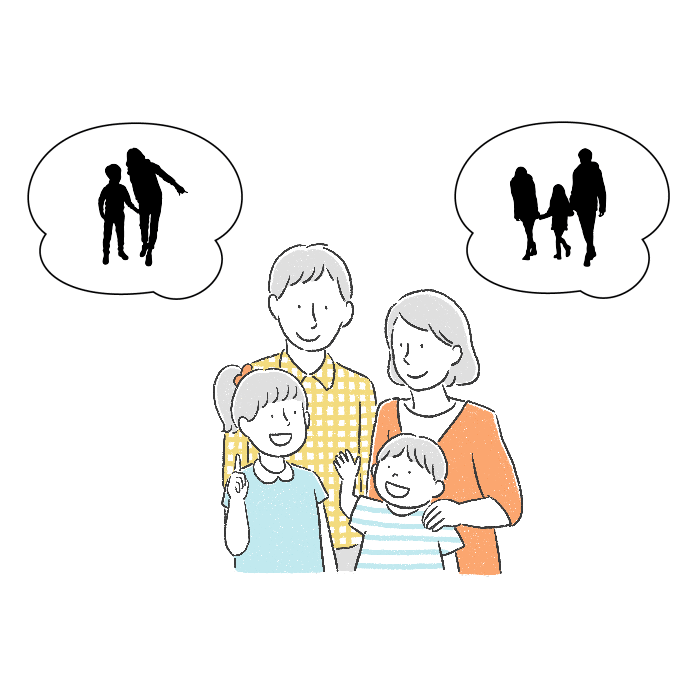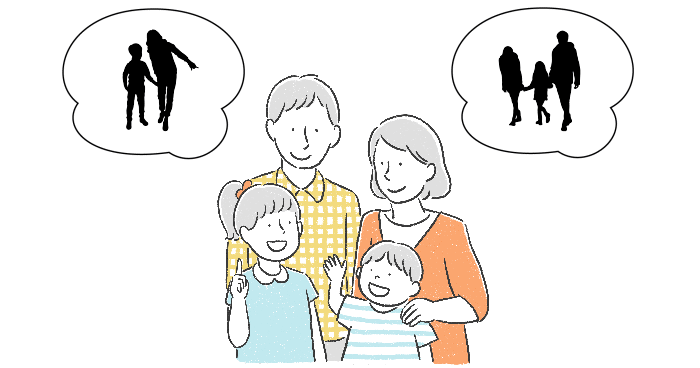
・毒親の特徴にあまり当てはまりませんでした
「毒親」については以下の記事で詳しく解説しています。
また、「毒親」とは「精神医学」や「心理学」などの学術用語ではなく、アメリカの医療コンサルタント・グループセラピストとして活躍した「スーザン・フォワード」の著書「毒になる親」から生まれた言葉で、「子どもの人生に悪影響を及ぼす子育てを行う親を指す言葉」としての意味合いがあります。
毒親(どくおや、英: toxic parents)は、毒になる親の略で、毒と比喩されるような悪影響を子供に及ぼす親、子どもが厄介と感じるような親を指す俗的概念である。1989年にスーザン・フォワード(英: Susan Forward)が作った言葉である。学術用語ではない。
引用元:毒親
「毒親」とは、そもそも「精神医学」や「心理学」などの学術的な根拠がない言葉であるため、「毒親になる原因」は学術的には明確にされていませんが、「毒親自身が、子どもの頃に毒親の親から受けた子育てに原因がある場合が多い」と考えられています。
このように、人は「子育てのやり方」や「家庭の築き方」については「自分が子どもの頃に見聞きした親のやり方を、大人になって無意識に模倣し繰り返す」という特徴があり、「子どもの頃、親にされて嫌だった子育てのやり方(親の子育てから受けた負の影響)を、大人になって自分の子どもへと無意識に繰り返してしまうこと」を「負の世代間連鎖」と言います。
負の世代間連鎖とは、「親(又は親から上の世代)から引き継いだ負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」を指します。世の中の親子問題を抱えている人の多くが、「親を介してこの負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」に巻き込まれたことによって、様々な問題を抱えてしまうようになったことを知ることはとても大切なことです。
引用元:親子の問題①(世代間連鎖)
反対に言えば、「親子関係の問題」や「子育ての問題」とは「親が意図的に起こしている問題」ではなく、曾祖父母から祖父母へ、祖父母から父母へと「無意識に連鎖している問題」と言えます。
このように「毒親」とは「毒親に育てられた影響で子育てがうまくいかない親」を指しますが、「毒親の特徴(毒親に育てられた影響)」は「発達障害」ような生まれ持った「先天的性格(気質)」ではなく、生まれた後に形成された「後天的性格」であるため、専門的な取り組みをすることで克服することは可能です。
そして、心理カウンセリングの現場では「毒親の特徴(毒親に育てられた影響)を克服するために必要な考え方」として、「アダルトチルドレン」や「インナーチャイルド」という「概念」が用いられる場合が多いです。
なお、「『毒親』と『アダルトチルドレン』の関係」や「『毒親』と『インナーチャイルド』の関係」については以下に詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
「毒親」と「アダルトチルドレン」の関係
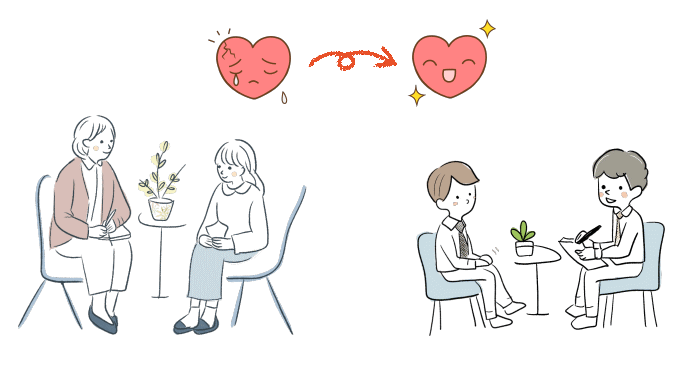
「アダルトチルドレン」とは、家庭内に存在する様々な問題が原因で子どもの頃に「トラウマ(心的外傷)」を負い、その影響で、大人になって「精神疾患、否定的自己概念、偏った人間関係、仕事・恋愛・結婚・子育てがうまくいかない」などの「生きづらさ」を抱えている人のことを指します。
アダルトチルドレン(AC)とは、子どもの頃に親や養育者など家族から受けたトラウマによって、大人になってからも自身が生きづらさを感じながら生活している人のことです。
また、「毒親」自身も「毒親に育てられた『毒親育ち』」である場合が多く、「毒親」とは「毒親に育てられた影響で子育てがうまくいかない親」のことを指します。
ですので、「毒親」と「アダルトチルドレン」は同じ意味合いの言葉と言えます。
今では、「アダルトチルドレン(AC概念)」の生みの親であるアメリカのソーシャルワーカー・社会心理学博士「クラウディア・ブラック」によって「アダルトチルドレンからの回復プロセス」がしっかりと確立されています。
そして、「クラウディア・ブラック」は「アダルトチルドレンからの回復」には以下の2点が重要と述べています。
POINT
- 「親・家族」に対する負の感情は「親・家族」に聞かせるのではなく、「親以外の信頼できる相手(心理カウンセラー・自助グループなど)」に聞いてもらう必要がある
- 「親・家族」に対する負の感情は「安全な場所(カウンセリングルーム・自助グループなど)」で聞いてもらう必要がある
以上のことから、「心理カウンセリングは、アダルトチルドレンの克服(毒親の特徴の克服)にとても有効である」と言われており、カウンセリングを利用して、カウンセラーの協力を得ながら「アダルトチルドレンからの回復プロセス」を進めることで「アダルトチルドレンの克服(毒親の特徴の克服)が可能となる」と言えます。
なお、当社メンタル心理そらくもが考える「アダルトチルドレン克服カウンセリング(毒親の特徴の克服方法)」については、以下の記事で詳しく解説していますので是非お読み下さい。
「毒親」と「インナーチャイルド」の関係
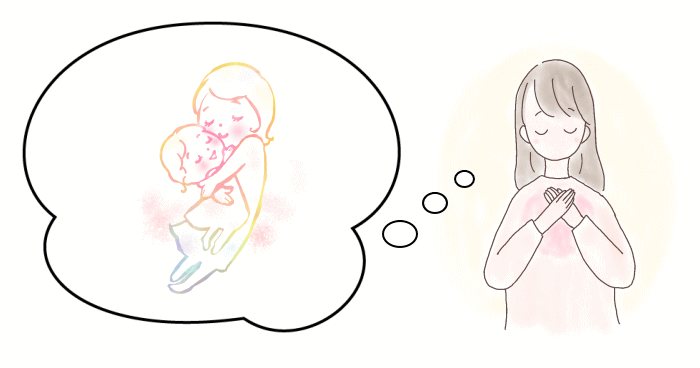
「インナーチャイルド(Innner Child)」とは、スイスの心理学者「カール・ユング」が提唱した「概念」で、直訳すると「内なる子ども」という意味であり、具体的には「傷ついたまま自分の心に取り残さている子どもの頃の自分のイメージ」を意味します。
心理学では「幼少期の体験は『人格形成』に多大な影響を与える」と考えられており、とくに「インナーチャイルドが傷ついたまま」だと、大人になって「精神疾患、否定的自己概念、偏った人間関係、仕事・恋愛・結婚・子育てがうまくいかない」などの「生きづらさ」を感じる場合があると考えられています。
子ども時代に体験したトラウマは、…(中略)…日々の生活や仕事、恋愛など多岐に渡ってあらゆる方面に長く影響を残します。なおかつ意図せずにトラウマを経験した年齢が通常よりも若く発達段階の早期であればあるほど、人生に与える影響は広く深いものになります。
引用元:トラウマが人生に与える影響とは
このように、心理学における「インナーチャイルド」とは「幼少期に負ったトラウマ(心の傷)」や「幼少期に満たされなかった気持ち」や「幼少期に身に付けた思考・行動パターン」など「生きづらさ(毒親の特徴)の根本原因」を指します。
以上のことから、「インナーチャイルド」とは「アダルトチルドレンの生きづらさ(毒親の特徴)の根本原因を意味する言葉」と考えることができ、カウンセリングを利用して、カウンセラーの協力を得ながら「傷ついたインナーチャイルド(幼少期のトラウマ)を癒す」ことで「アダルトチルドレンの克服(毒親の特徴の克服)が可能となる」と言えます。
なお、「インナーチャイルド(毒親の特徴の根本原因)」については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事・関連情報
さいごに、本記事に関する関連記事を以下に紹介します。
是非、あわせてお読みください。
関連記事
もう一度チェックする場合は、以下のリンクをクリックしてください。
もう一度チェックする
以上、「毒親チェックリストの結果」でした。