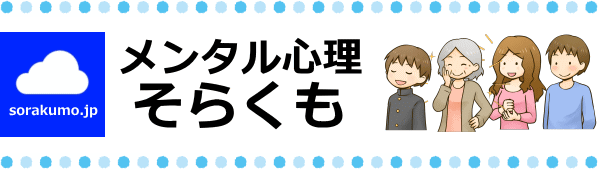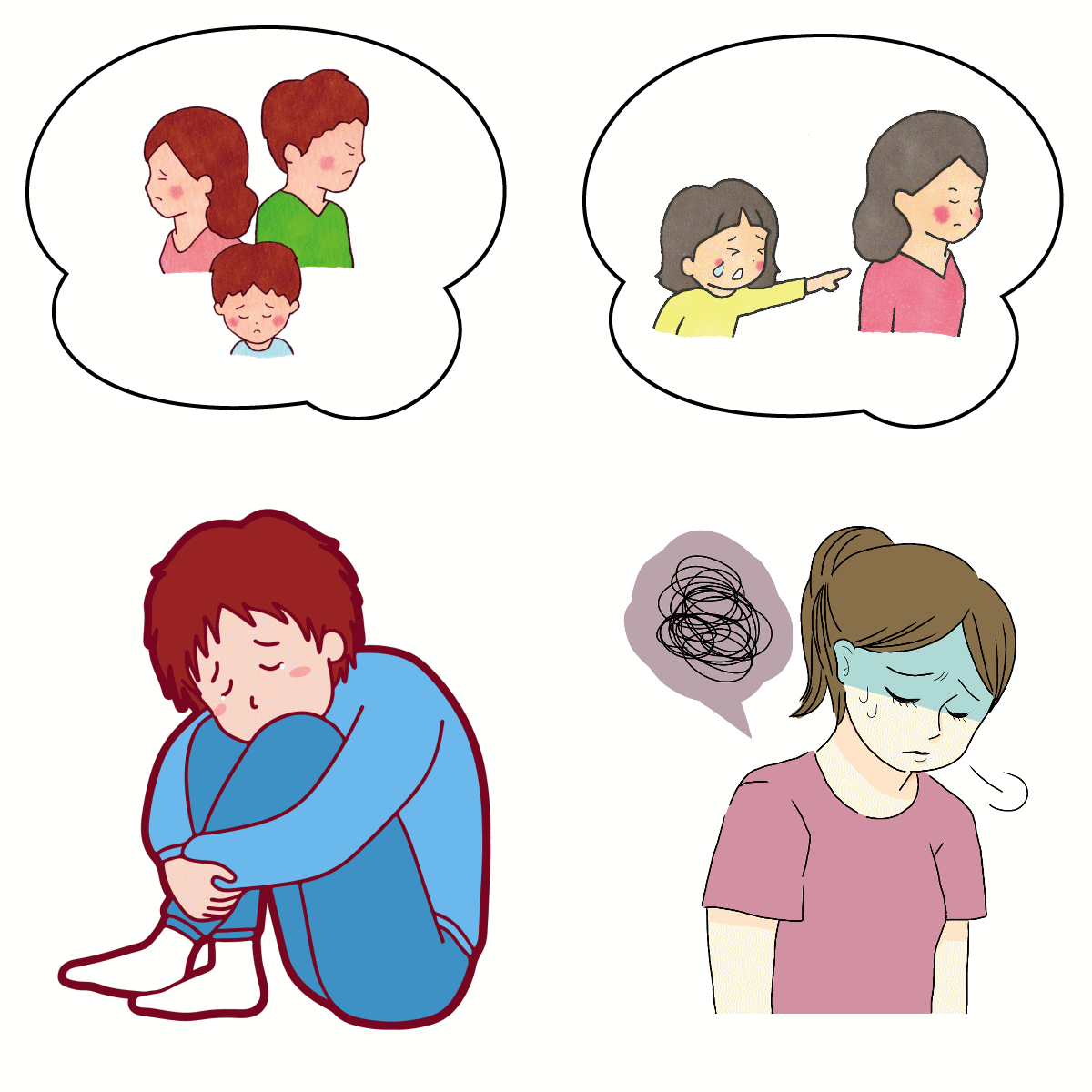
POINTアダルトチルドレンとは、「精神医学」や「心理学」などに学術的な根拠を持つ診断名ではなく、子どもの頃、正常な機能を果たしていない「機能不全家庭」で育ち、心にトラウマ(心的外傷)を負ったことが原因で、大人になって「生きづらさ」を感じている人たちを意味する言葉です。
心理カウンセラーの寺井です。
「アダルトチルドレン」とは、「子どものままの大人」あるいは「大人になりきれない大人」という意味ではありません。
「アダルトチルドレン」とは、「精神医学」や「心理学」などに学術的な根拠を持つ診断名でもなく、「自己理解を深めるための言葉」です。
「アダルトチルドレン」とは、「生きづらさには必ず原因があり、生きづらさの克服は可能である」ことを示す「希望の言葉」と言えます。
このように、「アダルトチルドレン」については研究が進み、現在ではさまざまな克服方法が確立されており、その中でも、心理カウンセリングは「アダルトチルドレン克服の重要な役割」を担っています。
この記事は、アダルトチルドレンに関連する記事をまとめています。
アダルトチルドレン(AC概念)とは?
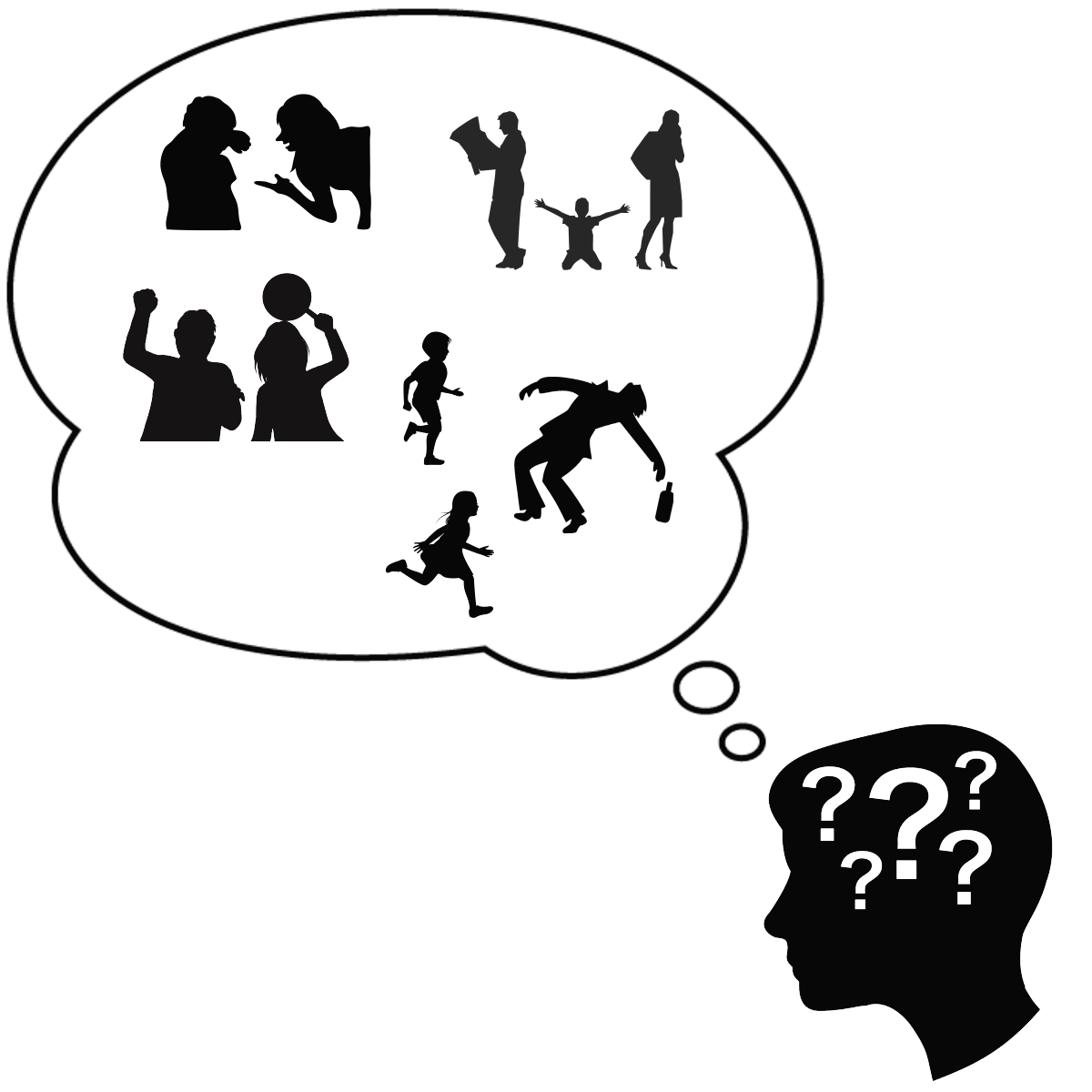
「アダルトチルドレン」とは、子どもの頃の家庭環境において、親や家族との間で何らかのトラウマ(心的外傷)を負ったことが原因で、大人になって「人間関係の悩み」や「自己否定感」など、「生きづらさ」を感じ悩み苦しんでいる人たちを意味する言葉です。
アダルト・チルドレン(Adult Children:以下AC)とは、子どものころに、家庭内トラウマ(心的外傷)によって傷つき、そしておとなになった人たちを指します。…(中略)…ACの概念は1970年代にアメリカで提唱され始めました。
引用元:アダルト・チルドレンってなに
そして「アダルトチルドレン(AC概念)」とは、以下のような考え方を指します。
POINT
- アダルトチルドレンとは、学術的な根拠を持つ診断名ではなく、「自己理解を深めるための言葉」である
- アダルトチルドレンは、「子どもが安心できない子育てをする親」に育てられたことにで負った「トラウマ(心的外傷)」が原因である
- アダルトチルドレンは、生まれ持った「遺伝」ではなく、生まれた後で身に付けた「人生脚本」という「習慣」である
- アダルトチルドレンは、親から子へと「習慣」が「世代間連鎖」する可能性がある
- アダルトチルドレンは「習慣」である以上、克服が可能である
- アダルトチルドレンは、子どもの頃に心に負った「トラウマ(心的外傷)」を治療することで克服できる
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレンの歴史

「アダルトチルドレンの歴史」は未だ浅く、まるで「病気や診断名であるかのような誤解」が未だ残っているのも確かです。
「アダルトチルドレン」という概念は、もともと、カナダの「マーガレット・コーク」が1969年に出版した「忘れられた子どもたち~アルコール依存症の親に育てられた子どもについて~」という本から始まったと言われています。
1974年、アメリカの「国立アルコール乱用とアルコール依存症研究所(NIAAA)」により、「アルコール依存症の親を持つ子どもたちの研究」が開始されたことから、「アダルトチルドレン」という概念は、アメリカのアルコール依存症の治療現場から広がりを見せ始めました。
1980年代、アメリカのソーシャルワーカー・社会心理学博士「クラウディア・ブラック」や、アメリカの心理学者「ジャネット・ウォイティッツ」が著した「『アダルトチルドレン』と『アルコール依存症』に関する書籍」が次々とベストセラーとなったことから、「アダルトチルドレン」という概念は、アメリカ社会に定着していきました。
日本でのアダルトチルドレンの歴史は、「クラウディア・ブラック」が1981年に出版した「私は親のようにならない」を、1989年に「斎藤学(さいとうさとる)」氏が翻訳出版したことから始まりました。
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
アダルトチルドレンの特徴
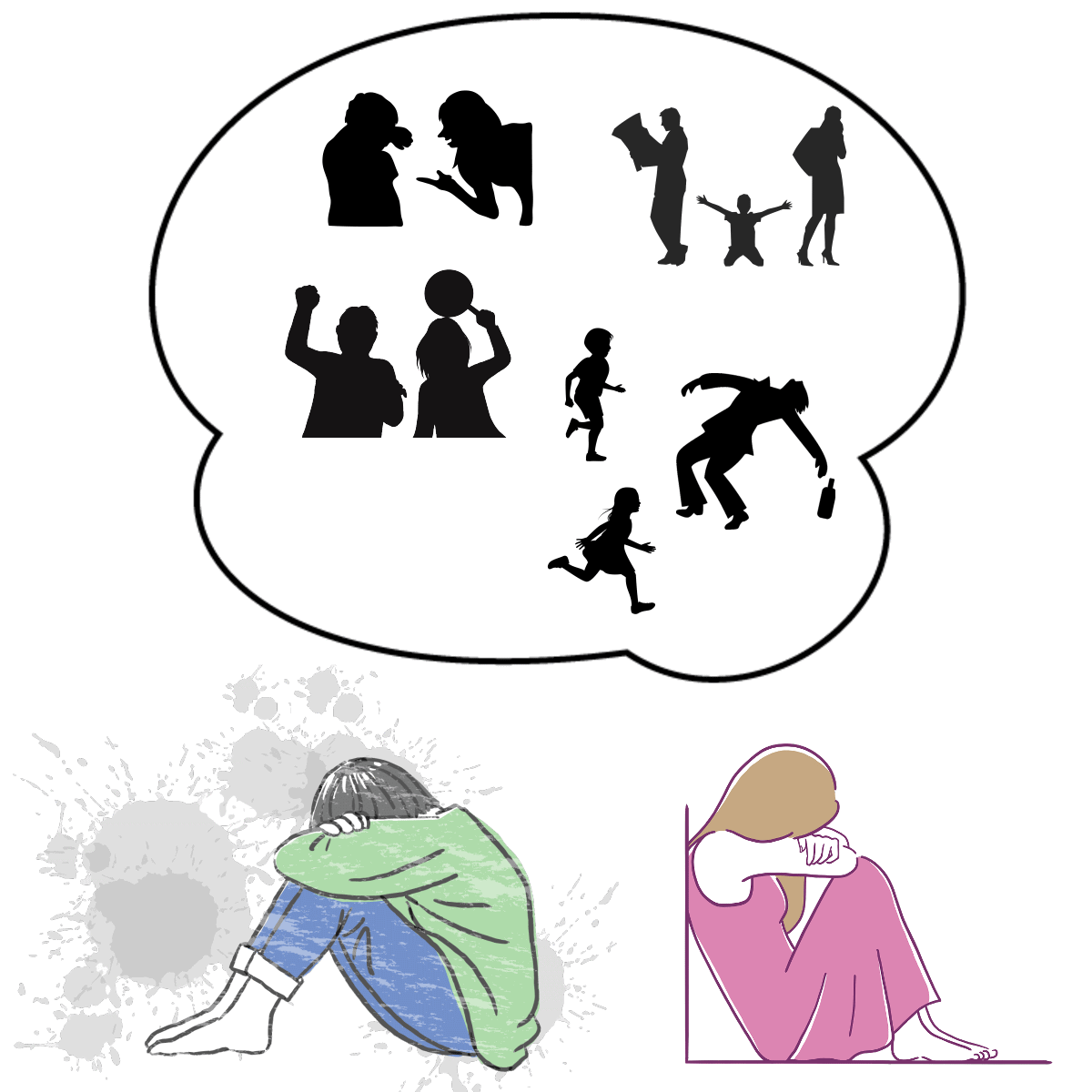
「アダルトチルドレン」とは、本来であれば子どもにとって最も信頼できるはずの「両親」や「家族」から傷つけられたことが原因となり、「他者との信頼関係の構築に不可欠な『人への基本的信頼感』に問題を抱えたまま大人へと成長した人たち」「『精神的な自立』が果たせないまま大人になった人たち」「『生き方』がわからないまま大人になった人たち」ということになります。
よって、「機能不全家族で育った大人・アダルトチルドレン」は、「人が怖い・人が信頼できない・人に相談できない・人に自分の気持ちを言えない(特に怒りや悲しみといったネガティブ感情)・どうせ自分は理解されない」など、他者への警戒心「防衛機制」が高まりやすい傾向があり、そのぶん、家族・職場・恋愛・結婚・子育て・友人など「人間関係の悩み」を抱えやすい特徴があります。
また、このような「機能不全家族で育った大人・アダルトチルドレンの特徴」を「生きづらさ」と呼ぶ場合もあり、「機能不全家族で育った大人・アダルトチルドレン」のことを「毒親育ち」と呼ぶ場合もあります。
この記事は、「アダルトチルドレンの特徴」について、以下の点を詳しく解説しています。
POINT
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレン(ac)チェックリスト
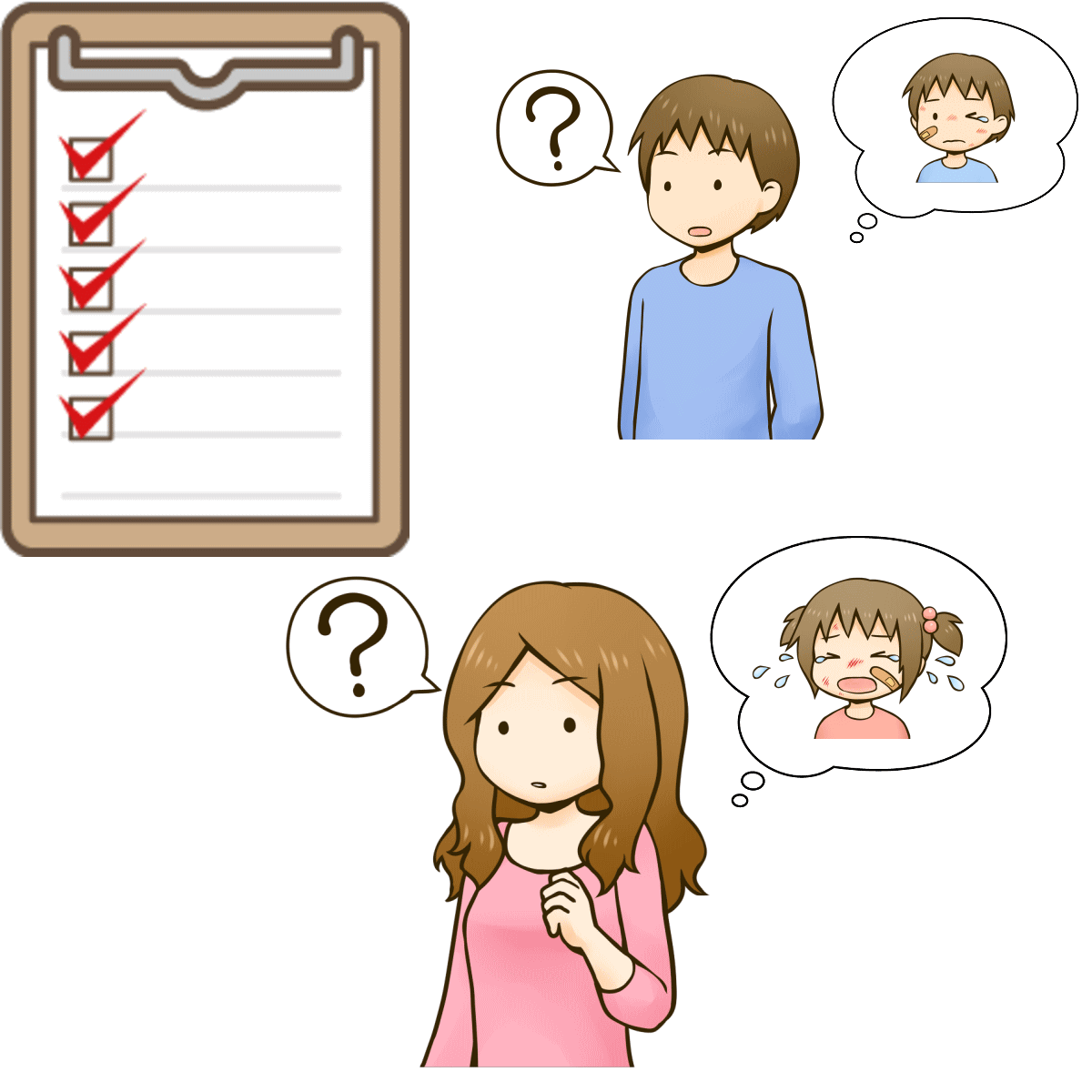
以下の「アダルトチルドレン(ac)診断チェックリスト」は、「アダルトチルドレン研究の専門家たちの文献」と「心理カウンセリングでの症例」に基づき作成した「当社監修の自己評価式チェックリスト」です。
本チェックリストは、アダルトチルドレンの特徴を「60個」あげており、「アダルトチルドレンの傾向(インナーチャイルドがどのくらい傷ついているのか?)」をチェックできます。
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレンの原因
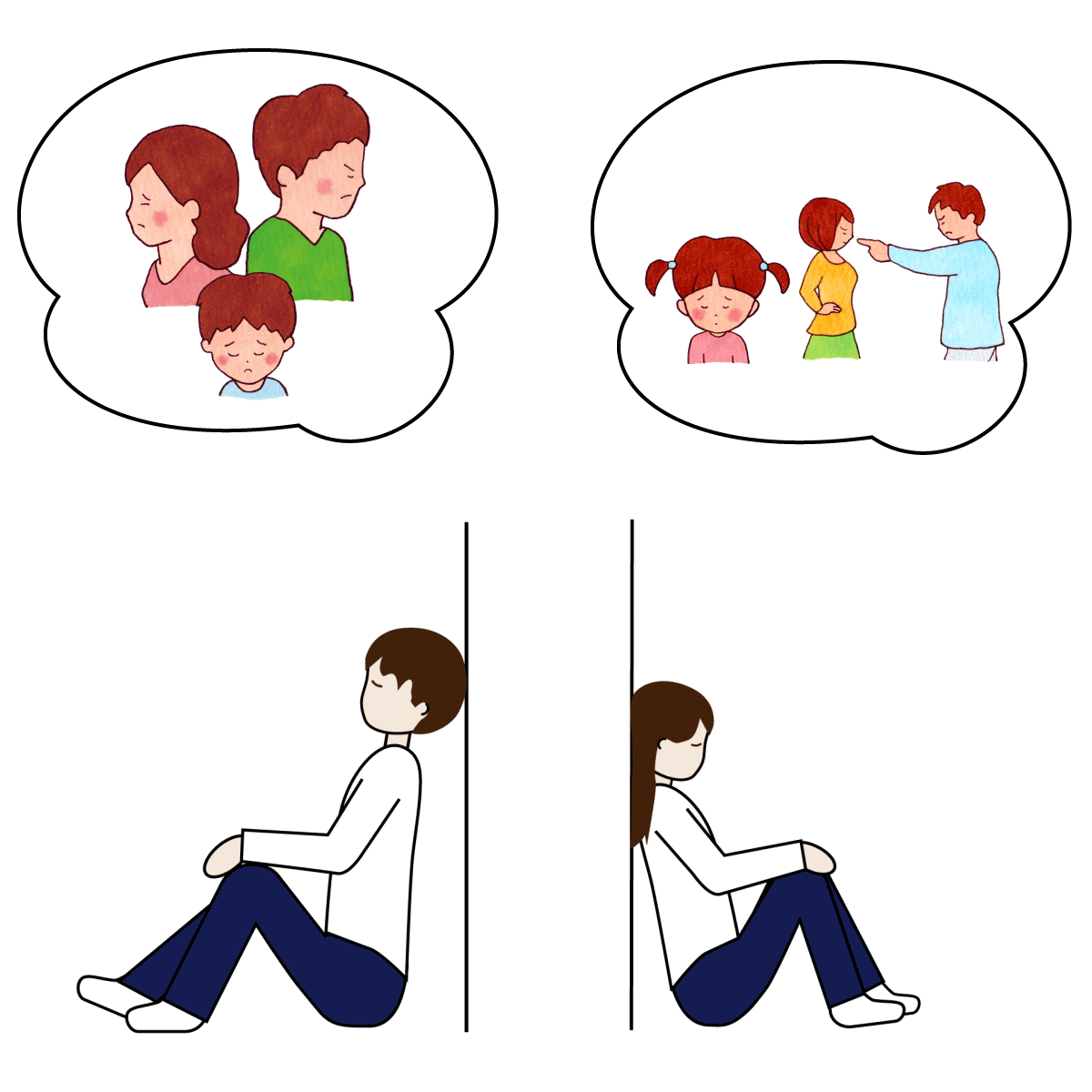
「アダルトチルドレンの原因」は、子どもの頃の「親子関係」や「家庭環境」と密接な関係があります。
ですが、「アダルトチルドレン」になるかどうかは、「親子関係や家庭環境など『環境的原因』」のみで決まるわけでなく、「子どもの性格やストレス耐性など『心理的原因』」も大きく影響しています。
また、アダルトチルドレンが感じる生きづらさの根本原因とは、あくまで「子どもの頃に負ったトラウマ(心的外傷)」などの「心理的問題」であるため、いくら「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」が解決されても、アダルトチルドレンの生きづらさが解決されるわけではないと言えます。
それどころか、「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」の解決を目指せば目指すほど、かえって「親」や「家族」に「執着」してしまい、結果として「共依存」に陥ってしまう可能性があります。
反対に言えば、例え「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」が解決されなくても、「子どもの頃に負ったトラウマ(心的外傷)」などの「心理的な問題」さえ解決することができれば、アダルトチルドレンが感じる生きづらさを改善することができると言えます。
以上のことから、「アダルトチルドレンの原因」は、以下のように「環境的原因」と「心理的原因」に分けて考える必要があります。
アダルトチルドレンの原因
①アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」
②アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」
- ②-1「未完の感情(幼少期トラウマ)」
- ②-2「人生脚本(禁止令・ドライバー)」
続きは、以下に詳しく解説しています。
関連記事
アダルトチルドレン(ac)タイプ診断
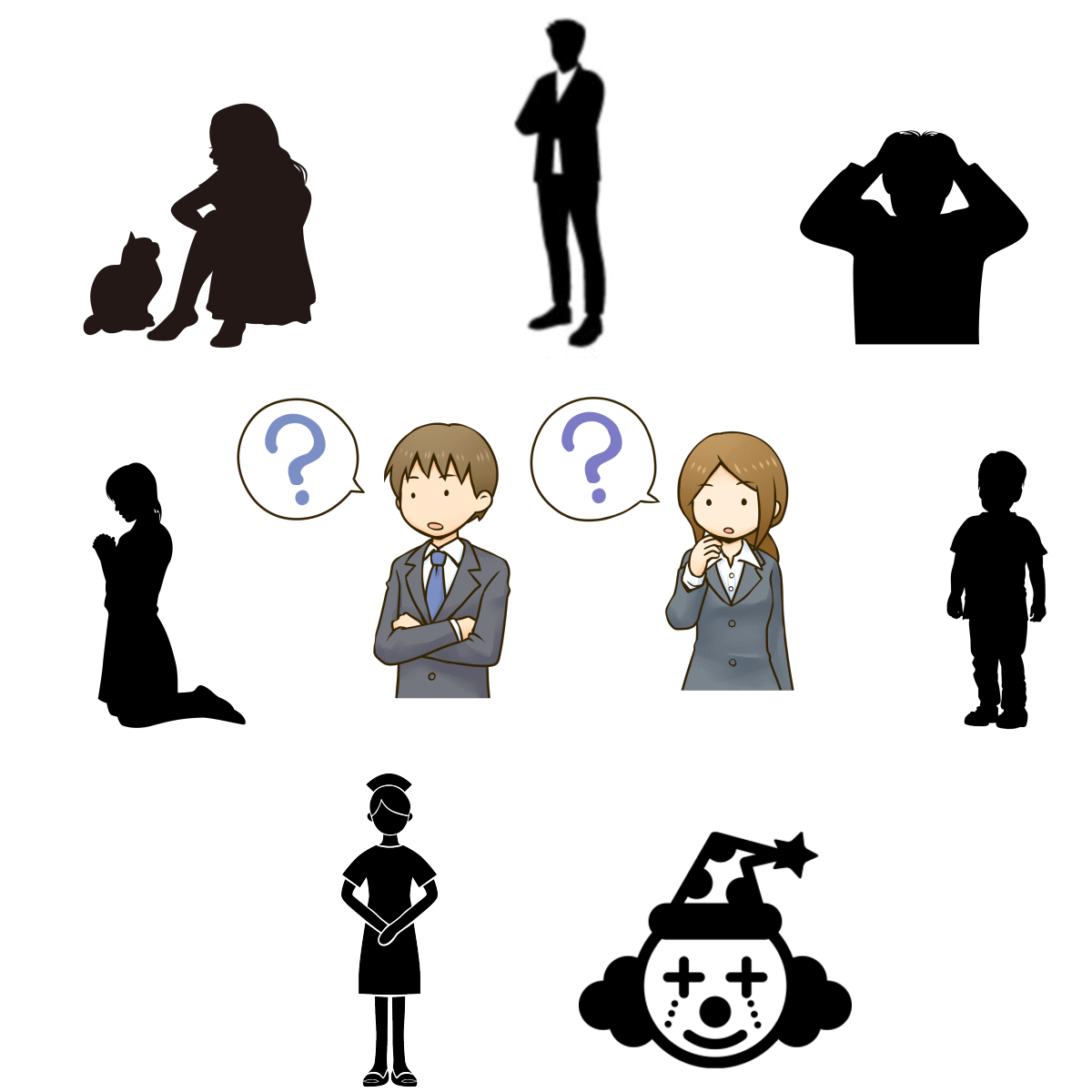
「アダルトチルドレンタイプ」とは、1980年代にアメリカ社会に定着し始めた「アダルトチルドレン(AC概念)」をより理解しやすくするために、アメリカの心理療法家「ウェイン・クリッツバーグ」が「アダルトチルドレン・シンドローム―自己発見と回復のためのステップ」という著書の中で示した「考え方」であり、アダルトチルドレンが子どもの頃に担った「機能不全家族での役割」を言い表したものです。
アメリカのセラピスト、クリッツバーグ(Kritsberg,W)が1985年に出した『ACOA症候群(The Adult Children of Alcoholics Syndrome)』という本の中で、成人してアダルトチルドレンとなった人々が、子ども時代に機能不全家族のなかで、どのような役割を担わされていたかについて言い表したものです。
引用元:アダルトチルドレン6つの役割
「アダルトチルドレンタイプ」という考え方の背景には、あくまで「自己理解を深める」という目的があり、「アダルトチルドレンが自己理解を深めること(アダルトチルドレンのタイプ診断)」は、「アダルトチルドレン(AC)概念」の生みの親である「クラウディア・ブラック」が示す「アダルトチルドレン、回復の4ステップ」のなかの「ステップ②:『過去と現在をつなげる』」にあたります。
アダルトチルドレン「7つ」のタイプ
このように、「ウェイン・クリッツバーグ」は「アダルトチルドレンの克服を進めやすくする」ために、アダルトチルドレンが「機能不全家族で担う役割」を、「①ヒーロータイプ(英雄役)、②スケープゴート(身代り役)、③ロストワン(いない子)、④ピエロタイプ(おどけ役)、⑤イネイブラー(支え役)、⑥プラケーター(慰め役)」の「6タイプ(6つの役割)」にまとめました。
ですが、近年では上記の「6タイプ」に加え、「ケアテイカー(世話役)」という「アダルトチルドレンタイプ」も注目されることが多いことから、当社メンタル心理そらくもの「アダルトチルドレンタイプ診断」では、「ウェイン・クリッツバーグ」がまとめた上記の「6タイプ」に「ケアテイカー(世話役)」もプラスして、以下の「7タイプ(7つの役割)」を使用しています。
POINT
- 「ヒーロータイプ(英雄役)」
「勉強・スポーツ」などで活躍を示すなど、「優秀な人間(英雄的存在)」となることで家族を支える - 「スケープゴート(身代り役)」
家族からの「八つ当たり」を黙って一身に受けとめるなど、「家族のストレスのはけ口(身代りの犠牲者)」となることで家族を崩壊から防ぐ - 「ロストワン(いない子)」
自我を抑え込んだり一人で過ごすなど、「自分の存在感を消す(いない子になる)」ことで家族の負担を減らす - 「ピエロタイプ(おどけ役)」
「家族のストレスや緊張」を和らげるため、おどけたり笑顔を振りまくなど、「ムードメーカー(おどけ役)」となって家族の雰囲気を和ませる - 「ケアテイカー(世話役)」
「病気の家族の看病」をしたり「幼い弟妹の面倒」を見るなど、「父親代わり・母親代わり(世話役)」となって家族の世話をする - 「イネイブラー(支え役)」
「苦労する母親」を支えたり「不甲斐ない父親」を支えるなど、「自己犠牲」によって家族を支える - 「プラケーター(慰め役)」
「落ち込んでいる家族」や「悩んでいる家族」に優しく寄り添うなど、「聞き役に徹する」ことで家族を慰める
アダルトチルドレンのタイプ診断
このように「アダルトチルドレンのタイプ診断」は「アダルトチルドレンの克服を進める(自己理解を深める)」ために行う診断です。
「アダルトチルドレンのタイプ診断」を行うことで、「子どもの頃に身に付けた『生きづらい思考パターン』の影響」や「子どもの頃に負った『幼少期のトラウマ』の影響」などの「生きづらさの原因」を理解することができ、「自分に適した(それぞれのタイプに適した)方法で『アダルトチルドレンの克服』に取り組める」ようになります。
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレンの恋愛傾向
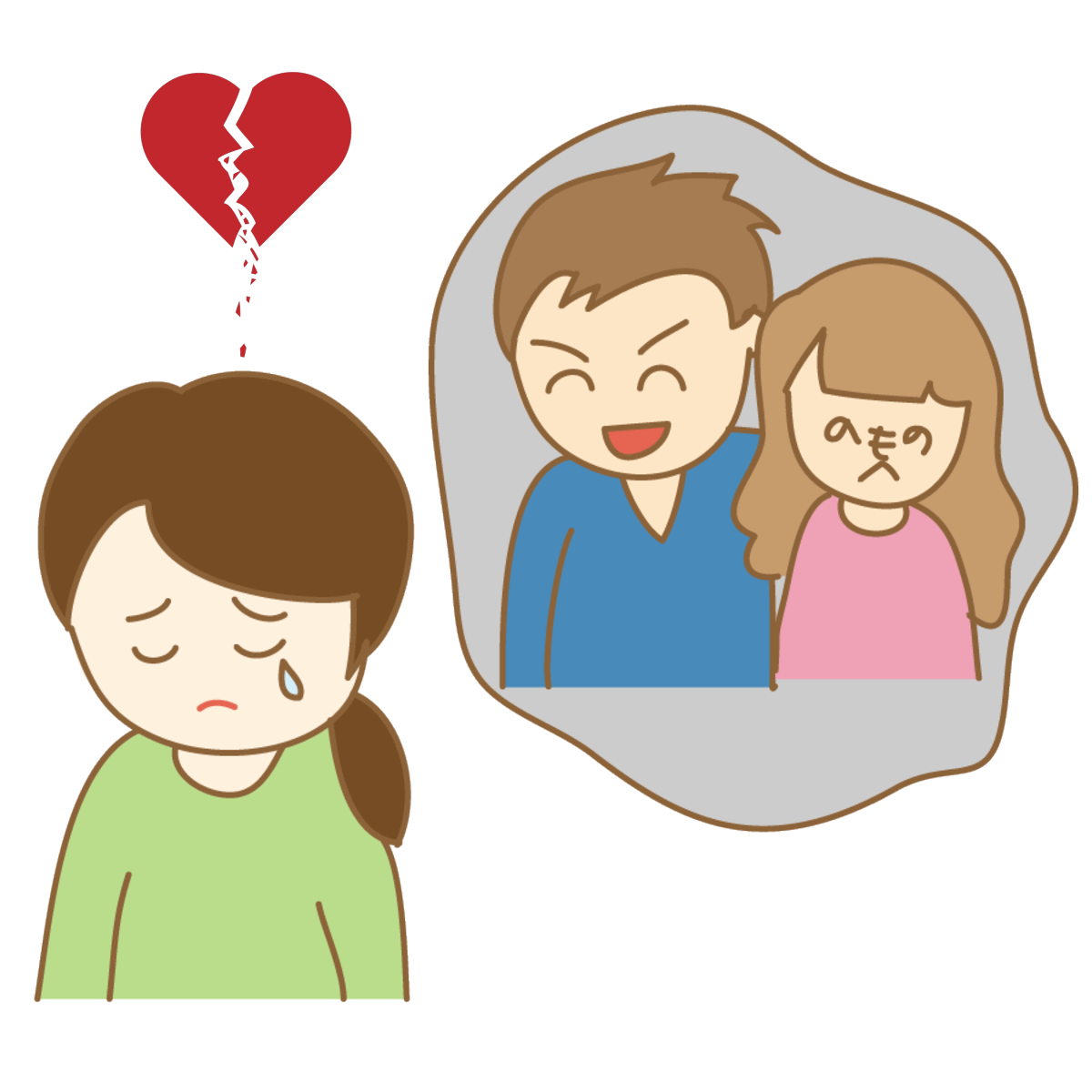
「アダルトチルドレン」とは、「親の愛情不足」のまま大人へと成長した人を指す言葉であり、そのぶん「親の愛情不足」が原因で起きる「見捨てられ不安」や「恋愛依存症」は、「アダルトチルドレンの恋愛傾向」に大きな影響を与えていると考えられています。
また、「恋愛依存症- 苦しい恋から抜け出せない人たち」の著者である心理学者の「伊藤明」氏によると、「恋愛依存症」とは「4つのタイプ」が存在すると考えられており、以下の「4つタイプ」のなかで、とくに「共依存型」と「回避依存型」は「アダルトチルドレンの恋愛傾向」に深く関わっていると考えられています。
恋愛依存症にはタイプ別に
- 「共依存型」
- 「回避依存型」
- 「ロマンス依存型
- 「セックス依存型
という4つの種類が存在します。
この中でも、とくに恋愛依存症の女性と関わりが深いのが「共依存型」と「回避依存型」です。
また、「共依存型」と「回避依存型」に共通してみられる(アダルトチルドレンに良くみられる)恋愛傾向として、「親代わり恋愛」と「試し行為(試し行動)」と呼ばれる「2つの恋愛パターン」があげられます。
以上のことから、「アダルトチルドレンの恋愛傾向」とは、主に以下の「4つ」と考えることができます。
POINT
- 「共依存恋愛(共依存型)」
恋人の存在なしでは、自分の存在価値を感じることができない心理状態
男性も女性もどちらも存在するが、女性の方が多いと考えられている - 「回避依存症(回避依存型)」
恋人の存在は必要だが、恋人から愛されることに息苦しさを感じやすい心理状態
男性も女性もどちらも存在するが、男性の方が多いと考えられている - 「親代わり恋愛」
子どものように甘える・親のように尽くすなど、親子のような恋愛関係
彼女に母親代わりを求める男性・彼氏に父親代わりを求める女性
彼女の父親代わりをする男性・彼氏の母親代わりをする女性…など - 「試し行為(試し行動)」
あえて恋愛相手を困らせるような行動を取ることで、恋愛相手の愛情を確認する行為
男性も女性もどちらも行う行為だが、男性のみ激しい暴力に発展する場合がある
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
アダルトチルドレンの克服
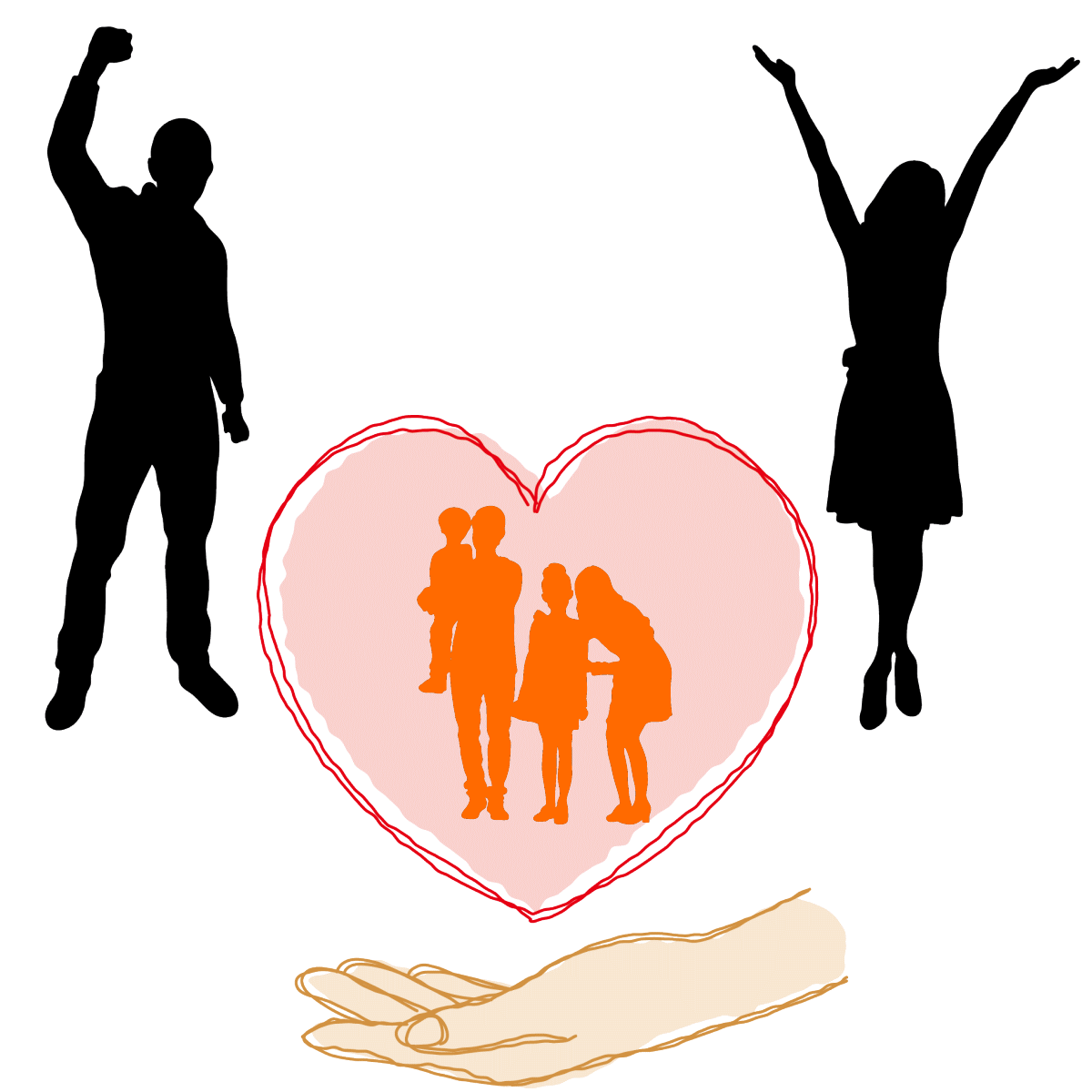
アダルトチルドレンの克服は、「アダルトチルドレン(AC)概念」の生みの親である「クラウディア・ブラック」が示した「アダルトチルドレン、回復の4ステップ」を順守する必要があります。
アダルトチルドレンの克服方法は、「心理カウンセリング」「インナーチャイルドセラピー」「自助グループへの参加」などがあり、「アダルトチルドレンの克服本」も数多く出版されていますが、そのなかでも、「心理カウンセリング」と「インナーチャイルドセラピー」を用いる方法は、アダルトチルドレンの克服にとても有効であると言われています。
そして、「心理カウンセリング」や「インナーチャイルドセラピー」によってアダルトチルドレンの克服が進んでいくと、自分の人生、人間関係、恋愛、結婚、子育てにおいてさまざまなプラスの変化が感じられるようになります。
また、私「心理カウンセラー寺井啓二」は、今はアダルトチルドレン克服の専門家ですが、かつては私自身がアダルトチルドレンであり、「アダルトチルドレン(ac)を克服した人」でもあります。
この記事は、「アダルトチルドレンの克服」について、以下の点を詳しく解説しています。
POINT
- 世の中で知られている「アダルトチルドレンの克服方法」
- 「クラウディア・ブラック」が示した「アダルトチルドレン、回復の4ステップ」
- 「アダルトチルドレンの心理カウンセリング」のポイント
- 「心理カウンセラー寺井啓二」の「AC克服体験談」
- 「アダルトチルドレンを克服すると生まれる5つの変化」
- インナーチャイルドセラピーによる「アダルトチルドレンの克服体験談」
- 「アダルトチルドレンの克服本」の紹介
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレンの回復「4つのステップ」
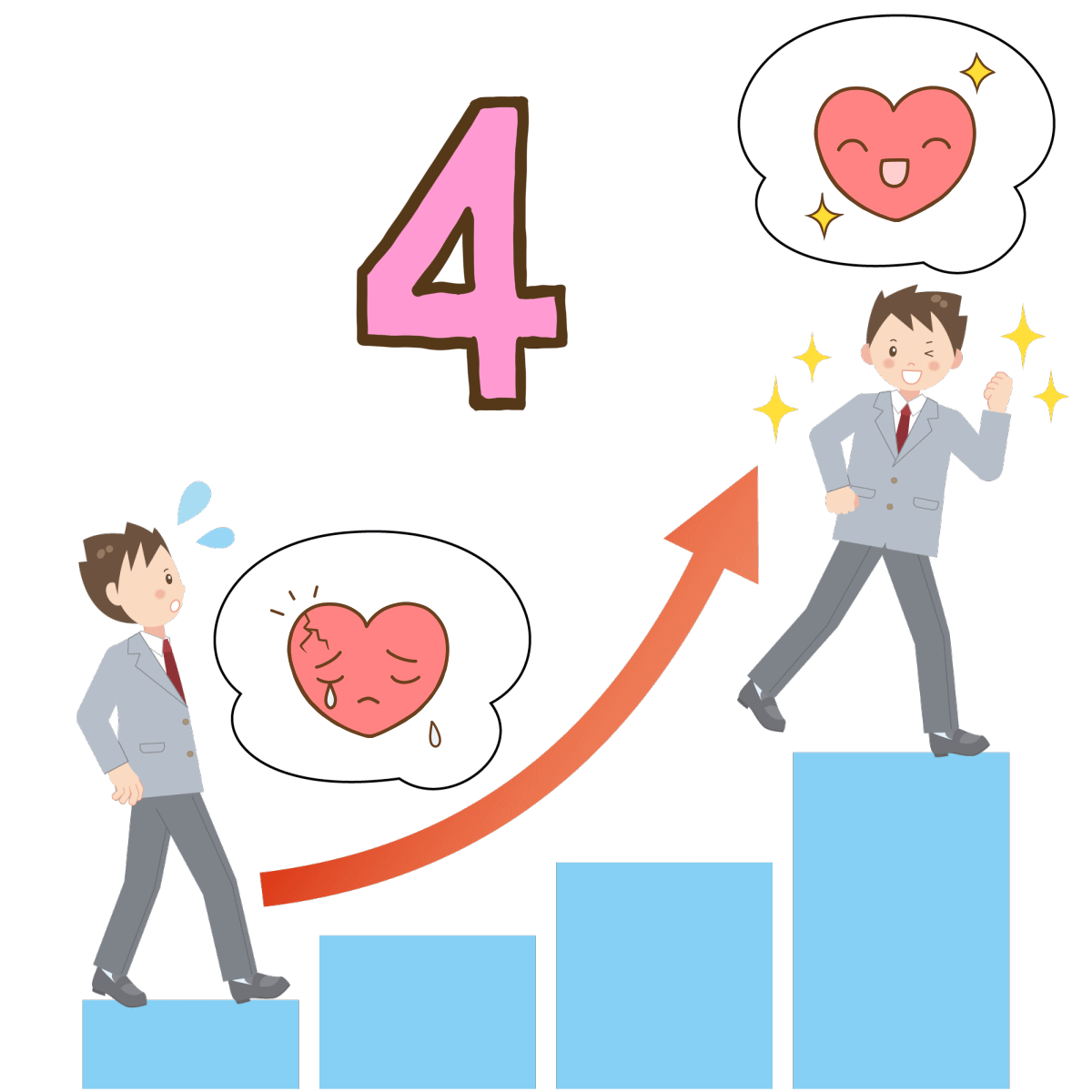
アメリカのソーシャルワーカー・社会心理学博士「クラウディア・ブラック」は、「子どもを生きればおとなになれる―「インナーアダルト」の育て方」という著書の中で、「アダルトチルドレンからの回復プロセス」として、次の「4つのステップ」を示しました。
アダルトチルドレン(AC)概念の生みの親であるクラウディア・ブラックは、ACの回復プロセスを次のような4段階で説明しています。
- ステップ1=過去の喪失を探る
- ステップ2=過去と現在をつなげる
- ステップ3=取りこんだ信念に挑む
- ステップ4=新しいスキルを学ぶ
また、「クラウディア・ブラック」が示した「アダルトチルドレンからの回復プロセス」を「具体化」すると以下のようになります。
POINT
- ステップ1=過去の喪失を探る
子どもの頃から自分の中に存在し続けている「幼少期のトラウマ」の存在に気づき、「幼少期のトラウマを治療する(癒す)」 - ステップ2=過去と現在をつなげる
「人生脚本」を原因とする「禁止令・ドライバーの影響」や「幼少期トラウマ」を原因とする「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の影響」が、現在の自分にどのような影響を与えているか?を理解する - ステップ3=取りこんだ信念に挑む
「禁止令・ドライバー」を緩め、「生きづらい『人生脚本』」から「生きやすい『人生脚本』」へと書き換える - ステップ4=新しいスキルを学ぶ
子どもの頃に学べなかった「人間関係の方法」「感情の扱い方」「自分を大切にする方法」を学ぶ
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
アダルトチルドレンのカウンセリング
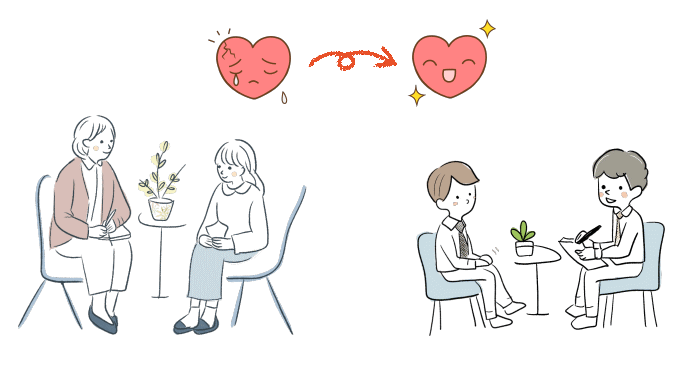
「アダルトチルドレン(AC概念)」の生みの親である、アメリカのソーシャルワーカー・社会心理学博士「クラウディア・ブラック」は、「アダルトチルドレンからの回復」には以下の2点が重要と述べています。
POINT
- 「親・家族」に対する負の感情は「親・家族」に聞かせるのではなく、「親以外の信頼できる相手(心理カウンセラー・自助グループなど)」に聞いてもらう必要がある
- 「親・家族」に対する負の感情は「安全な場所(カウンセリングルーム・自助グループなど)」で聞いてもらう必要がある
以上のことから、「心理カウンセリングは、アダルトチルドレンの克服にとても有効である」と言われています。
また、当社メンタル心理そらくもは、代表:寺井啓二自身が「アダルトチルドレンの克服経験を持つ心理カウンセラー・心理セラピスト」あり、「対話型の心理カウンセリング」に加えて「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」などの「心理セラピー」も取り入れることで、「解決志向(短期療法)に基づく『アダルトチルドレン克服のお手伝い』」を行っております。
なお、「当社メンタル心理そらくもの『AC克服カウンセリング』の特徴」は、主に以下の「4つ」があげられます。
POINT
- アダルトチルドレン「回復の4ステップ」を遵守する
- 「インナーチャイルドセラピー」で最大限の効果を引き出す
- 「解決志向(短期療法)」で何度も通う必要がない
- 「アダルトチルドレンの克服経験を持つ専門家」の協力が得られる
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
以上、「アダルトチルドレンとは?心理学でやさしく解説」という記事でした。