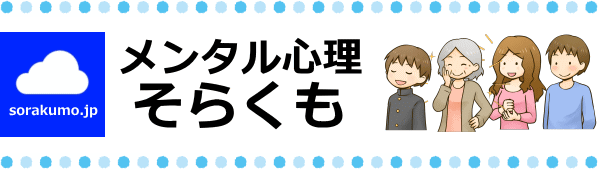POINTアダルトチルドレンの歴史は、1970年代にアメリカのアルコール依存症の治療現場から広がり始め、日本では1990年代に広がり始めました。
心理カウンセラーの寺井です。
「アダルトチルドレンの歴史」は、1969年にカナダで出版された一冊の本から始まり、その後、1980年代のアメリカで本格的に使われ始めました。
そして、日本におけるアダルトチルドレンの歴史は、さらに遅れて1990年代に入ってから始まったと言われています。
このように、アダルトチルドレンの歴史は未だ浅く、まるで「病気や診断名であるかのような誤解」が未だ残っているのも確かです。
アダルトチルドレンの克服は、アダルトチルドレンの歴史を理解するところから始まります。
この記事は、アダルトチルドレンの歴史について説明しています。
アダルトチルドレンの起源

「アダルトチルドレン」という概念は、もともと、カナダの「マーガレット・コーク」が1969年に出版した「忘れられた子どもたち~アルコール依存症の親に育てられた子どもについて~『The forgotten children:a study of children with alcoholic parents』」という本から始まったと言われています。
ですが、この頃は、あくまで、のちの「アダルトチルドレン」に該当する概念が生まれただけで、まだ、「アダルトチルドレン」という言葉そのものは使われませんでした。
その後、1970年代に入ると、「アダルトチルドレン」という概念は、アメリカのアルコール依存症の治療現場から広がりを見せ始めました。
「アダルトチルドレン」への関心の高まり
まず、1974年、アメリカの「国立アルコール乱用とアルコール依存症研究所(NIAAA)」により、アルコール依存症の親を持つ子どもたちの研究が開始されました。
その結果、アルコール依存症の親を持つ子どもたちは、大人になったとき「対人関係の問題」や「生きづらさ」を抱えやすいということがわかってきました。
また、1979年には、「国立アルコール乱用とアルコール依存症研究所(NIAAA)」が主催した国際会議が開催され、「アダルトチルドレン」への関心がさらに高っていきました。
「アダルトチルドレン」の定着
その後、1981年になると、アメリカのソーシャルワーカー・社会心理学博士「クラウディア・ブラック」が、「アルコール依存症である親が子どもに与える精神的な影響」について著した、「私は親のようにはならない」という本を出版し、ベストセラーとなりました。
また、1983年には、アメリカの心理学者「ジャネット・ウォイティッツ」が、「アダルト・チルドレン~アルコール問題家族で育った子供たち~」という本を出版してベストセラーとなり、アメリカにおいて「アダルトチルドレン」という概念が定着していきました。
「アダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス(ACOA)」
このような経緯から、アルコール依存症の親を持ち、「対人関係の問題」や「生きづらさ」に悩み苦しんでいる人たちを、「アダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス(Adult Children of Alcoholics)」と呼び始め、これが「アダルトチルドレン」という用語の起源と言われています。
また、「アダルトチルドレン(Adult Children)」という用語は「AC」と略されることがありますが、1980年代の中頃までは、「アダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス(Adult Children of Alcoholics)」という呼び方をしており、当初の略称は「AC」ではなく「ACOA」と略されていました。
その後、さらに短縮され「AC」と略されるようになったと言われています。
このように、「アダルトチルドレン」という概念は、当初「アルコール依存症の親がいる家庭で育ったことが原因で、『対人関係の問題』や『生きづらさ』に悩み苦しんでいる人たち」だけを指していました。
機能不全家族で育ったアダルトチルドレン
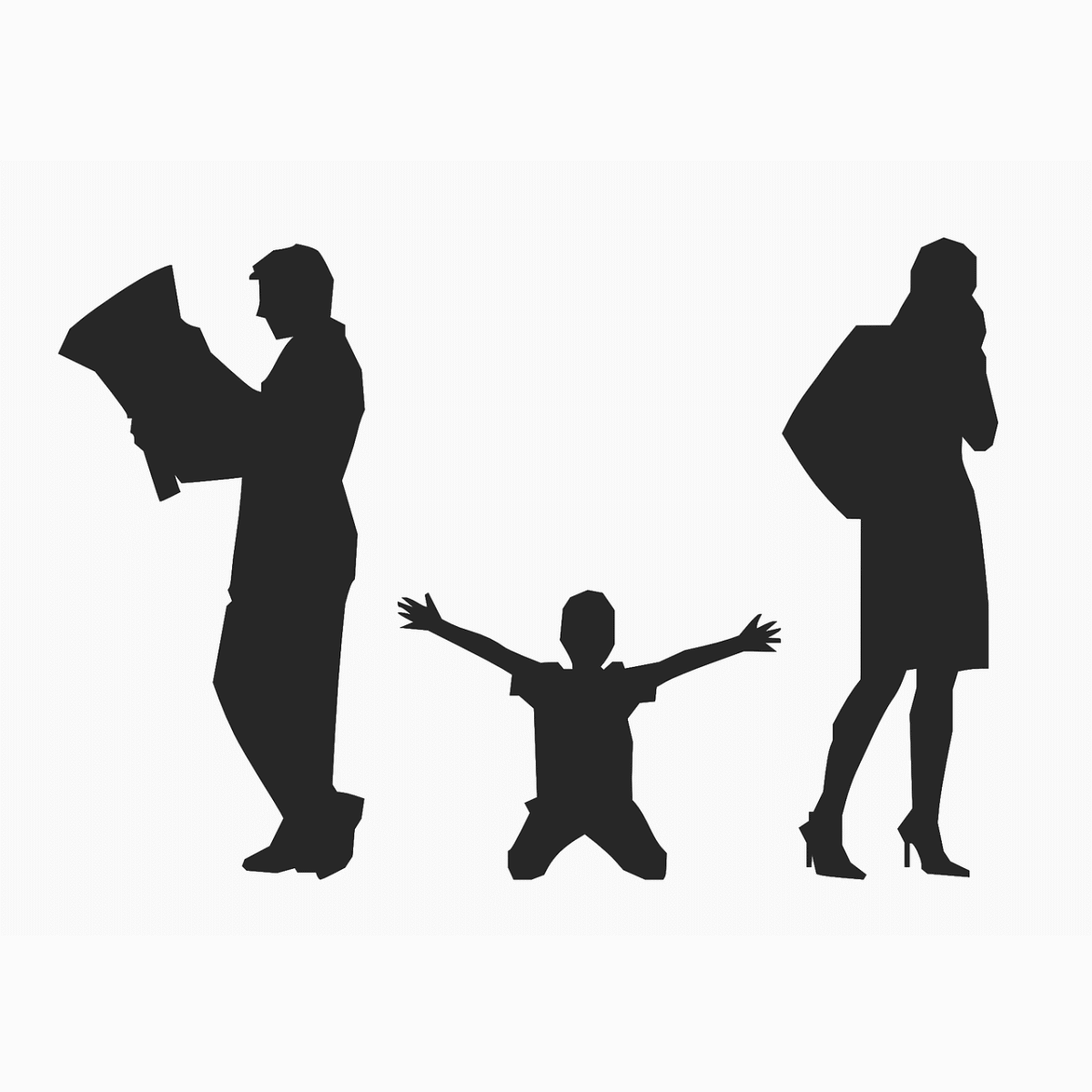
アダルトチルドレンの歴史を振り返ると、「アダルトチルドレン」という概念は、当初「アルコール依存症の親のもとで育った人」=「アダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス」=「ACOA」のことだけを指していました。
うらを返せば、当初、アダルトチルドレンの原因は、あくまで「アルコール依存症の親」に限られて考えられていました。
ですが、1980年代の後半に入るとさらに研究が進み、「アルコール依存症ではない親」であっても、アダルトチルドレンの原因になり得ることがわかってきました。
「アダルトチルドレンの原因」について研究が進む
1980年代の後半になると、「アルコール依存症の親」に限らず、薬物依存症、ギャンブル依存症、拒食、過食、暴言、暴力、引きこもりなど、「嗜癖者である親のもとで育った人」にも、「ACOA」と同じような特徴が見られることがわかってきました。
嗜癖(しへき、addiction)とは、精神医学の用語。アディクションともいう。…(中略)…一般的に「嗜癖」の用語は「嗜癖薬(嗜癖性薬物)」「アルコール嗜癖」あるいは「物質嗜癖」のように用いられる。
引用元:嗜癖とは
このように、当初「アダルトチルドレンの原因」は、「アルコール依存症の親」に限られて考えられていましたが、1980年代の後半になると、「アルコール依存症の親」に限らず、依存症を抱える親、虐待を行う親、ネグレクトを行う親、過干渉な親、過保護な親など、「子どもが安心できない子育てをする親」の全てが、アダルトチルドレンの原因になり得ることがわかってきました。
「アダルトチルドレン・オブ・ディスファンクショナルファミリー(ACOD)」
このとき、「『子供が安心できない子育てをする親』のもとで育ったことが原因で、『ACOA』と同じように、『対人関係の問題』や『生きづらさ』に悩み苦しんでいる人たち」を、「アダルトチルドレン・オブ・ディスファンクショナルファミリー(Adult Children of Dysfunctional Family)」と呼ぶようになりました。
そして、「アルコール依存症の親」を原因とする「アダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス(ACOA)」と区別するために、「アダルトチルドレン・オブ・ディスファンクショナルファミリー(Adult Children of Dysfunctional Family)」は「ACOD」と略されました。
「機能不全家族」と「アダルトチルドレン」の関係
そして、アルコール依存症の親がいる家庭も含め、「親や家族がさまざまな問題を抱えていることが原因で、子どもが安心して生活できない緊張や不安をはらんだ家庭」のことを「機能不全家族」と呼び、「機能不全家族」は「アダルトチルドレン」と密接な関係があることがわかってきました。
機能不全家族とは、ストレスが日常的に存在している家族状態のことです。主に親から子どもへの虐待・ネグレクト(育児放棄)・子どもに対する過剰な期待などの様々な要因が家庭内にあり、子育てや生活などの家庭の機能がうまくいっていない状態です。
このように、アダルトチルドレンの原因は、アルコール依存症の親に限らず、「子どもを否定する親」「子どもを放置する親」「過干渉な親」「過保護な親」など、子どもにとって不適切な養育をする親や家族の全てに拡大し、「アダルトチルドレン」という概念も、「ACOA」から「ACOD」へと拡大していきました。
アダルトチルドレン「AC概念」という捉え方
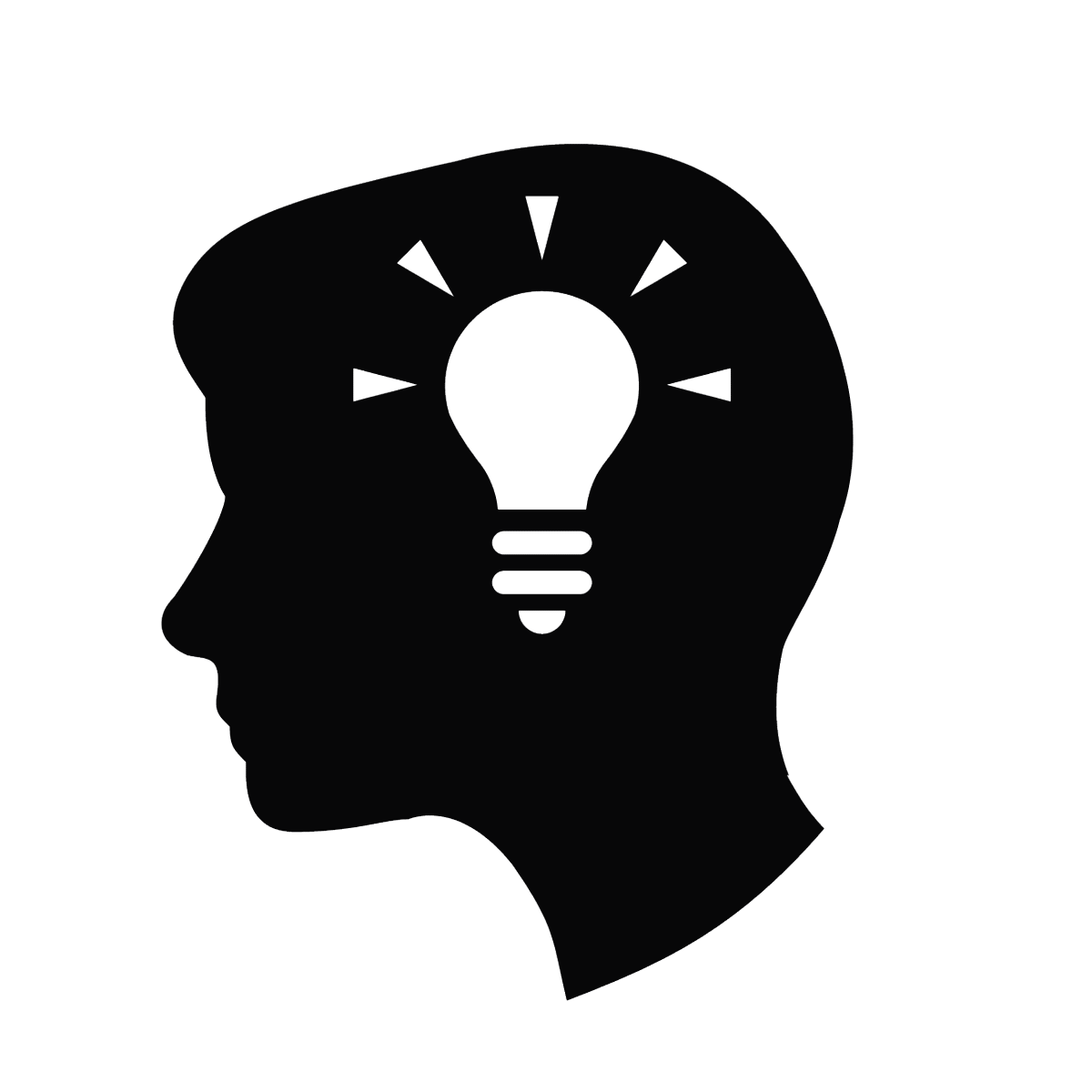
「アダルトチルドレン(AC)」という用語が広がり始めると、その言葉の意味や使い方を巡って問題が生じ始めました。
「アダルトチルドレン(AC)」とは、その用語が示す意味合いが広いため、しばしば「何を指す用語なのか?」が議論の的となってきました。
「AC概念」とは?
その結果、「アダルトチルドレン(AC)」という用語は、人が感じる心の不調・性格的な特徴・心身の症状などのひとつの捉え方=「概念」のひとつとして捉えるようになり、「AC概念」と呼ばれるようになりました。
アダルト・チルドレン(Adult Children:以下AC)とは、子どものころに、家庭内トラウマ(心的外傷)によって傷つき、そしておとなになった人たちを指します。…(中略)…ACの概念は1970年代にアメリカで提唱され始めました。
引用元:アダルト・チルドレンってなに
つまり「アダルトチルドレン(AC)」を「精神医学」の概念で表現すると、「アダルトチルドレン(AC)」とは、「うつ病」「依存症」「躁うつ病」「適応障害」「パニック障害・不安障害」「パーソナリティ障害」「PTSD」などの「精神疾患を患いやすい人」と言い換えることができます。
また、「アダルトチルドレン『AC概念』とは何か?」については、以下の記事で詳しく説明していますので、興味のある方は参考にしてください。
アダルトチルドレンの歴史、日本での広まり
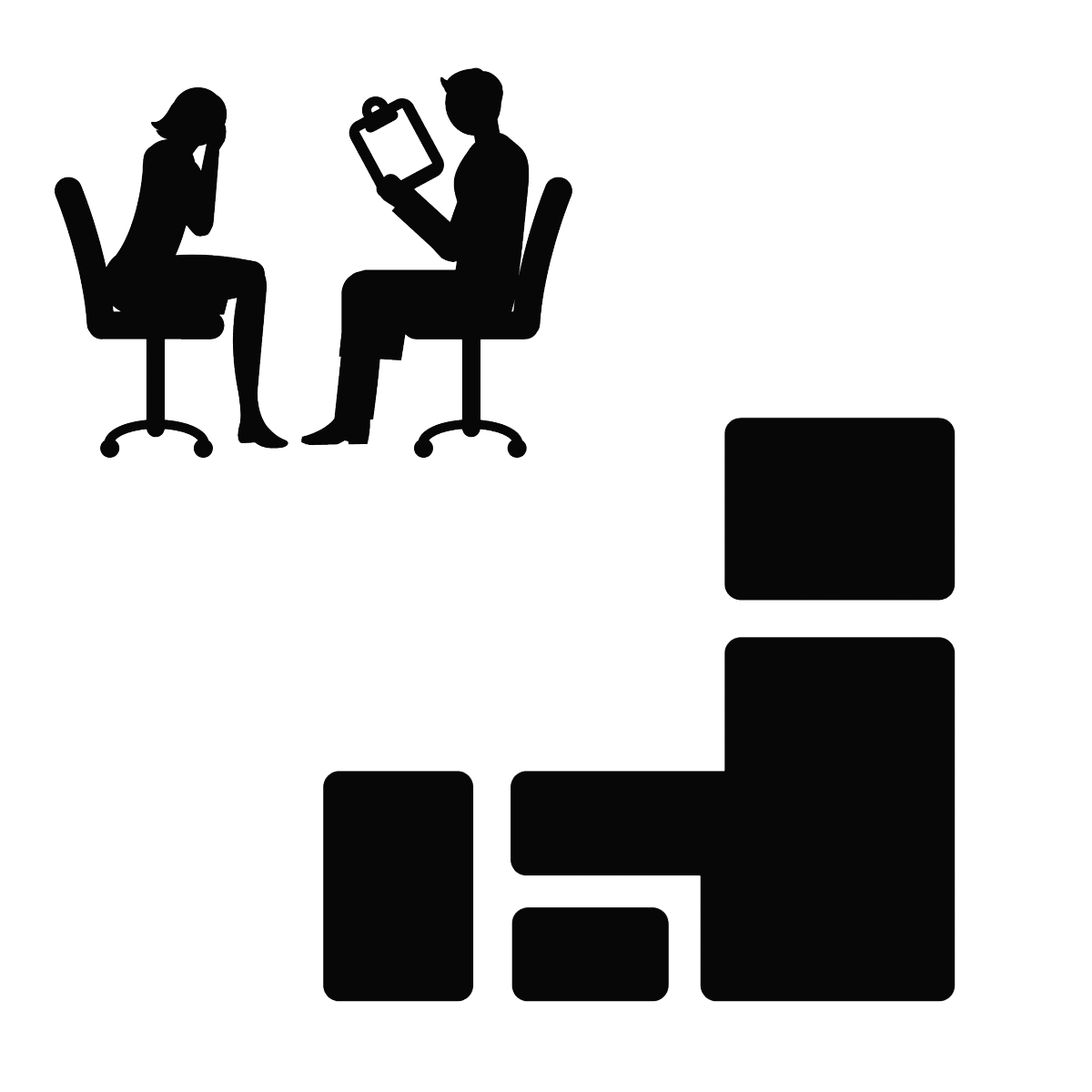
日本でのアダルトチルドレンの歴史は、「クラウディア・ブラック」が1981年に出版した「私は親のようにならない『It will never happen to me』」を、1989年に「斎藤学(さいとうさとる)」氏が翻訳した「私は親のようにならない~アルコホリックの子供たち~」という本が出版され、大きな反響を呼んだことから始まりました。
日本では1990年代に広がり始める…
その後、1995年には「西山明」氏の著書「アダルトチルドレン~自信はないけど、生きていく~」、1996年には「大越嵩」氏の著書「アダルトチャイルド物語~機能不全家族で育った子供たちへ~」など、アダルトチルドレンに関する書籍が次々と出版されたことで、1990年代、「アダルトチルドレン」という概念は日本でも広がり始めます。
日本における「アダルトチルドレン」とは「機能不全家族で育ったアダルトチルドレン」
このように、1990年代、「アダルトチルドレン(AC)」という概念は、日本において一大ブームとなります。
その反面、急激に広まったことによって、「アダルトチルドレン(AC)」という用語が、あたかも診断名や病気であるかのような誤った流布がなされてしまった部分もあり問題も生じました。
このように、「アダルトチルドレン(AC)」とは、「スポーツマン」や「ベジタリアン」といった用語と同じように、「人それぞれが持つ個性」を表す概念のひとつであり、病気や診断名といったものではありません。
なので、今日の日本において、「アダルトチルドレン(AC)」と言えば、「ACOD」のこと、すなわち「機能不全家族で育ったアダルトチルドレン」のことだと捉えることが一般的です。
また、「自分は機能不全家族で育ったのか?」については、、以下の「機能不全家族チェックリスト」でチェックすることができますので、興味のある方は参考にしてください。
まとめ
さいごに、アダルトチルドレンの歴史について重要ポイントをまとめます。
POINT
- 「アダルトチルドレン」という概念は、カナダの「マーガレット・コーク」が1969年に出版した「忘れられた子どもたち~アルコール依存症の親に育てられた子どもについて~」という本から始まった
- アダルトチルドレンの歴史は、アメリカの「国立アルコール乱用とアルコール依存症研究所(NIAAA)」により、「アルコール依存症を親に持つ子供たちの研究」が開始されたことをきっかけに、1970年代のアメリカの「アルコール依存症の治療現場」で広がり始めた
- 1980年代に入り、アメリカの社会心理学博士「クラウディア・ブラック」や、アメリカの心理学者「ジャネット・ウォイティッツ」などが、アダルトチルドレンに関する本を出版しベストセラーとなったことから、アメリカで「アダルトチルドレン」という概念が定着していった
- 1980年代の後半に入ると、アダルトチルドレンの原因は、アルコール依存症の親に限らず、依存症を抱える親、虐待を行う親、ネグレクトを行う親、過干渉な親、過保護な親など、「子どもが安心できない子育てをする全ての親」に拡大し、「アダルトチルドレン・オブ・ディスファンクショナルファミリー(機能不全家族で育ったアダルトチルドレン)」という言葉が生まれた
- アダルトチルドレンの歴史の中で、「アダルトチルドレン(AC)」という用語は、「人が感じる心の不調・性格的な特徴・心身の症状などを表す概念のひとつ」と定義づけられ、「AC概念」と呼ばれるようになった
- 日本でのアダルトチルドレンの歴史は、アメリカの「クラウディア・ブラック」が1981年に出版した「私は親のようにならない」を、1989年に「斎藤學(さいとう・さとる)」氏が翻訳出版したことから始まった
- アダルトチルドレンの歴史の中で、現在の日本における「アダルトチルドレン(AC)」とは、「機能不全家族で育ったアダルトチルドレン」を指すことが一般的となっている
このように、アダルトチルドレンについては研究が進み、現在では心理カウンセリングを始め、さまざまな克服方法が確立されています。
「アダルトチルドレンの克服方法に沿った心理カウンセリング」については、以下の記事で詳しく説明していますので、是非、参考にしてください。
また、「自分はアダルトチルドレンなのか?」については、以下の「アダルトチルドレン(ac)チェックリスト」でチェックすることができますので、興味のある方は参考にしてください。
また、アダルトチルドレンの歴史に関する関連記事を以下に紹介します。
是非、あわせてお読みください。
関連記事
参考サイト
本記事の作成に関する「参考サイト」は以下です。
なお、本記事に関する関連情報は、以下のページでもまとめていますのであわせて紹介します。
関連情報まとめページ
以上、「アダルトチルドレンの歴史」という記事でした。