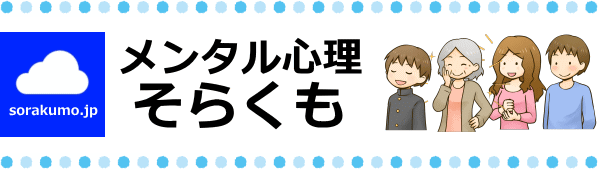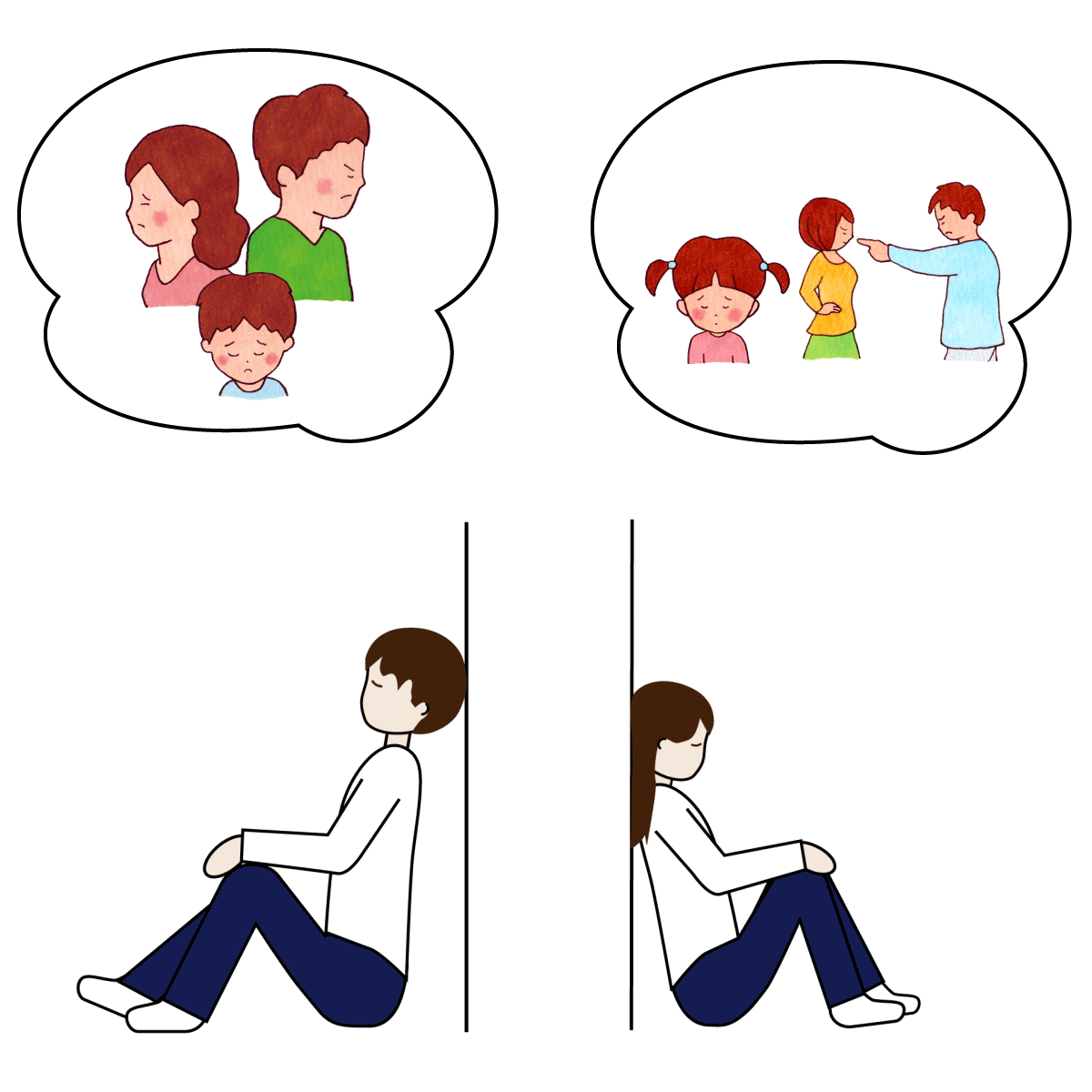
POINTアダルトチルドレンの原因は、「機能不全家族」「毒親」「負の世代間連鎖」などの「環境的原因」と、「未完の感情(幼少期トラウマ)」「人生脚本(禁止令・ドライバー)」などの「心理的原因」が考えられます。
心理カウンセラーの寺井です。
「アダルトチルドレン」とは、子ども時代の家庭環境において、親や家族との間で何らかのトラウマ(心的外傷)を負ったことが原因で、大人になって生きづらさを感じている人たちを指す言葉です。
アダルト・チルドレン(Adult Children:以下AC)とは、子どものころに、家庭内トラウマ(心的外傷)によって傷つき、そしておとなになった人たちを指します。…(中略)…ACの概念は1970年代にアメリカで提唱され始めました。
引用元:アダルト・チルドレンってなに
このように、「アダルトチルドレンの原因」とは、「アダルトチルドレンが生まれる理由である『環境的原因』」と「アダルトチルドレンが生きづらさを感じる理由である『心理的原因』」に分けることができます。
ですが、アダルトチルドレンが感じる生きづらさの根本原因とは、あくまで「子どもの頃に負ったトラウマ(心的外傷)」などの「心理的問題」であるため、いくら「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」が解決されても、アダルトチルドレンの生きづらさが解決されるわけではないと言えます。
それどころか、「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」の解決を目指せば目指すほど、かえって「親」や「家族」に「執着」してしまい、結果として「共依存」に陥ってしまう可能性があります。
反対に言えば、例え「親」や「家族」などの「家庭環境の問題」が解決されなくても、「子どもの頃に負ったトラウマ(心的外傷)」などの「心理的な問題」さえ解決することができれば、アダルトチルドレンが感じる生きづらさを改善することができると言えます。
よって、「アダルトチルドレンの克服」とは、「親」や「家族」など「家庭環境の改善」を意味するのではなく、自らの「感情」や「考え方」など「心理的な問題の解決(生きづらさの改善)」を意味するものです。
そして、「心理カウンセリング」と「インナーチャイルドセラピー」を用いる方法は、「アダルトチルドレンの生きづらさの改善」にとても有効であると言われています。
この記事は、アダルトチルドレンの原因について解説しています。
アダルトチルドレン「環境的原因」と「心理的原因」
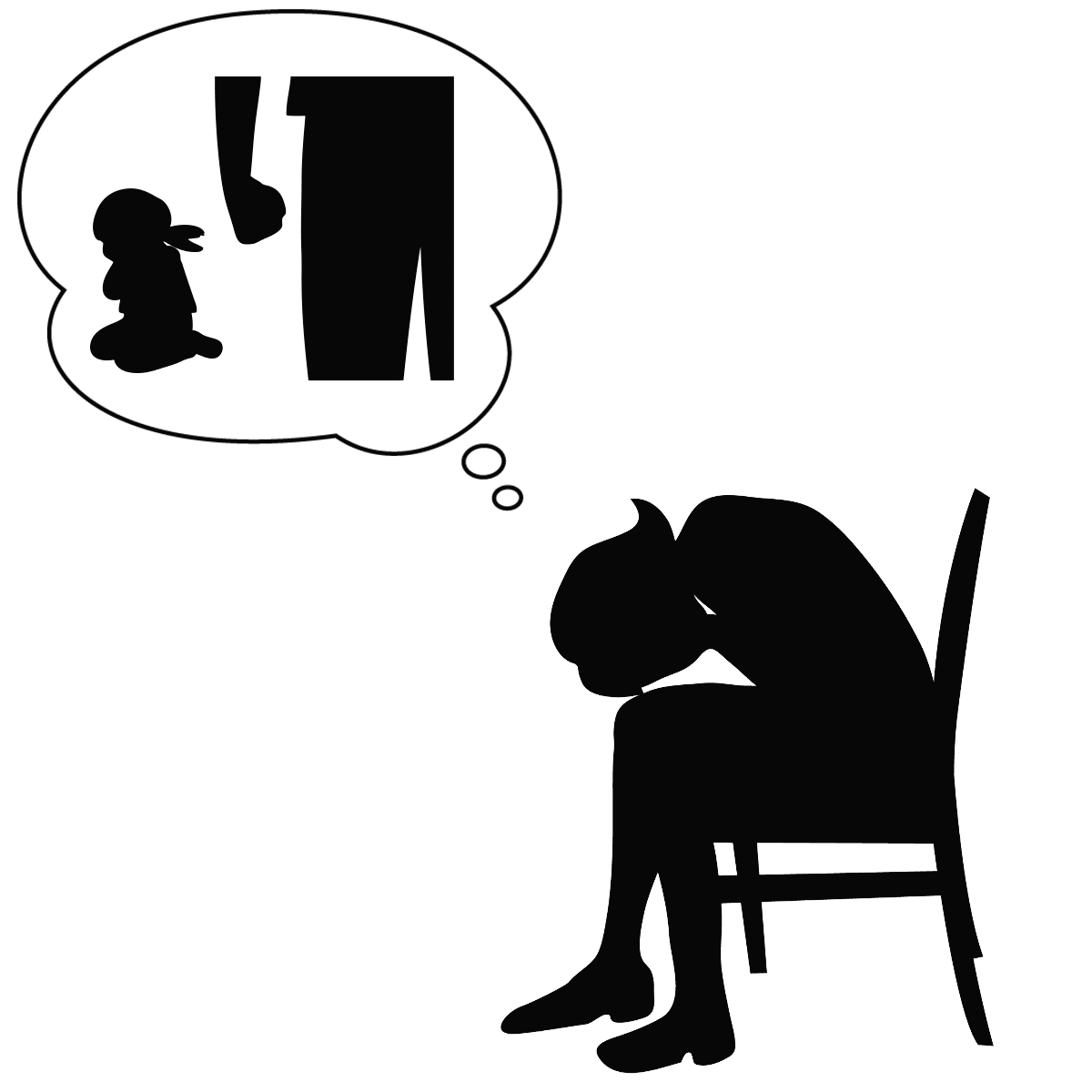
日本でも「三つ子の魂百まで」という諺がある通り、子どもの頃に身に付けた「思考・行動パターン(性格パターン)」は、年齢を重ねても自らの人生に大きな影響を与え続けます。
「三つ子の魂百まで」とは「幼い頃に体得した性格はいくら年をとっても変わるものではない」「幼い頃に出来上がった性質は一生変わらない」という意味のあることわざです。
引用元:「三つ子の魂百まで」の意味とは?
よって「アダルトチルドレンの原因」は、子どもの頃の「親子関係」や「家庭環境」と密接な関係にあると言えます。
ですが、「アダルトチルドレン」になるかどうかは、「親子関係や家庭環境など『環境的原因』」のみで決まるわけでなく、「子どもの性格やストレス耐性など『心理的原因』」も大きく影響しています。
以上のことから、「アダルトチルドレンの原因」は、以下のように「環境的原因」と「心理的原因」に分けて考える必要があります。
アダルトチルドレンの原因
①アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」
- ①-1「機能不全家族」
- ①-2「毒親」
- ①-3「負の世代間連鎖」
②アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」
- ②-1「未完の感情(幼少期トラウマ)」
- ②-2「人生脚本(禁止令・ドライバー)」
それでは、以下に詳しく解説していきます。
原因①-1:機能不全家族
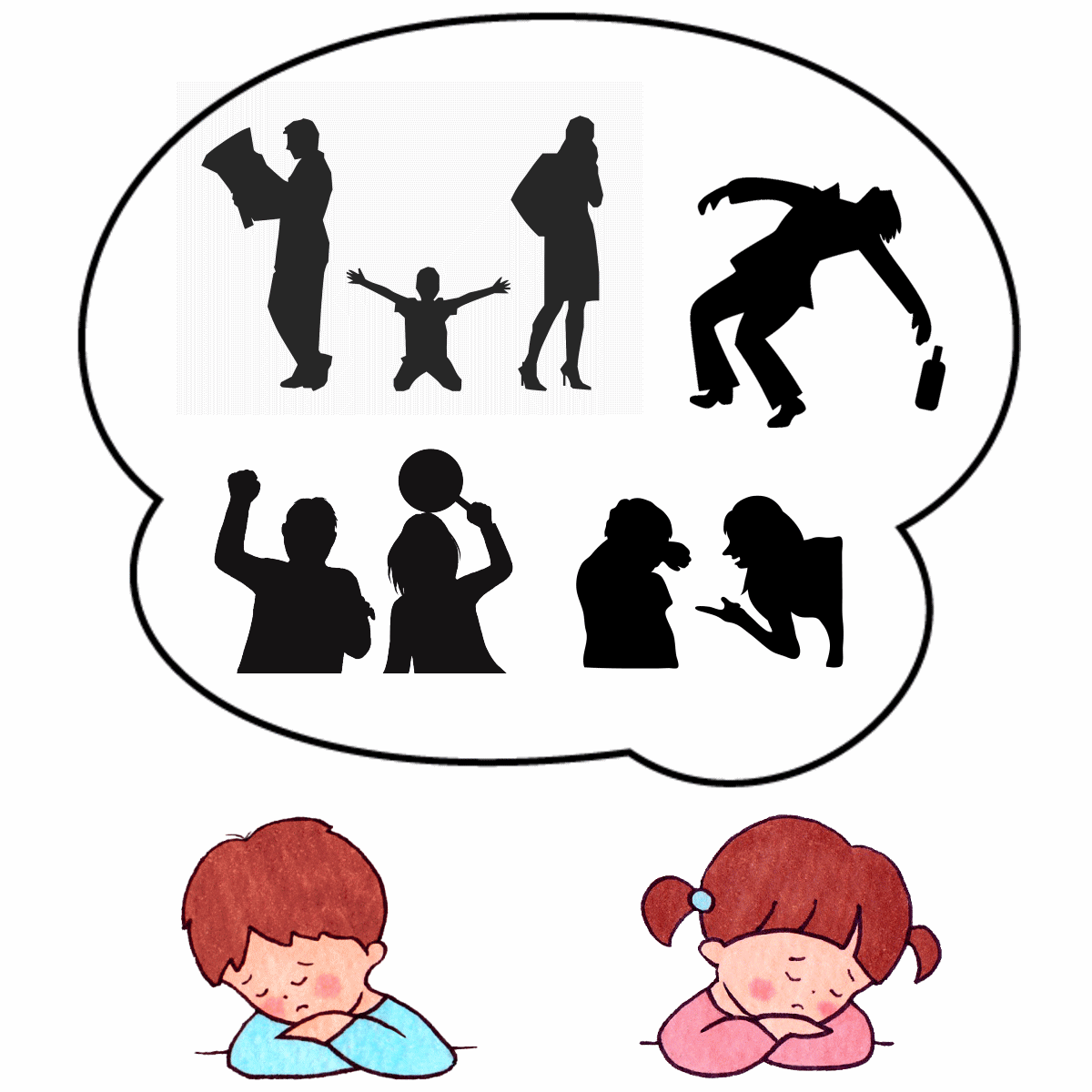
そもそも「アダルトチルドレン(AC概念)」とは、1970年代、「アメリカのアルコール依存症の治療現場」から広がり始めた考え方です。
1970年代、アメリカの「国立アルコール乱用とアルコール依存症研究所(NIAAA)」の研究により、「アルコール依存症の親を持つ子どもたちは、大人になったとき『対人関係の問題』や『生きづらさ』を抱えやすい」ということがわかってきました。
アダルトチルドレンの概念が誕生した背景には、アルコール依存症の親を持つ子どもたちが、大人になった際に生きづらさを感じていることが多いと判明したためです。現在ではアルコール依存症だけにとどまらず、身体的虐待や言葉の暴力、ネグレクトなど、さまざまな家庭問題が影響していると考えられています。
その後、1980年代に入るとさらに研究が進み、「アルコール依存症の親」に限らず、「薬物・ギャンブル・仕事などの依存症を持つ親」「拒食・過食などの嗜癖を持つ親」「暴言・暴力・ネグレクトなどの虐待を行う親」「過干渉な親・過保護な親」など、「子どもが安心できない子育てをする親の全てがアダルトチルドレンの原因になり得る」ことがわかってきました。
「機能不全家族」とは、「アダルトチルドレンの原因となる家族」
そして、アルコール依存症の親がいる家庭も含め、上記のように「親や家族がさまざまな問題を抱えていることが原因で、子どもが安心して生活できない緊張や不安をはらんだ家庭」のことを「機能不全家族」と呼び、「機能不全家族で育った影響により、大人になってからも生きづらさや心に傷を抱えている人」を「アダルトチルドレン」と呼ぶようになりました。
「アダルトチルドレン」とは、機能不全家族で育ったことにより、「親から守られる」「適切な教育を受ける」などの正常な成長過程をたどれず、成人してからも生きにくさや心に傷を抱えている人のことをさします。
このように、「機能不全家族とは、アダルトチルドレンの原因となる家族」を意味し、具体的には以下のような意味合いがあります。
機能不全家族の意味合い
- 子どもが日常的にストレスを感じている家族
- 家庭の本来の働きがうまく機能していない家族
- 子どもが心身共に健全に成長していくために必要なものを満たすことができていない家庭
- 子どもの健全な成長を阻害してしまう可能性がある家族
以上のことから、「機能不全家族」とは、アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」のひとつと考えられます。
なお「機能不全家族」については以下の記事で詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
原因①-2:毒親
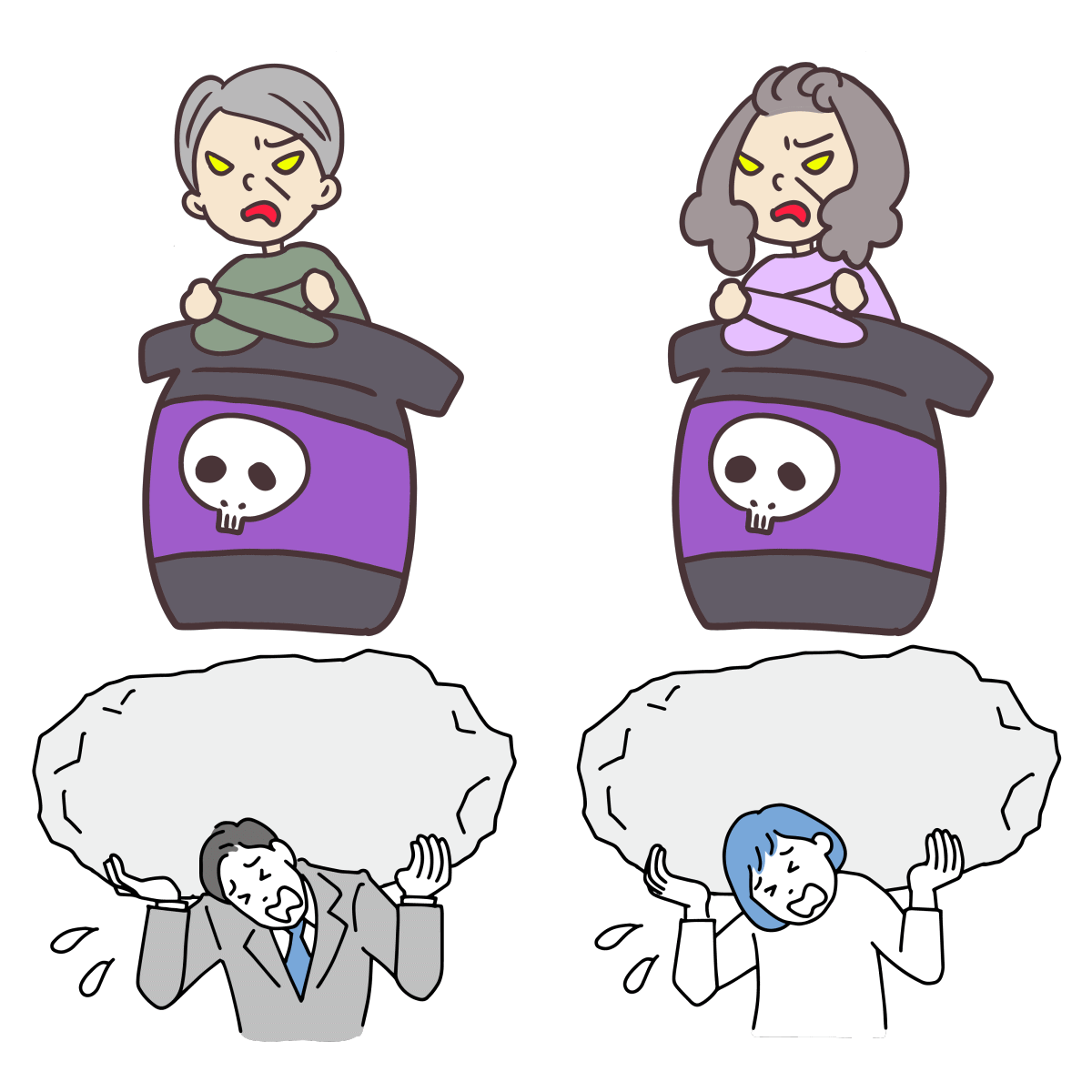
前述の通り「機能不全家族とは、アダルトチルドレンの原因となる家族」であり、「機能不全家族とは、家庭が果たすべき役割がうまく機能していない家庭」を意味します。
機能不全家族とは、家庭内で弱い立場にある人に対して、身体的または精神的ダメージを与える機会が日常的に存在している家族状態のことをいいます。…(中略)…機能不全家族においてダメージを受ける存在は、家庭内で弱い立場になりやすい高齢者や子どもである場合がほとんどです。…(中略)…その原因は子どもの保護者が招いている場合がほとんどです。
反対に言えば、そもそも「家庭」とは「親」や「祖父母」など「大人」が中心となって営むものですので、機能不全家族の原因は「子ども」にあるのではなく、「親」や「祖父母」といった「大人」にあると言えます。
そして「家庭」の中心を担っているのは、ほとんどの場合「祖父母」よりも「親」である場合が多いと言えます。
よって、機能不全家族を引き起こしている原因も、ほとんどの場合「親」である場合が多いと言えます。
「毒親」とは、「アダルトチルドレンの原因となる親」
そして、「本来、家庭が果たすべき役割をうまく果たせない親」のこと、すなわち「機能不全家族の原因になる親」を「毒親」と呼びます。
毒親(どくおや、英: toxic parents)は、毒になる親の略で、毒と比喩されるような悪影響を子供に及ぼす親、子どもが厄介と感じるような親を指す俗的概念である。1989年にスーザン・フォワード(英: Susan Forward)が作った言葉である。学術用語ではない。
引用元:毒親
このように、「毒親とは、アダルトチルドレンの原因となる親」を意味し、具体的には以下のような意味合いがあります。
毒親の意味合い
- アルコール・薬物・ギャンブル・仕事などの依存症を持つ親
- 拒食・過食などの嗜癖を持つ親
- 暴言・暴力・ネグレクトなどの虐待を行う親
- 過干渉な親・過保護な親
このような「特徴」を持つ親から子育てを受けた場合、子どもは家庭にいながら日常的にストレスを感じ続ける可能性があります。
以上のことから、「毒親」とは、アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」のひとつと考えられます。
なお「毒親」については以下の記事で詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
原因①-3:負の世代間連鎖
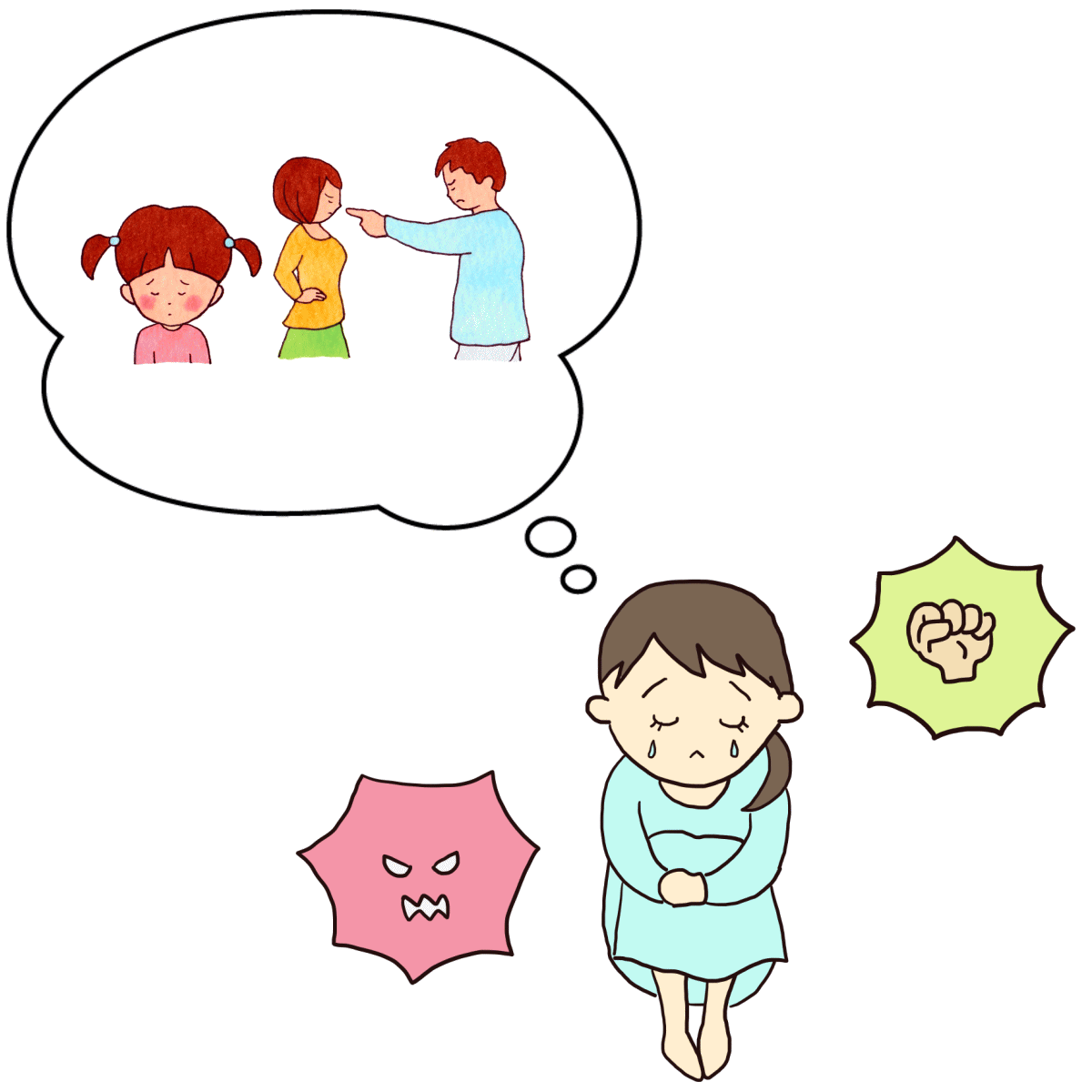 「機能不全家族」とは、「本来、家庭が果たすべき役割がうまく機能していない家族」を指す言葉であり、「アダルトチルドレンを生みだす家族を意味する言葉」として1980年代のアメリカで使われはじめ、1990年代になると日本でも使われ始めました。
「機能不全家族」とは、「本来、家庭が果たすべき役割がうまく機能していない家族」を指す言葉であり、「アダルトチルドレンを生みだす家族を意味する言葉」として1980年代のアメリカで使われはじめ、1990年代になると日本でも使われ始めました。
そして、「アダルトチルドレン(AC概念)」を日本に取り入れた専門家の一人であり、「アダルトチルドレン」や「DV問題」に精通する臨床心理学博士の「西尾和美氏」は、「機能不全家族」について以下のように述べています。
日本の家族の80%が機能不全を起こしている。その原因は、父親業・母親業の仕方にある…。
このように、日本において数多くのアダルトチルドレン関連書籍を出版している「西尾和美氏」は、「機能不全家族-「親」になりきれない親たち」という著書の中で、アダルトチルドレンの原因になる「機能不全家族」について、「日本の家族の8割以上が機能不全家族である」と述べています。
「負の世代間連鎖」とは、「アダルトチルドレンの問題が連鎖する原因」
また、アダルトチルドレン研究の専門家たちは「機能不全家族」について、以下の特徴を指摘しています。
機能不全的な家庭となっている場合は、その家庭を構成する親、または祖父母などが、機能不全家族で育った可能性もある。
引用元:機能不全家族|Wikipedia
以上のことから、アダルトチルドレンの原因となる「機能不全家族」には、以下のような特徴があると言えます。
機能不全家族の連鎖
- 家庭が「機能不全状態」である場合、機能不全家族の原因である「親」自身が、子どもの頃に「機能不全家族」で育った可能性が高い
- また、「親」の「親(祖父母)」も、子どもの頃に「機能不全家族」で育った可能性が高い
このように、人は「子どもの頃、親にしてもらった子育て方法を、自分が親になったとき、自分の子どもに繰り返す(世代間連鎖)」という特徴があり、子どもの頃、自分が親にされて辛く苦しかった「子育てによる負の影響」を、大人になって自分の子どもへと無意識に繰り返してしまうことを、心理学では「負の世代間連鎖」と言います。
負の世代間連鎖とは、「親(又は親から上の世代)から引き継いだ負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」を指します。世の中の親子問題を抱えている人の多くが、「親を介してこの負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」に巻き込まれたことによって、様々な問題を抱えてしまうようになったことを知ることはとても大切なことです。
引用元:親子の問題①(世代間連鎖)
このように、「負の世代間連鎖」とは、決して「親が意図的に起こしている問題」ではなく、曾祖父母から祖父母へ、祖父母から父母へと「無意識に連鎖している」と言えます。
反対に言えば、「機能不全家族」も「毒親」も「アダルトチルドレン」も、決して「親が意図的に起こしている問題」ではなく、曾祖父母から祖父母へ、祖父母から父母へと「負の世代間連鎖によって無意識に連鎖している問題」と言えます。
以上のことから、「負の世代間連鎖」とは、アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」のひとつと考えられます。
なお「負の世代間連鎖」については以下の記事で詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
原因②-1:未完の感情(幼少期のトラウマ)
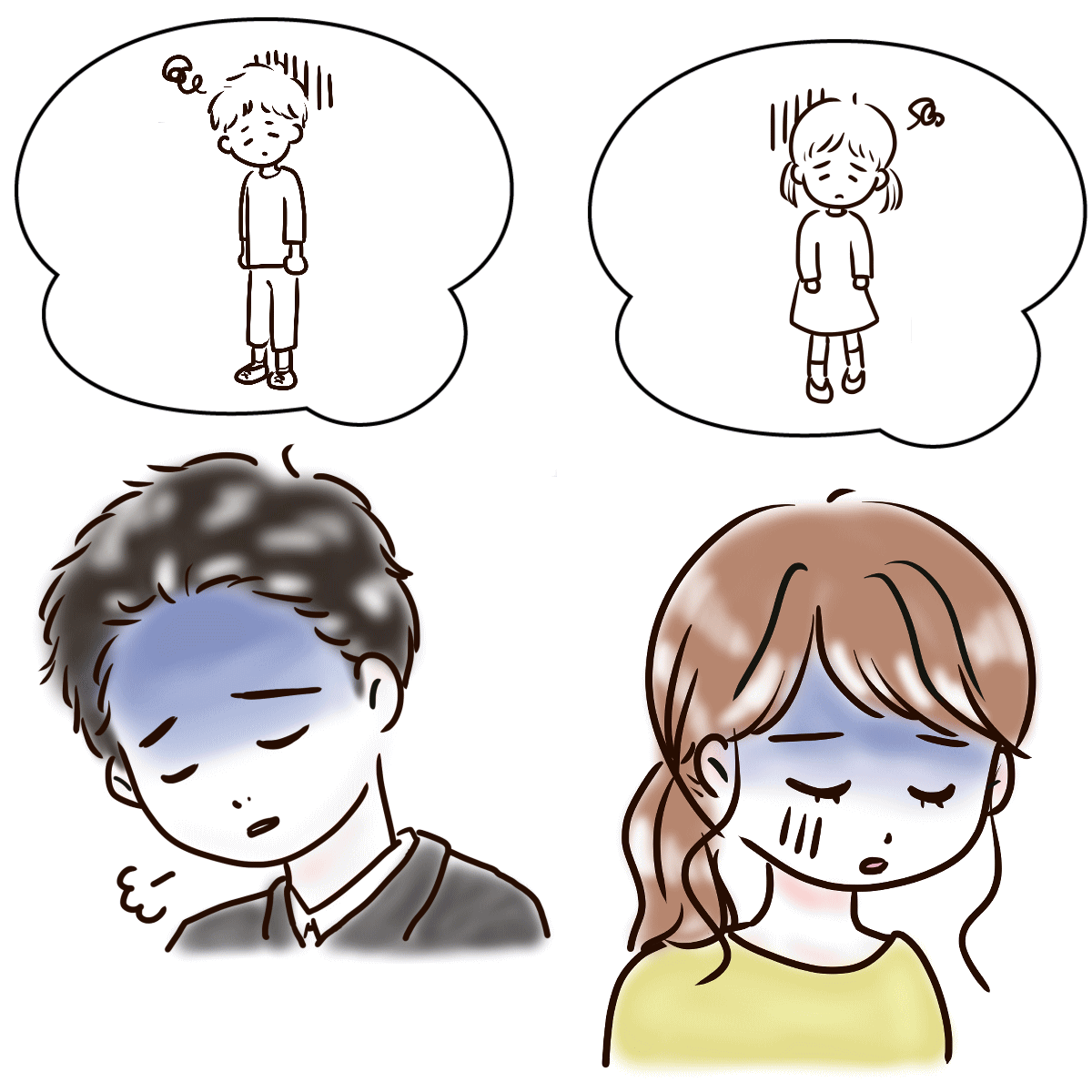
前述の通り、アダルトチルドレンとは「機能不全家族で育った(毒親に育てられた)影響によって心に傷を負い、『心の傷』を抱えたまま大人なり、その『心の傷』が原因で生きづらさを感じている人」を指します。
そして、アダルトチルドレンが子どもの頃に「機能不全家族」や「毒親」の影響で負ってしまった「心の傷」を「トラウマ(心的外傷)」と呼び、子どもの頃に負った「トラウマ(心的外傷)」を「幼少期トラウマ」と言います。
トラウマとは心的外傷、つまり「心の傷」を指します。…(中略)…トラウマは単なるストレスとは意味が異なり、過去に起こったストレスフルな事象が、後の人生に様々な影響を及ぼしているような意味で使われます。
引用元:トラウマに苦しまないために
また、子どもの立場で考えてみれば、無条件で信頼しきっている「親」から理不尽に厳しい仕打ちを受けてしまったわけですから、子どもの心は深く傷つくことになり、そのぶん「大きなトラウマ(心的外傷)」を抱えることになってしまいます。
発達期に受けたトラウマは、その後の人生に影響を及ぼしかねません。今まさに発達期にあるお子さんはもちろん、子どものころにトラウマを負って、癒えないまま大人になったという方は、心の傷による生きづらさを抱えています。
また、親からの理不尽で厳しい仕打ちをうけたなど、大きなショック体験が原因で、時間が経ってもその影響を受け続けることを「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」と言います。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるものです。
引用元:PTSDについて
このように、アダルトチルドレンが負った「幼少期のトラウマ」は、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」などの「精神疾患」を始め、さまざまな「生きづらさの原因」となっていると言えます。
「未完の感情(幼少期トラウマ)」とは、「精神疾患の根本原因」
そして、アダルトチルドレンが負った「幼少期トラウマ」のように、ある時から満たされないまま心に残っている感情を「ゲシュタルト療法」という心理学では「未完の感情」と呼びます。
納得がいかない思いは、行き場がなくて、心のどこかにモヤモヤしたまま残ってしまいます。いわば出口がなくて迷子になってしまった感情。これを「未完の感情」と呼びます。
「未完の感情」とは、具体的には「言いたいけど言えなかったこと」「やりたいけどできなかったこと」など、「子どもの頃に我慢をしたり抑圧した感情、いわゆる『ストレス』のこと」を指し、「子どもの頃、心に『トラウマ(心的外傷)』を負ったのだけれども、グッと心に我慢・抑圧した『寂しさ・悲しさ・怖さ・辛さ』」がそれにあたります。
具体的には、カウンセリングの現場では以下のような「未完の感情」に注目していきます。
「未完の感情」の具体例
- 無性に寂しい、底なしに悲しい、漠然と不安、生き辛い、人目が気になる、イライラが止まらない、怒りが爆発する、どうせわかってくれない、やる気が出ない、眠れない、落ち着かない、嫌われたくない、失敗が怖い、1人が怖い、馬鹿にされたくない、怒られたくない、認めてほしい、褒めてほしい…など
反対に言えば、上記のような「未完の感情」が心に残っている場合、常に大きな「心的負担(ストレス)」を抱え続けていることになり、そのぶん「精神不安定」になりやすく、以下のような「精神疾患」を患いやすくなります。
アダルトチルドレンが患いやすい「精神疾患」
以上のことから、「未完の感情(幼少期のトラウマ)」とは、アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」のひとつと言えます。
なお「未完の感情」については以下の記事で詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
関連記事
原因②-2:人生脚本(禁止令・ドライバー)
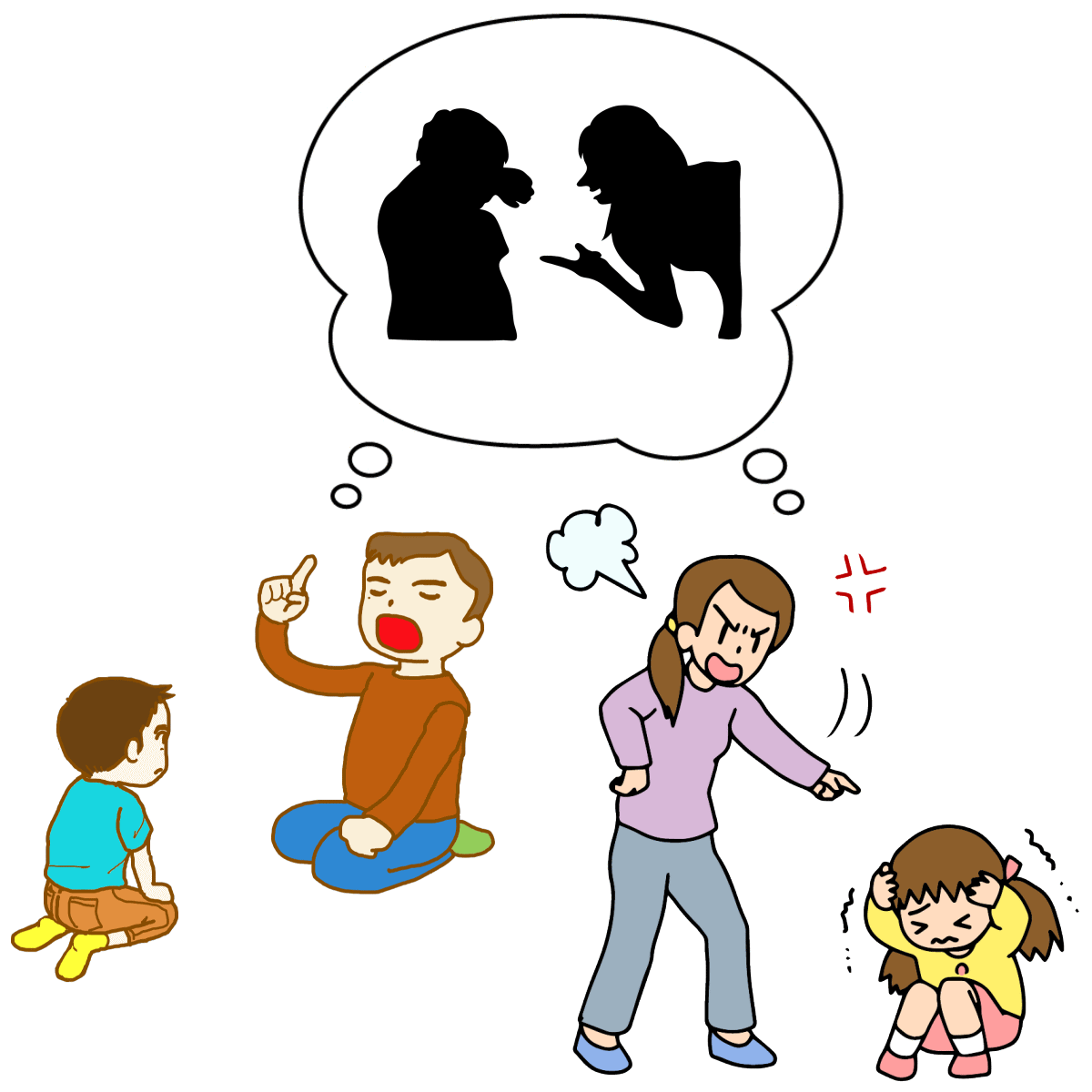
前述の通り、アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」となる「機能不全家族」や「毒親の特徴」は、「負の世代間連鎖」によって、親から子へ、子から孫へと無意識に連鎖していきます。
このように、子どもの頃に親から受けた子育ての影響によって形成され、大人になっても無意識に繰り返されている「思考・行動パターン(性格パターン)」を「交流分析」という心理学では「人生脚本」と言います。
人生脚本とは、エリック・バーンが提唱した心理学理論です。幼少期に自分自身の人生脚本を描き、その通りになるとされています。人生脚本の大部分は親からのメッセージにより決定されます。無意識のうちに生き方を決め、それに従い行動するということです。
引用元:人生脚本とは
「人生脚本」は、幼少期(おおよそ6歳頃まで)に「親に言われたメッセージ」や「親にされた行動」などに基づいて形成され、人はそれ以降、人生脚本に沿って無意識に生き方を決めるようになり、人生脚本に従った「思考・行動パターン」を無意識に繰り返すようになると考えられています。
反対に言えば、アダルトチルドレンとは、「子どもの頃、親から厳しい言葉を言われて育った人」や「子どもの頃、親から暴言・暴力を受けて育った人」を指す言葉であり、そのぶん「機能不全家族」や「毒親」から受けた「厳しい言葉」や「暴言・暴力のイメージ」は、アダルトチルドレンの「思考・行動パターン」に大きく影響していると言い換えることができます。
このように、子どもの頃に身に付けた「人生脚本」は、親子・家族・友人・恋愛・結婚・子育て・仕事など、「他者との人間関係の築き方」に大きな影響を与えており、さまざまな「生きづらさの原因」となっていると考えられています。
「禁止令」とは、「自らの感情を我慢・抑圧する思考癖」
また、「人生脚本」と呼ばれる「思考・行動パターン」は、大きく分けて、以下の2つの「価値観」で形成されています。
「人生脚本」2つの価値観
- 「禁止令」…「○○してはダメだ!」など、親が子どもに対して何かを禁止する言葉を掛けたことにより、子どもが大人になっても「自分は○○してはダメだ!」と思い込み続けている価値観
- 「ドライバー」…「もっと○○しなさい!」など、親が子どもに対して何かを煽り立てる言葉を掛けたことにより、子どもが大人になっても「自分はもっと○○しなくてはならない!」と思い込み続けている価値観
このように「禁止令・ドライバー」とは、親が子どもに対して「ありのままの感情表現」や「ありのままの自己表現」を否定した言葉であり、子どもの頃に親から言われた言葉のうち、「~するな!」「~しちゃダメ!」「~しないほうがいい!」など、何かを禁止する指示・命令のことを「禁止令」と呼びます。
禁止令とは心理学者エリックバーン博士によって開発された自己分析法で、文字通り「〇〇してはいけない」という「禁止」の「命令」のことです。…(中略)…幼いころに親などの養育者から否定的・禁止的な命令や態度を繰り返し受けることで、自らの思考や行動の制限を課してしまうものです。
そして「禁止令」とは、何かを「我慢」したり「抑圧」する「思考・行動パターン(性格パターン)」となって人生に影響を与え続けています。
具体的には、カウンセリングの現場では以下のような「禁止令」に注目していきます。
「禁止令」の具体例
- 失敗してはいけない、休んではいけない、諦めてはいけない、泣いてはいけない、怖がってはいけない、弱音を吐いてはいけない、他人を信じてはいけない、わがままを言ってはいけない、迷惑をかけてはいけない、幸せになってはいけない、目立ってはいけない…など
反対に言えば、上記のような「禁止令」の影響を強く受けている場合、「自らの感情を我慢・抑圧する思考癖(自己否定感)」を抱え続けていることになります。
以上のことから、「禁止令」とは、アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」のひとつと言えます。
「ドライバー」とは、「自分に厳しくなる思考癖」
同じように、子どもの頃に親から言われた言葉のうち、「~しろ!」「~しなさい!」「~したほうがいい!」など、何かを煽り立てられる指示・命令のことを「ドライバー(拮抗禁止令)」と呼びます。
拮抗禁止令とは、幼少期に親の役割をもつ人から与えられた「〇〇しなさい」「〇〇したほうがよい」「〇〇であるべき」という、いわゆる「〇〇しろ」というメッセージを受けて、そのよう生きていこうと「決断」することで自らに課したものです。…(中略)…ドライバーというその名の通り、その人の行動を駆り立ててしまうのです。
そして「ドライバー」とは、「頑張る」「煽る」という「思考・行動パターン(性格パターン)」となって人生に影響を与え続けています。
具体的には、カウンセリングの現場では以下のような「ドライバー」に注目していきます。
「ドライバー」の具体例
- 完璧でなければならない、もっと頑張らなければならない、限界まで全力を尽くさねばならない、世の中の役に立たねばならない、人に尽くさねばならない、早くしなければならない、もっと強くならなければならない、油断してはならない…など
反対に言えば、「ドライバー」の影響を強く受けている場合、「自分に厳しくなる思考癖(自己否定感)」を抱え続けていることになります。
以上のことから、「ドライバー」とは、アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」のひとつと言えます。
なお「禁止令・ドライバー」については以下の記事で詳しく解説していますので、是非お読み下さい。
「アダルトチルドレンタイプ」それぞれの「生まれる原因」
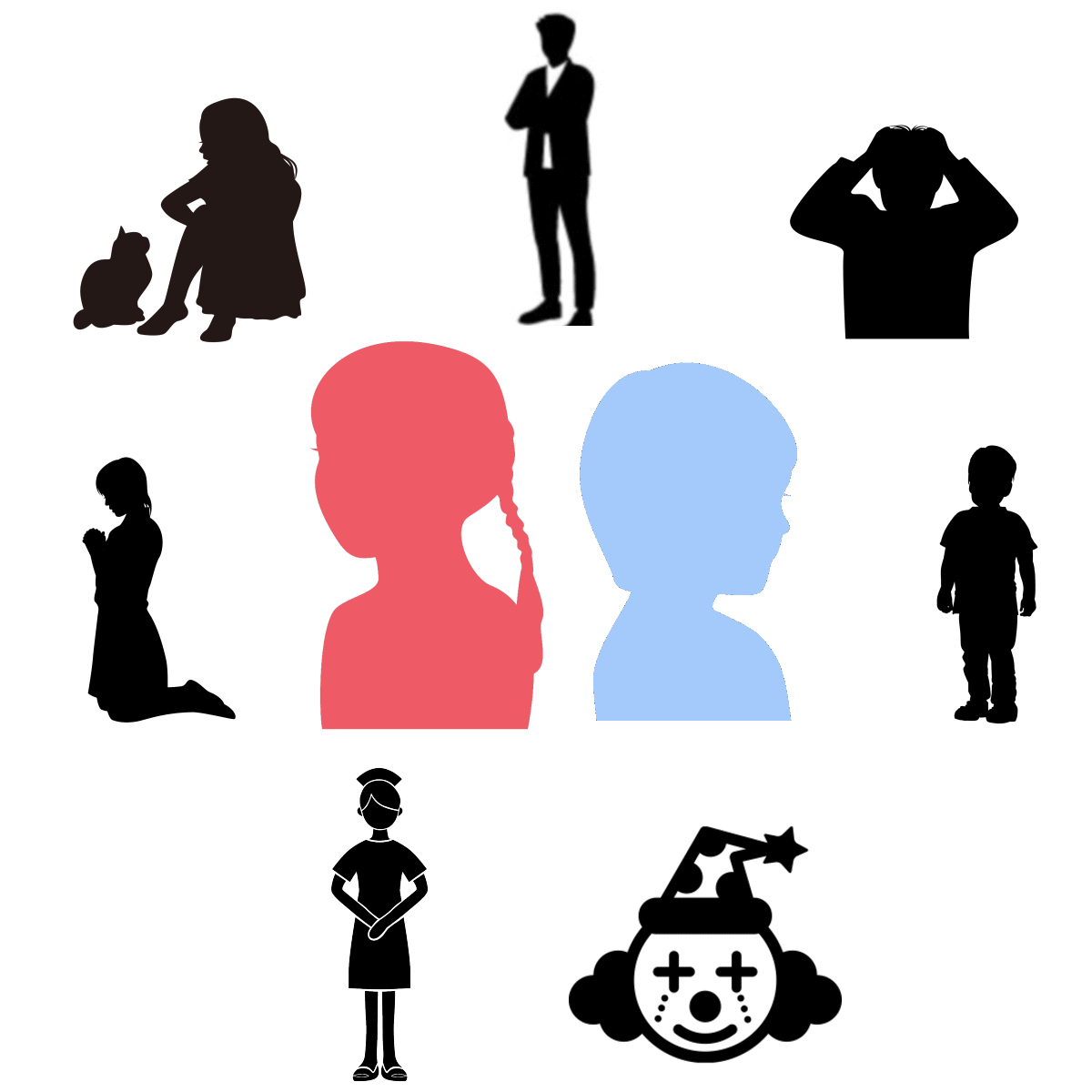
アダルトチルドレンが、子どもの頃に身に付けた「機能不全家族での役割」を、アメリカの心理療法家「ウェイン・クリッツバーグ」は「アダルトチルドレンタイプ」としてまとめました。
「アダルトチルドレンが生まれる原因」は、概ね「各タイプで共通している部分」が多いのですが、厳密に言うと「各タイプで異なる部分」も存在します。
なお、本サイトにおける「アダルトチルドレンタイプ」は以下の「7つ」を使用しており、「アダルトチルドレンタイプ」それぞれの「生まれる原因」については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
アダルトチルドレンの克服
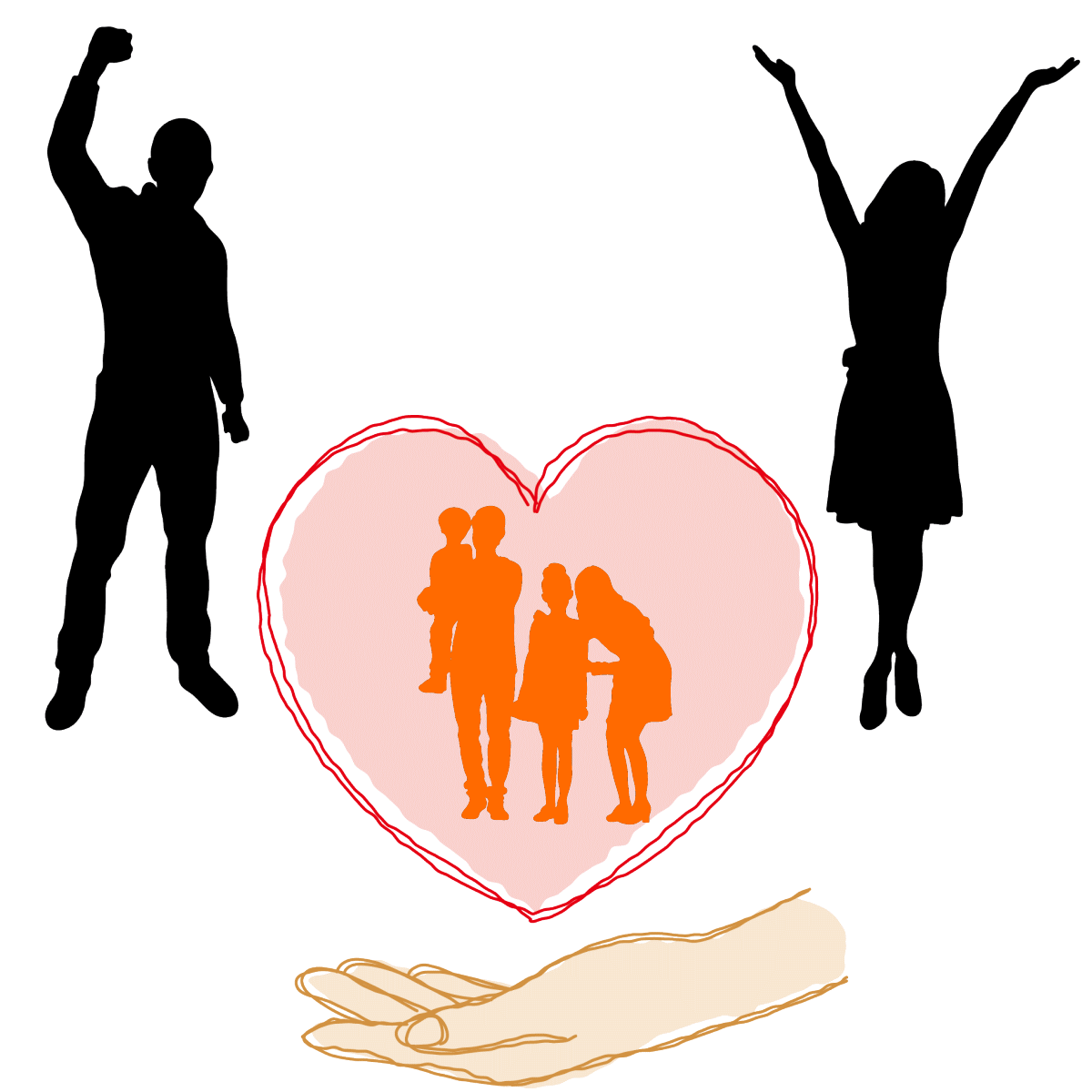
ここまで、アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」と、アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」について解説してきました。
とはいえ、「機能不全家族」や「毒親」などの「環境的原因」を自分にとって望ましい方向に変えようとしても、「親」や「家族」が理解を示して変わってくれない限り、アダルトチルドレンの克服はいつまでも実現できません。
ですが、「未完の感情(幼少期トラウマ)」や「人生脚本(禁止令・ドライバー)」などの「心理的原因」は、自分の内面に存在するものであり、「親」や「家族」が変わらなくとも、自らの「感情」や「考え方」を変えていくことはできます。
反対に言えば、アダルトチルドレンが感じる生きづらさの根本原因とは、「機能不全家族」や「毒親」などの「環境的原因」ではなく、「未完の感情(幼少期トラウマ)」や「人生脚本(禁止令・ドライバー)」などの「心理的原因」にあると言えます。
「アダルトチルドレンの克服」とは、「心理的な問題の解決(生きづらさの改善)」を目指すこと
また、「アダルトチルドレン(AC概念)」の生みの親である「クラウディア・ブラック」も「アダルトチルドレン克服方法」を考えるにあたり、「親」や「家族」などの「環境的原因」ではなく、自らの「感情」や「考え方」などの「心理的原因」に注目しています。
そして、「クラウディア・ブラック」は、「アダルトチルドレンからの回復プロセス」として、次の「4つのステップ」を示しました。
アダルトチルドレン(AC)概念の生みの親であるクラウディア・ブラックは、ACの回復プロセスを次のような4段階で説明しています。
- ステップ1=過去の喪失を探る
- ステップ2=過去と現在をつなげる
- ステップ3=取りこんだ信念に挑む
- ステップ4=新しいスキルを学ぶ
また、「クラウディア・ブラック」が示した「アダルトチルドレンからの回復プロセス」を「具体化」すると以下のようになります。
POINT
- ステップ1=過去の喪失を探る
子どもの頃から自分の中に存在し続けている「幼少期のトラウマ」の存在に気づき、「幼少期のトラウマを治療する(癒す)」 - ステップ2=過去と現在をつなげる
「人生脚本」を原因とする「禁止令・ドライバーの影響」や「幼少期トラウマ」を原因とする「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の影響」が、現在の自分にどのような影響を与えているか?を理解する - ステップ3=取りこんだ信念に挑む
「禁止令・ドライバー」を緩め、「生きづらい『人生脚本』」から「生きやすい『人生脚本』」へと書き換える - ステップ4=新しいスキルを学ぶ
子どもの頃に学べなかった「人間関係の方法」「感情の扱い方」「自分を大切にする方法」を学ぶ
このように、「アダルトチルドレンの克服」とは、「未完の感情(幼少期トラウマ)」や「人生脚本(禁止令・ドライバー)」」などの「心理的な問題の解決(生きづらさの改善)」を目指す場合が多く、そのなかでも「心理カウンセリング」と「インナーチャイルドセラピー」を用いる方法は、「アダルトチルドレンの心理的な問題の解決(生きづらさの改善)」にとても有効であると言われています。
続きは、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
さいごに、本記事の重要ポイントをまとめます。
- POINTアダルトチルドレンの原因は、「親子関係や家庭環境など『環境的原因』」と「子どもの性格やストレス耐性など『心理的原因』」にわけて考える
- アダルトチルドレンが生まれる「環境的原因」は、「機能不全家族」「毒親」「負の世代間連鎖」の3つが考えられる
- アダルトチルドレンが生きづらさを感じる「心理的原因」は、「未完の感情(幼少期トラウマ)」「人生脚本(禁止令・ドライバー)」の2つが考えられる
- 「機能不全家族」とは、「アダルトチルドレンの原因となる家族」を指す
- 「毒親」とは、「アダルトチルドレンの原因となる親」を指す
- 「負の世代間連鎖」とは、「アダルトチルドレンの問題が連鎖する原因」を指す
- 「未完の感情(幼少期トラウマ)」とは、「精神疾患の根本原因」となる
- 「禁止令」とは、「自らの感情を我慢・抑圧する思考癖」を指す
- 「ドライバー」とは、「自分に厳しくなる思考癖」を指す
- 「アダルトチルドレンの克服」とは、「家庭環境の問題を解決する」ことではなく「心理的問題を解決する」こと
- 「心理カウンセリング」と「インナーチャイルドセラピー」を用いる方法は、「アダルトチルドレンの心理的な問題の解決(生きづらさの改善)」にとても有効である
また、本記事に関する関連記事を以下に紹介します。
是非、あわせてお読みください。
関連記事
なお、本記事に関する関連情報は、以下のページでもまとめていますのであわせて紹介します。
関連情報まとめページ
以上、「アダルトチルドレンの原因の解説」でした。