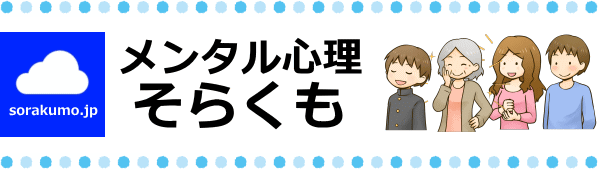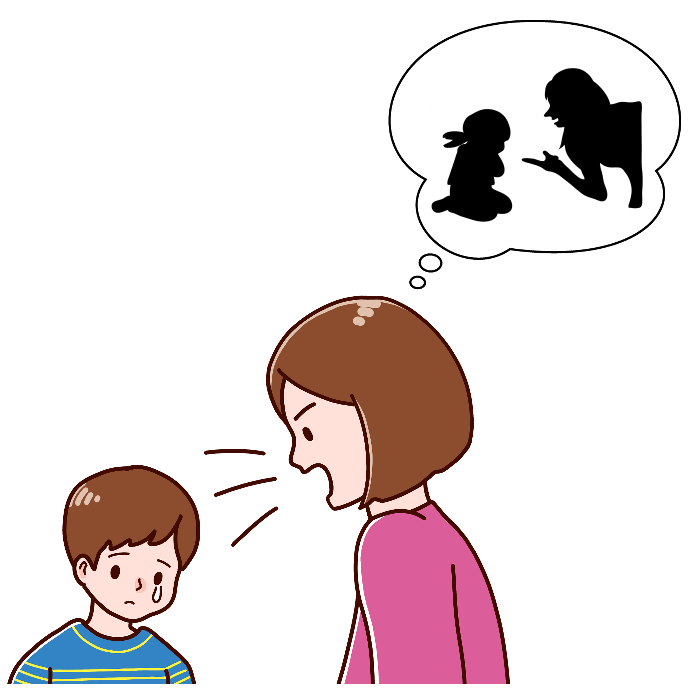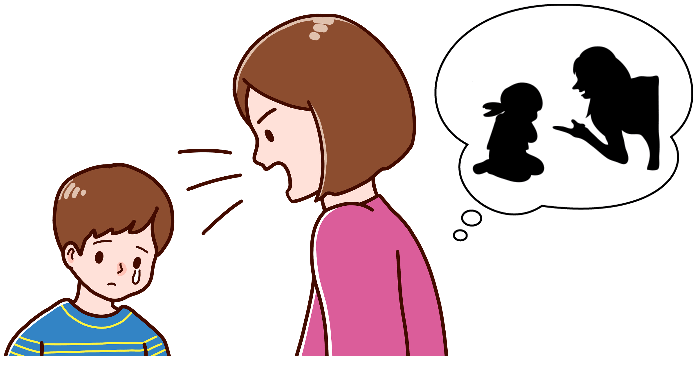
POINTインナーチャイルドが子育てに与える影響は、①傷ついた感情を子どもに投影する、②イライラしやすい、落ち込みやすい、③親の理想を子どもに押し付ける、④過干渉、⑤過保護、⑥子どもを束縛・コントロールする、⑦子育てのやり方がわからない、⑧負の世代間連鎖を繰り返す、などがあげられます。
心理カウンセラーの寺井です。
心理学では「幼少期の体験は『人格形成』に多大な影響を与える」と考えられており、とくに「子育てのやり方(親子関係の築き方)」は、「自分が子どもの頃に親にしてもらった(親にされた)子育て方法を、大人になって自分の子どもに同じように繰り返す場合が多い」と考えられています。
このように、「インナーチャイルド(幼少期の体験)」は「子育て」に大きな影響を与えており、とくに「インナーチャイルドが深く傷ついている親ほど、子育てに問題が生じやすい」と考えられています。
ちなみに、この記事は「インナーチャイルドが『子育てに与える影響』」についての解説です。
なお、「インナーチャイルドが引き起こす『性格面の症状』」及び「インナーチャイルドが『恋愛・結婚に与える影響』」については、以下の記事で詳しく解説しています。
それでは、インナーチャイルドが子育てに与える影響について解説していきます。
インナーチャイルドが子育てに与える影響
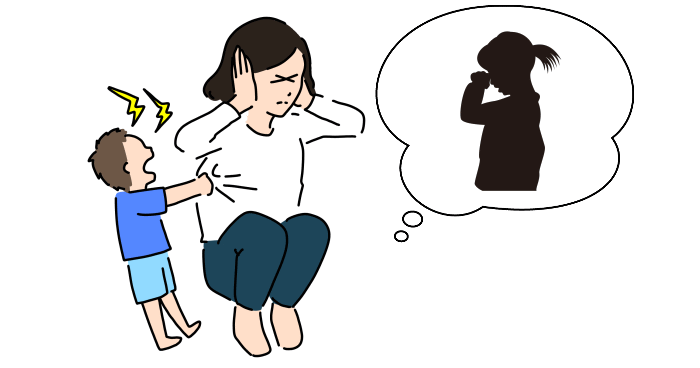
「子育てのやり方(親子関係の築き方)」には人それぞれ特徴があり、心理学では「自分が子どもの頃に親にしてもらった(親にされた)子育て方法を、大人になって自分の子どもに同じように繰り返す場合が多い」と考えられています。
反対に言えば、インナーチャイルドが傷ついている親は「自分が親にされて嫌だった子育てのやり方を自分の子どもに繰り返してしまう可能性がある」と言え、「インナーチャイルドが深く傷ついている親ほど、子育てに問題が生じやすい」と言えます。
なお、「インナーチャイルドが子育てに与える影響」は、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 傷ついた感情を子どもに投影する
- イライラしやすい、落ち込みやすい
- 親の理想を子どもに押し付ける
- 過干渉
- 過保護
- 子どもを束縛・コントロールする
- 子育てのやり方がわからない
- 負の世代間連鎖を繰り返す
それでは、以下に詳しく解説していきます。
①傷ついた感情を子どもに投影する
インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃に「親や家族」に傷つけられた経験を持つ場合が多く、その影響で、子育てにおいて「子どもの頃に親や家族に傷つけられた感情を無意識に子どもに重ねてしまう」ことが多いです。
なお、「自分の感情を相手に重ねてしまう」ことを、心理学では「投影」と言います。
投影とは、ジークムント・フロイトが提唱した防衛機制の1つで、「受け入れられない自分の感情や不快なもの、あるいは自分の悪い部分などを相手に映し出して、相手が持っていると思い込むこと」をいいます。そのため、本当は自分自身のことであったり、自分が思っていることであったりするのだけれども、そうしたものが自分の中にあることが受け入れられないがために、相手が持っていると思い込むことで安心しようとしているのです。
引用元:投影と投影同一視
また、「インナーチャイルドが傷ついている親が子どもに対して行う投影」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子どもの頃に叱られることが多かった親は、子どもの些細な失敗を許すことができず、子どもを過度に叱ってしまう
- 子どもの頃に辛い思いをすることが多かった親は、子どもの些細な変化が異常に気になってしまい、子どもを過度に心配してしまう
このように、インナーチャイルドが傷ついている親が子どもに対して行う投影とは、「子どもの頃に親にされたことを、自分の子どもに同じように体験させている」と言えます。
そして、子どもの頃に親に傷つけられた感情や体験を自分の子どもに投影して再現することによって、親は「自らのインナーチャイルド(傷ついたままの感情)の存在に気づく」場合があります。
「投影」とは、自分の気づいていない、未消化な感情に気付き、改めて手放すために起こるものと言われています。…(中略)…目の前の相手が見せてくれる自分の隠された思いを知ることが、「投影」の大きな役割の一つでもあるのです。
このように、インナーチャイルドが傷ついている親が子どもに対して行う投影とは、「親が自らのインナーチャイルドの存在に気づいていない」あるいは「親が自らのインナーチャイルドの存在から目を背けている」ことによって起きる症状と言え、「インナーチャイルドの存在に気づかせるためにインナーチャイルド自身が引き起こしている症状」と言い換えることができます。
反対に言えば、「親が自らのインナーチャイルドの存在に気づき、認め、癒すことで、子どもへの投影を終わらせることができる」と言えます。
以上のことから、「傷ついた感情を子どもに投影する」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
②イライラしやすい、落ち込みやすい
前述の通り、インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃に「親や家族」に傷つけられた経験を持つ場合が多いのですが、大人になっても「心が傷ついたままであること(インナーチャイルドの存在)に気づいていない」あるいは「心が傷ついたままであること(インナーチャイルドの存在)から目を背けている」ことが多いです。
このとき、親や家族の言動によって傷ついた感情を「トラウマ(心的外傷)」と言います。
子供の頃に、親からひどい仕打ちを受けたり、学校でいじめを受けると、心に傷跡が残ります。これをトラウマと呼びます
また、インナーチャイルドが傷ついている親は、幼少期に負った「トラウマ(心の傷)」を大人になっても抱え続けている場合が多く、その影響で、子育てにおいて「子どもの頃のトラウマ体験がフラッシュバックしやすい」という特徴があります。
なお、子どもの頃のトラウマ体験がフラッシュバックすることで、「感情の過剰反応」や「衝動的な行動」が起きることを「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」と言います。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)とは、トラウマになる圧倒的な出来事(外傷的出来事)を経験した後に始まる、日常生活に支障をきたす強く不快な反応です。
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は「PTSD」の影響で、子育てにおいて「イライラしやすい」あるいは「落ち込みやすい」という特徴があります。
なお、「インナーチャイルドが傷ついている親が感じるイライラ」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 親にしてもらえなかったことを自分の子どもにしてあげなければならないことに対する“イライラ”
- 親にされて嫌だったことを自分の子どもにしてしまうことに対する“イライラ”
- 子どもが自分の思い通りに行動しない、子どもが自分の言うことを聞かないことに対する“イライラ”
また、「インナーチャイルドが傷ついている親が感じる落ち込み」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子育てがうまくいかないと「自分のせいだ」と感じる
- 子育てがうまくいかないと「自分は役立たずだ」と感じる
- 子育てがうまくいかないと「自分の育て方が間違っている」と感じる
- 子育てがうまくいかないと「自分は親の資格がない」と感じる
このように、子育てにおける「イライラしやすい」あるいは「落ち込みやすい」という症状は、「幼少期に負ったトラウマ(インナーチャイルド)によって引き起こされる症状」である場合が多いです。
反対に言えば、前述の「投影」と同じく、「親が自らのインナーチャイルドの存在に気づき、認め、癒すことで、子育てにおけるイライラ・落ち込みを落ち着かせることができる」と言えます。
以上のことから、「イライラしやすい、落ち込みやすい」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
③親の理想を子どもに押し付ける
インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃から「親や家族の期待に応える、親や家族の世話をする、親や家族を支える」など、「ある条件を満たしたときには親から愛情をもらえるが、条件を満たしていないときには親から愛情をもらえない」という「条件付きの愛情」のなかで育った場合が多く、その影響で、子育てにおいて「自らの子どもに対して条件付きの愛情を繰り返してしまう」ことが多いです。
条件付きの愛とはすなわち「◯◯する子は愛してあげる」「◯◯できない子は愛してあげない」というコントロールです。
反対に言えば、インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃に「ありのままの自分では十分に愛情をもらえなかった(無条件の愛情が不足していた)」ことになり、そのぶん「親から愛情をもらうためには○○しなければならない!」あるいは「親から愛情をもらうためには○○してはならない!」という「価値観」を強めながら、大人へと成長してきたことになります。
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃、知らず知らずのうちに「親の理想を押し付けられてしまっている場合が多い」と考えられています。
とはいえ、インナーチャイルドが傷ついている親の中には、「親の理想を実現できた人」もいれば「親の理想を実現できなかった人」もいます。
なお、「親の理想を実現できた場合の子育ての特徴」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 野球やサッカーなど、スポーツの世界で自分が実現した「理想」や「夢」を子どもにも実現させようとする
- 音楽や美術など、芸術の世界で自分が実現した「理想」や「夢」を子どもにも実現させようとする
- 医師や弁護士など、自分が就いている「職業」に子どもを就かせようとする
また、「親の理想を実現できなかった場合の子育ての特徴」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 野球やサッカーなど、スポーツの世界で自分が実現できなかった「理想」や「夢」を子どもに実現させようとする
- 音楽や美術など、芸術の世界で自分が実現できなかった「理想」や「夢」を子どもに実現させようとする
- 医師や弁護士など、自分が就けなかった「職業」に子どもに就かせようとする
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は、「親の理想を実現できた子どもは認めるが、親の理想を実現できない子どもは認めない」という「価値観」が強いため、子育てにおいて「親の理想を子どもに押し付けてしまい、子どもをありのまま信用できない」ことが多いです。
以上のことから、「親の理想を子どもに押し付ける」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
④過干渉
インナーチャイルドが傷ついている親は、「病気の家族を看病する、炊事・洗濯など家事をこなす、幼い弟妹の面倒を看る、介護が必要な祖父母の世話をする」など、子どもの頃から家族の世話をしてきた場合が多く、その影響で、大人になって「世話焼きになる」ことが多いです。
ですので、インナーチャイルドが傷ついている親は、大人になって「誰かの世話をできている(誰かに必要とされる)ときには自分の存在価値を感じて精神的に安定するが、誰の世話もできていない(誰にも必要とされていない)ときには自分の存在価値を感じられず、精神的に不安定になる」ことが多く、その影響で、子育てにおいて「必要以上に子どもの意思や行動に口出しをしたり、子どもの気持ちを無視して先回りして行動してしまう」ことが多いです。
なお、「子育てにおいて親が子どもに干渉しすぎてしまう行動」を「過干渉」と言います。
過干渉とは、親が子どもを自分の意思に過度に従わせようとすることで、結果として子どもの意思や判断を極端に制限してしまう関わり方のことです。
また、「過干渉な親の特徴」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子どもの話を遮って話し始める
- 進路など、子どもの意見を尊重しない
- 友人など、子どもの人間関係に干渉する
- 趣味やファッションなど、子どもの好きなものを否定する
- 子どものできている点を褒めずに、できてない点ばかりを指摘する
- 子どもに対して完璧を求めすぎる
- 子どもに対して「あなたのためを思って…」とよく言う
- 子どもに対して「だって、心配だから…」とよく言う
- 子どもに対して「どうして言うことが聞けないの?」とよく言う
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は、「子どもの世話をすることで精神的な安定を得ようとする」という心理的特徴があるため、子どもを世話しようとするあまり、子育てにおいて「過干渉になりやすく、子どもの自立を妨げてしまう」ことが多いです。
以上のことから、「過干渉になる」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
⑤過保護
インナーチャイルドが傷ついている親は、「炊事・洗濯など家事をこなす、幼い弟妹の面倒を見る、母親の愚痴を聞く、父親と母親の夫婦仲を仲介をする」など、子どもの頃から「自分が楽しむ」ことより「家族を支える」ことを優先してきた場合が多く、その影響で、大人になって「自分を犠牲して誰かを支える(自己犠牲をする)」ことが多いです。
自己犠牲とは、他人のために自分の何かを犠牲にして尽くすこと。たとえば、他人の仕事まで引き受けたり、休みも自分ではなく周囲を優先してしまったり、などの行動をとることです。
ですので、インナーチャイルドが傷ついている親は、子育てにおいて「自分を犠牲にして子どもを支える」場合が多く、その影響で、子育てにおいて「必要以上に子どもを保護したり、子どもを甘やかしてしまう」ことが多いです。
なお、「子育てにおいて親が子どもを保護しすぎてしまう行動」を「過保護」と言います。
過保護とは、必要以上に子供を甘やかしたり、子供の要望を叶えてしまったりすることをいいます。
また、「過保護な親の特徴」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子どもの問題を子どもに代わって解決してしまう
- 子どもと常に関わっていないと気が済まない
- 外出するときは常に一緒に行動する(どこへでも送迎する)
- 子どもの身の回りの世話を全てしてしまう
- 子どもが欲しがるものは全て与えてしまう
- 子どもが困らないように先回りしてお膳立てをする
- 子どもを叱れない、子どもを注意できない
- 子どもに対して「かわいそう…かわいそう…」と思うことが多い
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は、「子どもを支えることで精神的な安定を得ようとする」という心理的特徴があるため、子どもを支えようとするあまり、子育てにおいて「過保護になりやすく、子どもの自立を妨げてしまう」ことが多いです。
以上のことから、「過保護になる」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
⑥子どもを束縛・コントロールする
前述の通り、インナーチャイルドが傷ついている親は、「子どもを世話したり支えることに強い生きがいを感じる反面、子どもを世話したり支えることができないことに強い不安を感じる」という心理的な特徴があります。
反対に言えば、インナーチャイルドが傷ついている親は、「子どもが自分から離れていってしまうこと、自分が子どもに必要とされなくなることを極端に恐れている」と言い換えることができ、「子どもに精神的依存をしている親」と言い換えることができます。
ですので、インナーチャイルドが傷ついている親は「子どもに必要とされたい」と思うあまり、子どもを懸命に世話したり支えたりしますが、親が子どもを懸命に世話したり支えたりすればするほど、子どもは自立できなくなってしまい、結果として「親と子どもが互いに強く依存し合う」ことになります。
なお、「親と子が過度に依存し合っている親子」を「共依存親子」と言います。
共依存親子とは、親と子どもが互いに強く依存し合い、自分自身を見失ってしまう関係です。親は子どもの存在によって自分の価値を見出し、子どもは親を喜ばせることでしか自分の存在意義を感じられなくなります。親が子どもに親がいないと何もできないと思わせたり、子どもがいないと親が困ると思わせたりして、子どもを支配します。
また、「共依存親子の特徴」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 親が子どもの友人関係・恋愛関係・進路・就職に干渉する
- 親が子どもに「誰のおかげで生活できていると思っているのだ!勝手は許さない!」など精神的圧力をかける
- 親が子どもに「あなたは1人では生きていけない…あなたは1人では何もできない…」など精神的圧力をかける
- 急に理不尽に怒ったり、急に不機嫌になったり、親が子どもにストレスを与えることで子どもの成長を阻害して束縛する
- 子どもの成長を否定したり、子どもの成長を無視したり、親が子どもの反抗期を受け入れないことで子どもの成長を阻害し束縛する
- 「○○しなさい!○○はダメ!頑張りなさい!我慢しなさい!」など、親が「過干渉」を繰り返すことで子どもの自由を奪い、子どもの成長を阻害し束縛する
- 「かわいそう…かわいそう…大変なことはしなくていい…」など、親が「過保護」を繰り返すことで子どもの自由を奪い、子どもの成長を阻害し束縛する
このように、インナーチャイルドが傷ついている親は「子どもに精神的な依存をする」という心理的特徴があるため、子どもが自分から離れていかないよう、子育てにおいて「子どもを束縛・コントロールする」ことが多いです。
以上のことから、「子どもを束縛・コントロールする」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
⑦子育てのやり方がわからない
インナーチャイルドが傷ついている親は、子どもの頃、自らも「親(祖父・祖母」から十分な愛情を注いでもらった経験が少ない場合が多く、その影響で「子育てに自信がない、子育てのやり方がわからない」など「子育てへの不安を感じやすくなる」ことが多いです。
なお、子どもの頃の「両親との関係性(愛着関係)」に何らかの問題があったことが原因で、大人になって子育てに問題が生じることを「愛着障害」と言います。
愛着障害とは、養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に問題が生じる状態です。主に虐待や養育者との離別が原因で、母親を代表とする養育者と子供との間に愛着がうまく芽生えないことによって起こります。
引用元:愛着障害(アタッチメント障害)
また、「インナーチャイルドが引き起こす愛着障害」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子どもの頃に親に傷つけられた感情がフラッシュバックして、子どもに対して感情的になる
- 子どもの頃に親に信頼してもらえなかった影響で、子どもに対して強い不信感を抱く
- 子どもの頃に親の愛情が不足していた影響で、子どもに対して強く依存・執着する
- 子どもの頃に親に可愛がってもらえなかった影響で、子どもを可愛いと思えない
- 子どもの頃に親に助けてもらえなかった影響で、育児に悩んでも周囲に助けを求められない(孤育て、ワンオペ)
- 傷つくことへの恐れから、子どもに対して素直な愛情表現ができない
- 自分に自信が持てないため、子どもと関わることを避けてしまう
このように、「愛着障害」とは「子どもに対して愛情がない状態」ではなく、「子どもに対して愛情はあるが、適切な愛情の表現方法(適切な子どもとの関り方)がわからない状態」を指します。
ですので、インナーチャイルドが傷ついている親は、子育てにおいて「子どもとの関り方がわからずに苦しみ続ける」ことが多く、場合によっては、苦しさのあまり子育てから逃げてしまう場合があります。
なお、親が子育てから逃げてしまうことを「ネグレクト(育児放棄・育児怠慢)」と言います。
ネグレクトは、英語では”neglect”となり、無視する、怠る、疎かにすると訳されます。子どもに対するネグレクトは、育児放棄や育児怠慢と言われ、児童虐待の1つです。
このように、「愛着障害(子育ての問題)」とは「『子どもへの愛情がない』ことによって起こる問題」ではなく、「『子どもへの愛情はあるが、愛情の届け方がわからない』ことによって起きる問題」と言えます。
とはいえ、「愛着障害」とは、あくまで「インナーチャイルド(生まれた後の幼少期の体験の影響)によって引き起こされる症状」であるため、「親が自らのインナーチャイルドの存在に気づき、認め、癒すことで、愛着障害を克服することができる」と言えます。
以上のことから、「子育てのやり方がわからない」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
⑧負の世代間連鎖を繰り返す
このように、子どもの頃に「問題のある子育てをする親(愛着障害の親)」に育てられた場合、自分も親になって「自分の子どもに問題のある子育てを繰り返してしまう(愛着障害を連鎖させてしまう)」場合が多く、「子どもの頃に親にされて嫌だった子育てのやり方(親の子育てから受けた負の影響)を、大人になって自分の子どもへと繰り返してしまうこと」を「負の世代間連鎖」と言います。
負の世代間連鎖とは、「親(又は親から上の世代)から引き継いだ負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」を指します。世の中の親子問題を抱えている人の多くが、「親を介してこの負の人生プログラム及び認知の歪みの連鎖」に巻き込まれたことによって、様々な問題を抱えてしまうようになったことを知ることはとても大切なことです。
引用元:親子の問題①(世代間連鎖)
なお、「インナーチャイルドが引き起こす負の世代間連鎖」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 子どもの頃、親から「暴言・暴力(モラハラ・DV)」を受けて育った親が、自分の子どもに「暴言・暴力(モラハラ・DV)」を振るう
- 子どもの頃、親から「過干渉・過保護」を受けて育った親が、自分の子どもに「過干渉・過保護」になる
- 子どもの頃、親から「育児放棄・育児怠慢(ネグレクト)」を受けて育った親が、自分の子どもに「育児放棄・育児怠慢(ネグレクト)」をする
- 子どもの頃、親に「精神的依存」をされて育った親が、自分の子どもに「精神的依存」をする
このように、「負の世代間連鎖(子育ての問題)」とは「親が意図的に起こしている問題」ではなく、「祖父母から親へ、親から子どもへと無意識に連鎖している問題」と言えます。
とはいえ、「負の世代間連鎖」とは、あくまで「インナーチャイルド(生まれた後の幼少期の体験の影響)によって引き起こされる症状」であるため、「親が自らのインナーチャイルドの存在に気づき、認め、癒すことで、負の世代間連鎖を断ち切ることができる」と言えます。
以上のことから、「負の世代間連鎖を繰り返す」という点は、「子育てにおいてインナーチャイルドが引き起こす症状」のひとつと言えます。
インナーチャイルドの癒し方
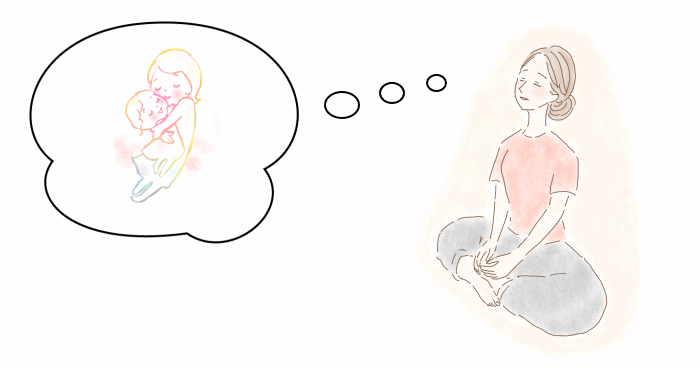
インナーチャイルドを癒すことは、心理学では「『生きづらさ』を根本から改善するプロセス」と考えられています。
インナーチャイルドを癒すというのは、単に「昔の記憶を振り返る」作業ではありません。
いまのあなたの感じ方・考え方・人との関わり方に、どんな幼少期の影響が残っているのかを、心理学の視点でゆっくり整理しながら、その作用をやわらげていくためのプロセスです。
また、「インナーチャイルドの癒し」は、以下のように「2つ」にわけて考える必要があります。
POINT
- 自宅での「セルフケア」
- 専門家による「インナーチャイルド・セラピー(退行催眠療法)」
インナーチャイルドの癒しは、特別な場所や特別な道具が必要なものではありません。
あなたが自分の心にそっと寄り添うことができれば、日常の中で、無理なく続けていけるセルフケアです。とはいえ、幼少期の体験はとても影響力が強く、その分、心の反応も大きく揺れ動きます。
インナーチャイルドの癒しを一人で進めることに難しさを感じるのは、とても自然なことです。
専門家と一緒に取り組むことで、より安全に、安心しながら癒しを深めていくことができます。
次のような場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
POINT
- 怒り・悲しみ・不安・嫌悪・孤独など、強い感情に圧倒されてしまうとき
- 自分の内面に向き合うことに強い恐れや抵抗を感じるとき
- 「自分を癒すこと」そのものに罪悪感があり、前へ進みづらいとき
- セルフケアに自信が持てず、何をどう進めれば良いかわからないとき
専門家は、感情が揺れたときのケアや、心の安全を守りながら進める方法を熟知しています。
POINT
- セルフケアは「日常の癒し」、専門家と行うケアは「深いレベルの癒し」
と分けて考えて、専門的なケアと、自宅でのセルフケアを併用する方法が最も安全で効果的です。
続きは、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事・関連情報
さいごに、本記事に関する関連記事を以下に紹介します。
是非、あわせてお読みください。
関連記事
- 心理学における「インナーチャイルド」の意味と重要性を理解しよう!
- 「長男・長女の役割」がインナーチャイルドに与える影響
- 長男・長女のインナーチャイルドが引き起こす症状
- 母親に優しくできないのは「インナーチャイルド」が原因?心理学から読み解く癒しのステップ
- 恋愛依存症とインナーチャイルドの深い関係
- アダルトチルドレン(ac)診断チェックリスト:『インナーチャイルドの傷つき度合』をセルフチェック!
- アダルトチルドレン(ac)タイプ診断チェックリスト:『インナーチャイルドのタイプ』をセルフチェック!
- インナーチャイルドを引き起こす「心理的原因」の解説
- インナーチャイルドの原因となる「父親」の特徴
- インナーチャイルドの原因となる「母親」の特徴
なお、本記事に関する関連情報は、以下のページでもまとめていますのであわせて紹介します。
関連情報まとめページ
以上、「インナーチャイルドが子育てに与える影響」という記事でした。