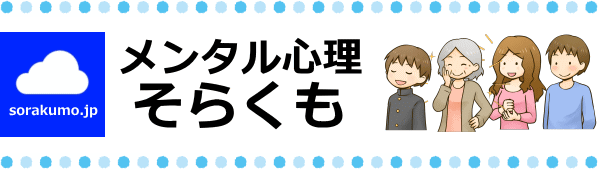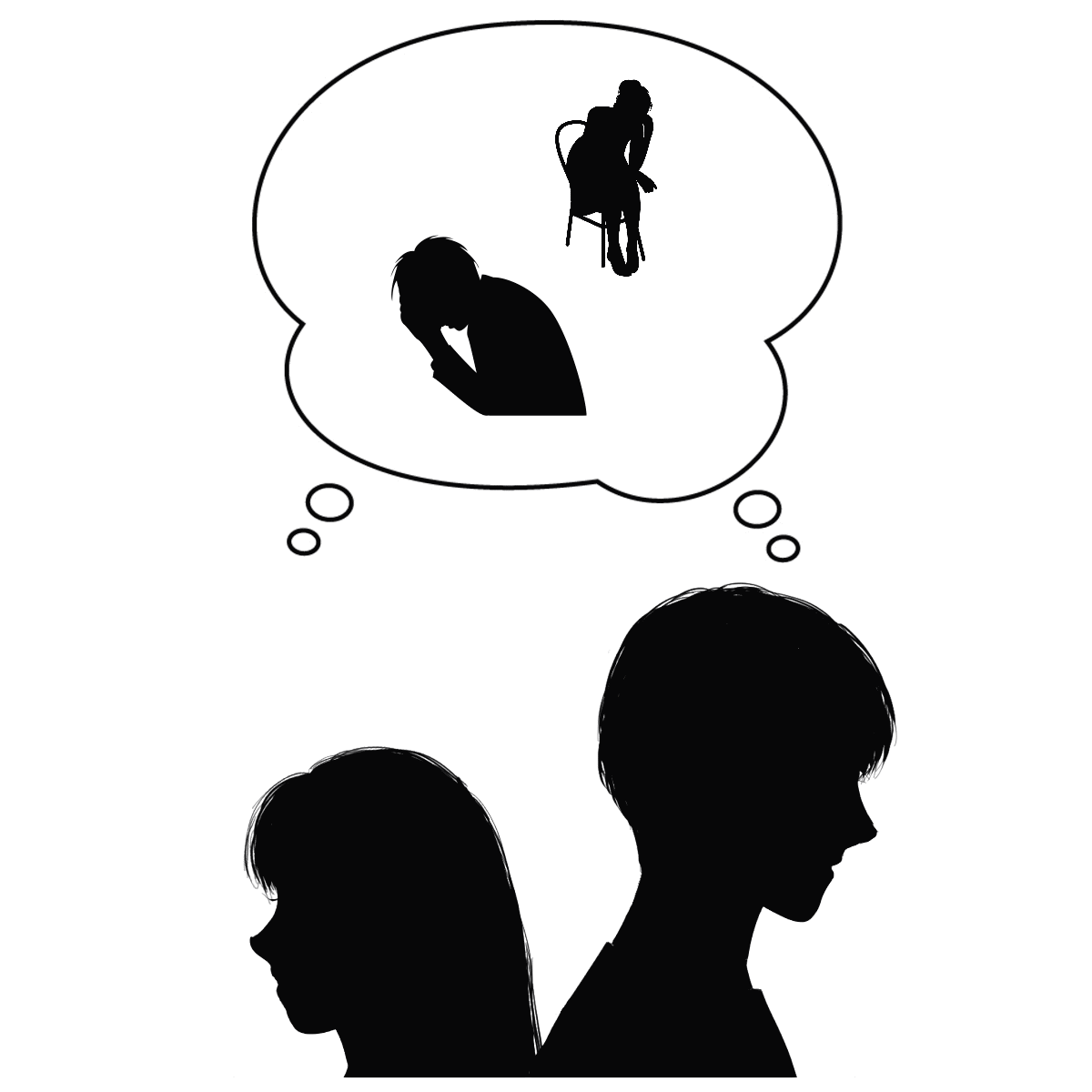
POINTロストワン(いない子)の克服には、「幼少期のトラウマ」を癒すことに加え、「自分の存在感を消して周囲に負担や迷惑を掛けないことで自分の存在価値を感じよう」という「思考パターン」を書き換えることが必要です。
心理カウンセラーの寺井です。
ロストワン(ロストチャイルド・ロンリー)タイプ(以下「ロストワン」と言う。)を始めとする「アダルトチルドレンの克服方法」は、「アダルトチルドレン(AC概念)」の生みの親である「クラウディア・ブラック」によってしっかりと確立されています。
ですので、本記事で解説している「アダルトチルドレン:ロストワンの克服方法」は、「クラウディア・ブラック」が示した「アダルトチルドレン、回復の4ステップ」を遵守した形で考えられています。
なお、ロストワンの原因には「感情面の原因(幼少期のトラウマ)」と「思考面の原因(無意識の思考パターン)」の「2つの原因」があるため、ロストワンの克服は「感情面のケア(幼少期のトラウマを癒す)」と「思考面のケア(思考パターンを書き換える)」の「2つの取り組み」が必要になります。
そして、「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」は、「幼少期のトラウマの癒し」と「人生脚本の書き換え」を「2つ同時」に取り組めるため、ロストワンの克服に非常に有効です。
この記事は、インナーチャイルドセラピー(退行催眠)による「アダルトチルドレン:ロストワン(いない子)」の克服方法について解説しています。
アダルトチルドレン:ロストワン(いない子)克服のポイント
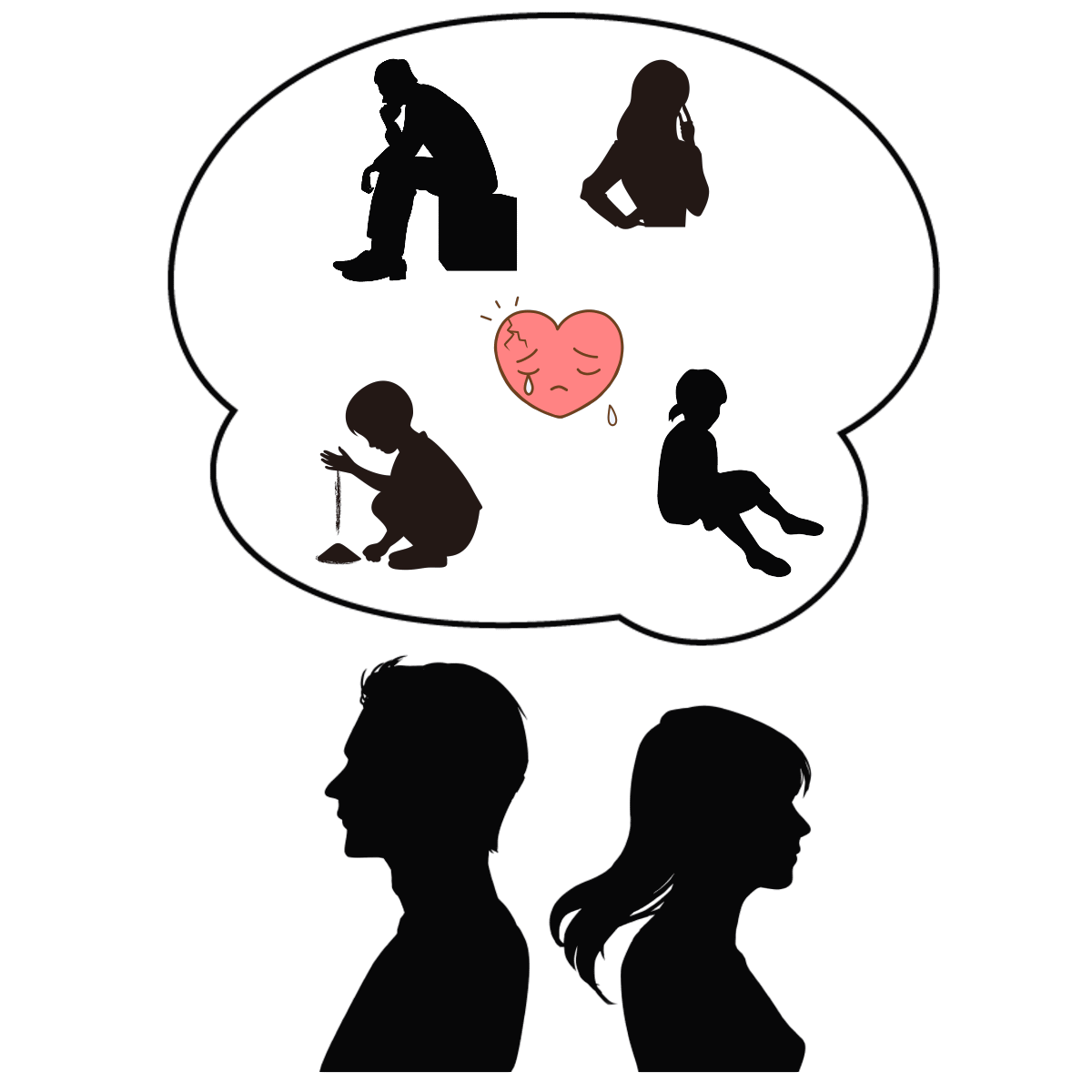
ロストワンは、「機能不全家族」で育った影響で「トラウマ(心の傷)」を負い、「トラウマ」の「防御行動」として「いない子」を演じるようになり、家族のなかで「いない子」を演じ続けているうちに「無意識の思考パターン(習慣)」として「潜在意識」に根付いていったと考えられています。
以上のことから、「ロストワンの原因」は、大きく分けて以下の「2つ」があります。
POINT
- 感情面の原因…「幼少期のトラウマ」
- 思考面の原因…「無意識の思考パターン」
よって、「ロストワンの克服」は、以下の「2つの取り組み」が必要となります。
POINT
- 感情面のケア…「幼少期のトラウマ」を癒す
- 思考面のケア…「無意識の思考パターン」を書き換える
このように、ロストワンを始めとする「アダルトチルドレンの克服」は、「感情面」と「思考面」の「両方の取り組み」が必要です。
反対に言えば、どちらか「片方の取り組み」だけでは、一時的には症状が落ち着いたとしても、しばらくして「いない子」の症状が再現する可能性が高いと言えます。
アダルトチルドレンの克服がうまく行かない理由
また、「ゲシュタルト心理学」や「交流分析」によると、「幼少期のトラウマを癒す作業」や「無意識の思考パターンを書き換える作業」は、子どもの頃の感情に「感情移入」できればできるほど効果が高いと考えられています。
とはいえ、「子どもの頃のトラウマ体験」や「子どもの頃の家族との記憶」は、「できれば思い出したくない『傷ついた記憶』」であるのと同時に、「なかなか思い出しづらい『遠い昔の記憶』」でもあります。
ですので、心理カウンセラーが視界に入ってしまうと集中しきれず、「アダルトチルドレンの克服」はうまく行かなくなってしまう場合が多いです。
よって、目を開けた状態で行う「対話型のカウンセリング」のみでは、「アダルトチルドレンの克服」がうまく行かない場合があると言えます。
インナーチャイルドセラピー(退行催眠)が有効な理由
このように、目を開けた状態で行う「対話型のカウンセリング」のみだと、心理カウンセラーが視界に入ってしまい、子どもの頃の感情に「感情移入」できず、「アダルトチルドレンの克服」がうまく行かない場合が多いです。
ですが、目を閉じた状態で行う「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」であれば、心理カウンセラーが視界に入らず、子どもの頃の感情に「感情移入」しやすくなり、「アダルトチルドレンの克服」が進めやすくなります。
よって、「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」は「アダルトチルドレンの克服」に非常に有効であると言えます。
以上のことから、「ロストワンの克服」は、以下の手順で行っていきます。
POINT
- ロストワン(いない子)の原因を理解する
- インナーチャイルドセラピーを用いて「幼少期のトラウマ」を癒す
- インナーチャイルドセラピーを用いて「無意識の思考パターン」を書き換える
それでは、以下に詳しく解説していきます。
①ロストワン(いない子)の原因を理解する
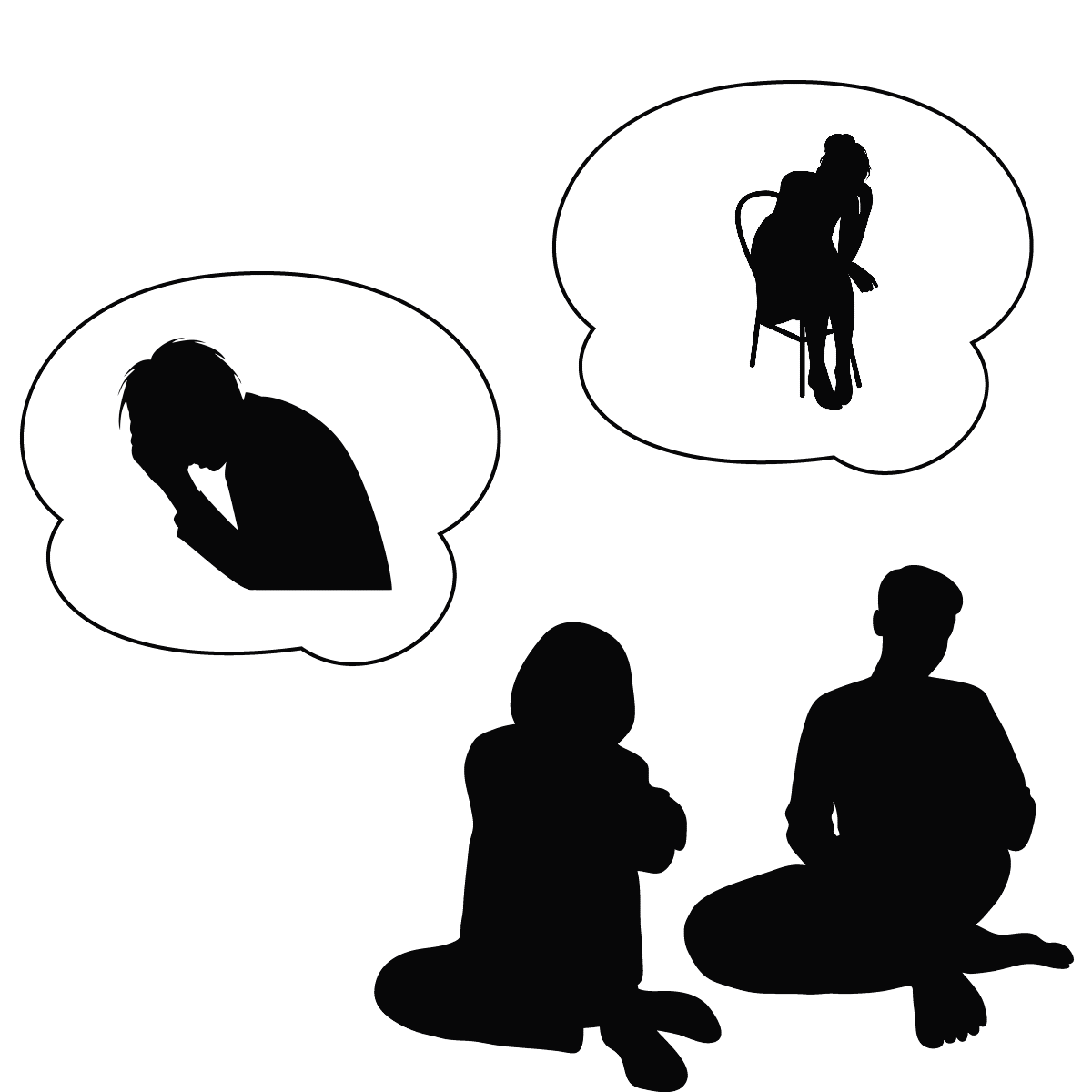
「人の心」は、以下のように「感情面」と「思考面」に分けて考えることができます。
POINT
- 「感情、本能、無意識、潜在意識、本音」
- 「思考、理性、意識、顕在意識、建前」
よって、「ロストワンの原因」は、以下のように「感情面」と「思考面」の「2つの原因」があると考えられます。
POINT
- 感情面の原因…「幼少期のトラウマ(見捨てられ不安)」
- 思考面の原因…「無意識の思考パターン(人生脚本)」
それでは、「ロストワンの原因」について、以下に詳しく解説していきます
①感情面の原因:幼少期のトラウマ(見捨てられ不安)
ロストワンが「いない子」を演じ始めた理由は、「機能不全家族」で育ったことにより、子どもの頃に「トラウマ(心の傷)」を負ったことが原因です。
なお、家庭において以下の「根本的な願い」が満たされなかったとき、子どもは「トラウマ」を負うと考えられています。
POINT
- だれかの期待にこたえるためではなく、ありのままの自分として大切にされる
- 親の欠損を埋め合わせるための存在ではなく、その子自身として慈しまれる
- 安全で、安定していて、温かさのある環境で、無条件に愛される
ロストワンをはじめ、アダルトチルドレンの原因となる「機能不全家族」とは、上記の「根本的な願い」が満たされない家庭であり、子どもが「トラウマ」を負いやすい家庭と言えます。
なお、「ロストワンが生まれ育った機能不全家族の特徴」は、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 親が子どもに対して関心が薄い(ネグレクト・育児放棄)
- 親が子どもに対して干渉しすぎる(過干渉・過保護)
- 親の愛情が「兄弟姉妹」で平等ではない(きょうだい差別)
また、子どもが負う「トラウマ」のひとつに「見捨てられ不安」があり、人は「見捨てられ不安」を感じると「強い精神的ストレス」に襲われるため居てもたってもいられなくなり、「見捨てられ不安」を和らげるために、衝動的にさまざまな「防御行動」をとるという特徴があります。
【見捨てられ不安とは?】見捨てられること、自分から人が離れてしまうことに強い不安を感じます。見捨てられたくない相手は、恋愛相手、友人、親、職場の人間などで、人から嫌われたくないため、様々な防衛行動を起こします。
なお、「ロストワンが負ったトラウマ(見捨てられ不安)」とは、主に以下の「具体例」が考えられます。
POINT
- 親が自分に対して無関心な様子に、強い不安を感じた
- 親が自分の感情を「否定・無視・干渉・詮索」してくる様子に、強い不安を感じた
- 親が自分を無視して「自分以外の兄弟姉妹」ばかりに愛情を注ぐ様子に、強い不安を感じた
また、「ロストワンが見捨てられ不安を和らげるためとり始めた『防御行動』」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 自分に対して無関心な親の気を無理に引こうとはせず、無関心な親に合わた形で親の負担を減らそう(親に迷惑を掛けないようにしよう)と、自我(自分の気持ち・意見)を抑え込むなど「おとなしい子」を演じるようになった
- 自分の感情を「否定・無視・干渉・詮索」してくる親に無理に抗おうとはせず、親に傷つけられない形で親の負担を減らそう(親に迷惑を掛けないようにしよう)と、一人で過ごすことで「手の掛からない子」を演じるようになった
このように、ロストワンは「耐え難い苦しさ」である「見捨てられ不安」を少しでも和らげるための「防御行動」として、「自我(自分の気持ち・意見)を抑え込む」ようになったり「一人で過ごす」ようになるなど、家族のなかで「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)を演じる」ようになったと考えられています。
以上のことから、「幼少期のトラウマ(見捨てられ不安)を癒す」ことで「いない子」という「防御行動」を終わらせることができ、ロストワンを克服できると言えます。
思考面の原因:「無意識の思考パターン(人生脚本)」
ロストワンが「いない子」を演じ続ける理由は、「いない子」を演じて「両親の負担」を減らしてあげたにもかかわらず、両親から「感謝」や「褒め」の言葉を十分に掛けてもらえなかったことにより、「いない子」を演じ続けることで「両親に自分の存在価値を認めてもらおう(自分の存在価値を感じよう)」という「人生脚本」を身に付けたことが原因です。
ロストワンは「耐え難い苦しさ」である「見捨てられ不安」を少しでも和らげるための「防御行動」として、自ら進んで「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」を演じるようになります。
ですが、ロストワンは「両親」から「負担を減らしてほしい!」とお願いをされてから「いない子」を演じ始めるのではなく、「両親」から「負担を減らしてほしい!」とお願いをされる前に先回りして「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」を演じてしまうため、「両親」から「ありがとう…」「助かった…」という「感謝」や「褒め」の言葉を掛けてもらえない場合があります。
そうすると、ロストワンは「いない子」を演じて「両親の負担」を減らしてあげたにもかかわらず、両親から「感謝」や「褒め」の言葉を十分に掛けてもらえなかったことになり、その影響で「回避型愛着スタイルの傾向が強くなる」という特徴があります。
回避型は、自分以外の人と深く関わることがストレスに感じてしまう愛着タイプです。周りの人との関係性において、感情的な親密さを持つことを避ける傾向があります。濃密な人間関係にストレスを感じやすいため、ストレスを感じるくらいなら1人でいたいと考えてしまうでしょう。
なお、親から「感謝」や「褒め」の言葉をもらえなかったことで、子どもが「自分はこうやって生きていこう!」という「生き方の方針」を決めることを「幼児決断」と言います。
幼児決断は、早期に幼児の感情をもとに決めることです。幼児決断をもとに、自分はこう生きようとシナリオを書く。これが、「人生脚本」です。幼児決断は両親(養育者)から、さまざまな禁止令(インジャンクション)を受けながらなされるものです。
引用元:交流分析|禁止令と幼児決断
このように、ロストワンは「いない子」を演じて「両親の負担」を減らしてあげたにもかかわらず、両親から「感謝」や「褒め」の言葉を十分に掛けてもらえなかったことにより、「『自分の存在価値』を『両親』に認めてもらえるまで『いない子』を演じ続けよう!」という「幼児決断」をすると考えられています。
そして、家族のなかで「いない子」を演じ続けているうちに、「無意識の思考パターン(習慣)」として「潜在意識」に根付いていったと考えられます。
なお、子どもの頃に親との関りで身に付けた「無意識の思考パターン」を「人生脚本」と言います。
人生脚本とは、エリック・バーンが提唱した心理学理論です。幼少期に自分自身の人生脚本を描き、その通りになるとされています。人生脚本の大部分は親からのメッセージにより決定されます。無意識のうちに生き方を決め、それに従い行動するということです。
引用元:人生脚本とは
このように、子どもの頃に身に付けた「人生脚本」の影響により、大人になっても、ロストワンは無意識に「いない子」を演じ続けていると考えられます。
以上のことから、「人生脚本」を書き換えることで「いない子」という「無意識の思考パターン」を終わらせることができ、ロストワンを克服できると言えます。
なお、「アダルトチルドレン(AC)ロストワンの原因」については、以下の記事で詳しく解説していますので、必要な方は参考にして下さい。
②幼少期のトラウマ(インナーチャイルド)を癒す
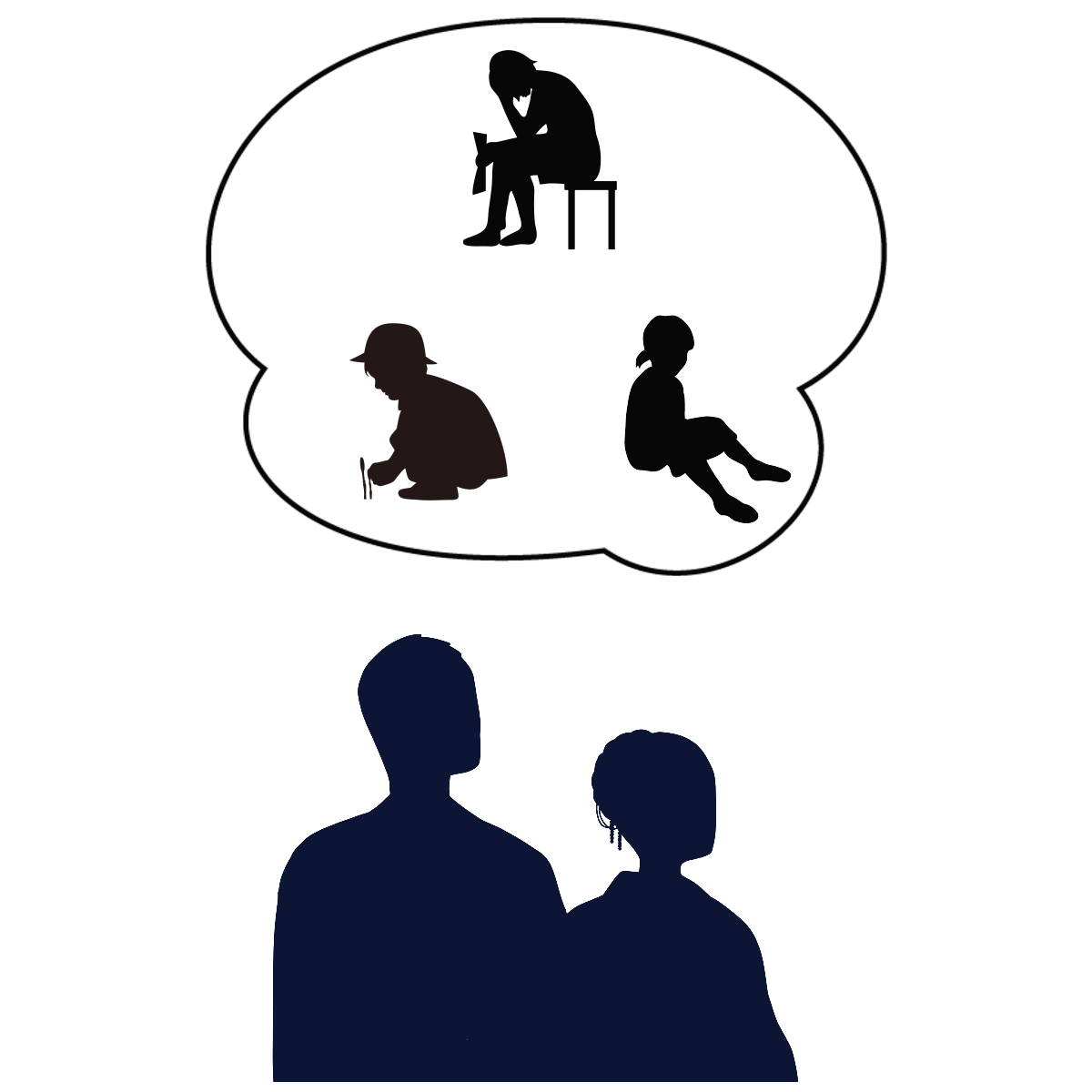
ロストワンが「いない子」を演じ始めた理由は、「幼少期のトラウマ(見捨てられ不安)」の「耐え難い苦しさ」を和らげるための「防御行動」にあります。
このように「幼少期のトラウマ」とは、「ロストワンの感情面の原因」を意味します。
ですので、ロストワンを克服するためには、子どもの頃に負った「トラウマ」を癒して「防御行動」を終わらせる必要があります。
とはいえ、「幼少期のトラウマ」とは、「なかなか思い出しづらい『遠い昔の記憶』」であるのと同時に、「できれば思い出したくない『傷ついた記憶』」でもあります。
ですので、「幼少期のトラウマ」は、頭では思い出そう・話そうとするのだけれども、気持ちで「恥ずかしさ」や「恐れ」を強く感じてしまい、結果、自分の意思に反して無意識に話を反らしてしまったり、無意識に話を誤魔化してしまう場合があります。
このように、「幼少期のトラウマ」のような「辛い記憶」に向き合おうとしたとき、自分の意思に反して無意識に話を反らしてしまったり誤魔化してしまう心の働きを「防衛機制」と言います。
心が傷つくことをさけるための機能である防衛機制は、不安やストレスを軽減するための心理メカニズムであり、私たちの精神的な安定に重要な役割を持っています。…(中略)…ただし、防衛機制が働きすぎると問題を先送りするだけで根本的な解決にならないことがあります。
引用元:苦手な人に対する心理と防衛機制
このように「防衛機制」とは、「今以上、心が傷つくことを避けるための無意識の『防衛心理』」を意味します。
ですので、「防衛機制」自体は決して悪いものではないのですが、「幼少期のトラウマ」が辛い体験であればあるほど「防衛機制」が活発に働いてしまい、結果、自分の意思に反して「幼少期のトラウマ」を癒すことが難しくなってしまうという特徴があります。
以上のことから、「幼少期のトラウマ」を「安全・確実」に癒すために、以下の「手順」で取り組む必要があります。
POINT
- 「幼少期のトラウマ」を「インナーチャイルド」というイメージに置き換える
- 「催眠療法(ヒプノセラピー)」を基本にした「インナーチャイルドセラピー」によって「インナーチャイルド(幼少期トラウマ)」を癒す
それでは、以下に詳しく解説していきます。
インナーチャイルドとは?
「インナーチャイルド」とは「幼少期のトラウマ」によって抱える「負の感情」の「別称」であり、「インナーチャイルド(幼少期トラウマ)」を癒すことで「アダルトチルドレンの克服」が可能となると考えられています。
インナーチャイルドは、幼少期のトラウマによって抱えてしまう負の感情のこと。…(中略)…インナーチャイルドを癒やすことで、共依存と同じようにアダルトチルドレンの症状が緩和する可能性があります。
また、「幼少期のトラウマ」のように、ある時(過去)から未解決のまま、モヤモヤと心に残り続けている感情を、「ゲシュタルト心理学」では「未完の感情」と言い、「幼少期のトラウマを癒す」ことを「未完の完結」と言います。
そして「ゲシュタルト心理学」では、「抑圧した過去を知る」すなわち「過去のトラウマ体験を振り返り、『未完の感情』を再体験することで『未完の完結』が果たされる」と考えられています。
未完の完結:ゲシュタルト療法では、「過去の未完の出来事は、ゲシュタルトとして完成されていないモヤモヤとして残っていて(「抑圧」という精神分析用語は用いられない)それを意識化させ、完結することで症状は無くなる、という。フロイトは、「抑圧した過去を知る」ことで症状がよくなると言った。
わかりやすく言うと、「幼少期のトラウマ」を癒すためには、子ども頃の「家族の様子」や「家庭の状況」を振り返って「幼少期のトラウマ」を思い出し、「幼少期のトラウマ」をあらためて体感し直す必要があると「ゲシュタルト心理学」では考えられています。
ですので、「幼少期のトラウマ」を癒すためには、大人の自分が「子どもの頃の自分の感情」にしっかりと「感情移入」することが重要となります。
例えば、「景色」や「風景」は「言葉」や「文字」で認識するより、「写真」や「映像」という「イメージ」で認識した方が「感情移入」がしやすくなります。
それと同じように、「幼少期のトラウマ」も「言葉」や「文字」で認識するより、「インナーチャイルド」という「イメージ」で認識した方が「感情移入」しやすくなります。
このように、「インナーチャイルド」とは、「幼少期のトラウマを癒す作業(未完の完結)」を「安全・確実」に進めやすくするために、あえて思い描く「トラウマを抱えた『子どもの頃の自分のイメージ』」を指します。
インナーチャイルドセラピーとは?
「インナーチャイルド」とは、「幼少期のトラウマ」に「感情移入」をしやすくするための工夫であり、「幼少期のトラウマを癒す作業(未完の完結)」を「安全・確実」に進めやすくするための工夫です。
ですが、前述の通り、人の心には「防衛機制」という「無意識の防衛心理」が働いているため、「インナーチャイルド(子どもの頃の自分のイメージ)」を思い描こうとしても、無意識に集中が反れてしまったり、無意識に誤魔化してしまう場合があります。
このように、「インナーチャイルド(幼少期のトラウマ)を癒す」ためには「防衛機制」を和らげる必要があります。
そこで、「防衛機制」を和らげながら「インナーチャイルドを癒す(未完の完結を果たす)」ことができる方法が「インナーチャイルドセラピー」です。
インナーチャイルド・セラピーは、まさにこの「未完の完結」作業を応用したものです。…(中略)…未完の感情をそのまま引きずるのではなく、「今ここ」で完結(終わらせ、創り直す)ことが、インナーチャイルド・セラピーです。
引用元:インナーチャイルド・セラピー
「インナーチャイルドセラピー」は、目を閉じた状態で行う「催眠療法(ヒプノセラピー)」を基本に行います。
ヒプノセラピー(催眠療法)とは、ユングやフロイトの提唱した深層心理学を根源とし、催眠状態を利用して潜在意識に働きかけ、心理的な問題(=悩み)や心因的な症状を改善する心理療法です。
引用元:ヒプノセラピー基礎知識
このように、「インナーチャイルドセラピー」は目を閉じた状態で行うため、心理カウンセラーの存在や周囲の状況が視界に入らず、そのぶん「恥ずかしさ」や「恐れ」といった「防衛機制の働き」を最小限に和らげることができ、そのぶん「幼少期のトラウマ」を「安全・確実」に癒しやすくなり、そのぶん「ロストワンの克服」を「安全・確実」に進めやすくなります。
インナーチャイルド(幼少期のトラウマ)を癒す
「インナーチャイルド(幼少期のトラウマ)を癒す作業」についてですが、前述の通り「インナーチャイルド(子どもの頃の自分のイメージ)」を思い描くだけで「感情移入」がなされますので、特に何もしなくても、目を閉じてゆっくりと「インナーチャイルド」を思い描くだけで「幼少期のトラウマの治癒」が進んでいきます。
そして必要であれば、「インナーチャイルド」が抱えている「負の感情」を、目を閉じてゆっくりと「言葉」で表現して解放することで、「インナーチャイルド(トラウマ)の癒し」をさらに進めることができます。
なお、「インナーチャイルドが抱えている負の感情」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 両親に関心を持ってもらえなくて寂しかった、本当は両親には関心をもってほしかった…積極的に関わってほしかった…
- 両親に自分の感情を「否定・無視・干渉・詮索」されて嫌だった、本当は両親には「自分の個性(感情・意見・価値観)」を尊重してほしかった…
- 両親に「兄弟姉妹と愛情の差別」をされて悲しかった、本当は両親には平等に愛情を注いでほしかった…
このように、目を閉じてゆっくりと「インナーチャイルド」をイメージしたり、「インナーチャイルドが抱える負の感情」を、目を閉じてゆっくりと「言葉」にすることで、「幼少期トラウマ(見捨てられ不安)」が癒すことができ、「いない子」という「防御行動」を終わらせることができ、ロストワンの克服が実現します。
とはいえ、「インナーチャイルドが抱えている負の感情」を「言語化」することは、専門知識と専門技術を必要とする難しい作業ですので、心理カウンセラーなど専門家の協力が必要です。
なお、「インナーチャイルドセラピー」については以下の記事で詳しく解説していますので、必要な方は参考にしてください。
③無意識の思考パターン(人生脚本)を書き換える
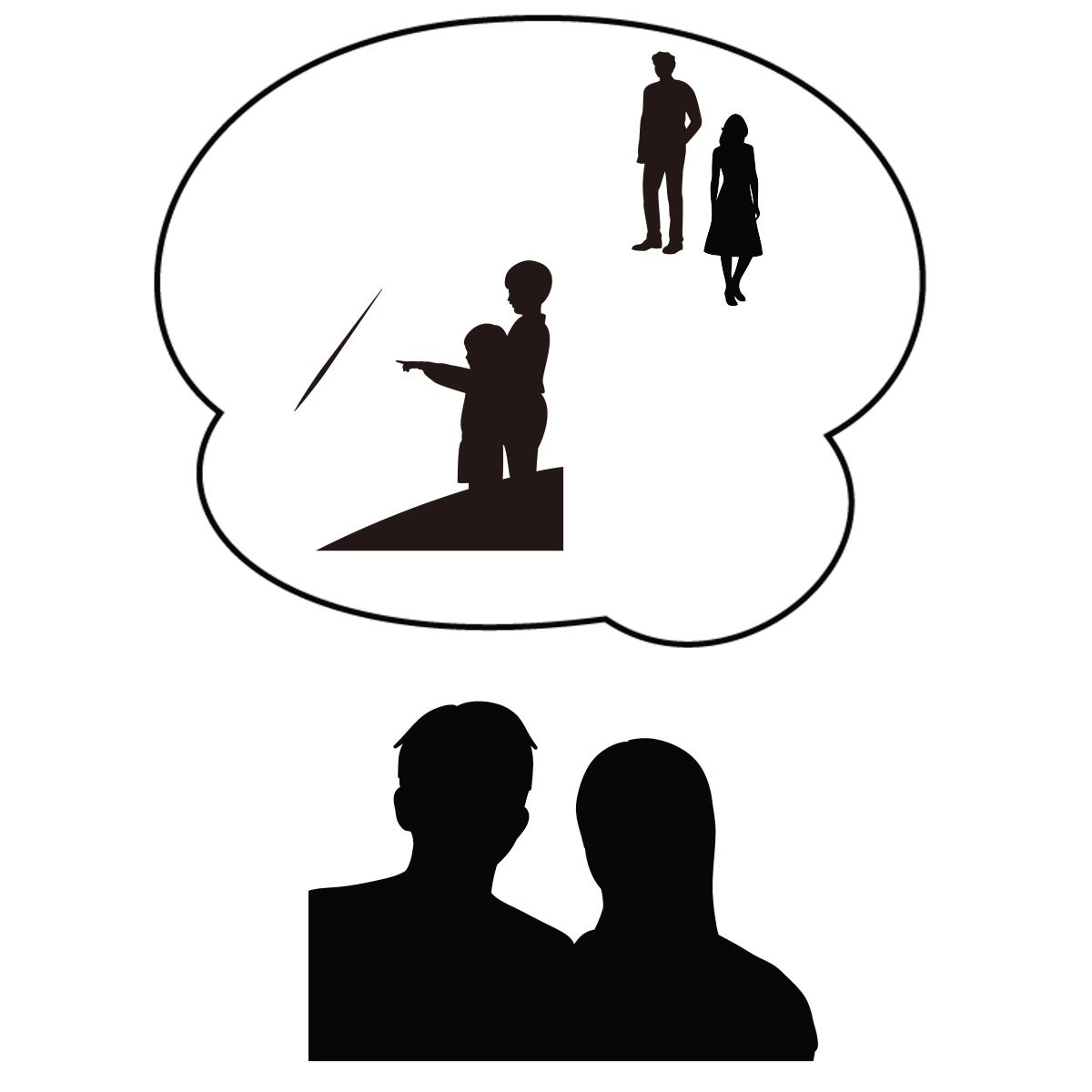
ロストワンが「いない子」を演じ続ける理由は、「いない子」を演じて「両親の負担」を減らしてあげたにもかかわらず、両親から「感謝」や「褒め」の言葉を十分に掛けてもらえなかったことにより、「『自分の存在価値』を『両親』に認めてもらえるまで『いない子』を演じ続けよう!」という「人生脚本(無意識の思考パターン)」を身に付けたことにあります。
このように「人生脚本」とは、「ロストワンの思考面の原因」を意味します。
ですので、ロストワンを克服するためには、子どもの頃に身に付けた「人生脚本」を書き換える必要があり、「人生脚本」を書き換えることを、「交流分析」という心理学では「人生脚本の書き換え」あるいは「再決断療法」と言います。
再決断療法とは、人生脚本、つまり幼児期に作った自分の決断に基づいて構成された人生のパターンの束縛から脱け出して、より自由で創造的な生き方をするために、チャイルドの自我状態に戻って、決断をやり直し人生脚本を書き換えて行く精神療法ということになります。
引用元:TA再決断療法とは?
とはいえ、「交流分析」によると、「再決断療法」によって「人生脚本を書き換える」ためには、「『子ども(チャイルド)』の自我状態に戻ってアプローチする必要がある」と考えられています。
再決断療法は「子ども」の自我状態にアプローチすることで、腑に落ちた気づきと感情をベースに、考えや行動を変えることができます。つまり、望まない無意識の人生計画といえる人生脚本から脱却することもできるのです。
引用元:人生脚本-幼時決断と再決断療法
「自我状態」とは「人と関わるときの思考・行動のクセや傾向」を指しますので、「チャイルドの自我状態」とは「人生脚本を身に付けた『子どもの頃の感覚』に戻った状態」を意味します。
ですので、「人生脚本を書き換える(再決断する)」ためには、「人生脚本」を身に付けた子どもの頃の感覚(チャイルドの自我状態)に戻った状態で「人生脚本」を選択しなおす必要があると言えます。
そして、「人生脚本を書き換える(再決断する)」ために、「子どもの頃の感覚・感情・記憶(チャイルドの自我状態)に戻る」ことを「退行(たいこう)」と言い、心理カウンセラーの催眠誘導による協力を得て行う「退行」を「退行催眠」と言います。
退行とは幼児期の感覚、感情、記憶へ遡る精神状態をいいます。そして退行催眠とは、昔の過去の記憶や感覚に戻らせる催眠誘導を指します(年齢退行)。
以上のことから、「人生脚本(無意識の思考パターン)」を「安全・確実」に書き換えるために、以下の「手順」で取り組む必要があります。
POINT
- 「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」によって「チャイルドの自我状態」に戻る
- 「チャイルドの自我状態」に戻って、書き換え前の「人生脚本」を理解する
- 「チャイルドの自我状態」のまま、新しい「人生脚本」へと書き換える
それでは、以下に詳しく解説していきます。
「チャイルドの自我状態」に戻る
「チャイルドの自我状態」に戻るとは、「『人生脚本』を身に付けた子どもの頃の感覚」に「感情移入」することです。
そして、「人生脚本」を身に付けた子どもの頃の自分を「インナーチャイルド」という「イメージ」に置き換え、「子どもの頃の感覚・感情・記憶(チャイルドの自我状態)に感情移入する(退行を行う)」方法が「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」です。
インナーチャイルド療法とは、退行療法の中の1つで、「自分の中の小さな子ども」にアクセスする療法です。潜在意識は決して忘れるということがないという特徴を持っています。また潜在意識には、時間の概念というものもありません。ですから、私たちの心の奥深くには、いまだに「傷ついたままの小さな子どもの自分」がいるのです。
このように、「子どもの頃の感覚・感情・記憶(チャイルドの自我状態)」を「インナーチャイルド」という「イメージ」に置き換えることで「人生脚本を書き換える(再決断療法)」方法を「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」と言います。
書き換え前の「人生脚本」を理解する
ロストワンは「いない子」を演じて「両親の負担」を減らしてあげたにもかかわらず、両親から「感謝」や「褒め」の言葉を十分に掛けてもらえない場合が多いため、次第に「『自分の存在価値』を『両親』に認めてもらえるまで『いない子』を演じ続けよう!」という「幼児決断」をするようになります。
その後、ロストワンは「幼児決断」によって決めた「いない子」を家族のなかで演じ続けていきますが、「いない子」を演じ続けているうちに、徐々に「いない子(おとなしい子・手の掛からない子)」を演じることが当然となってしまい、次第に家族から「生まれつき、おとなしい子」あるいは「生まれつき、手の掛からない子」と思われるようになります。
とくに、ロストワンは「先に生まれた『兄姉(年上のきょうだい)』」がすでに「アダルトチルドレン」である場合が多く、親が「先に生まれた『兄姉(年上のきょうだい)』」への対応に手一杯で精神的に余裕がない場合に生まれやすいと考えられおり、その影響で「生まれ順が遅い子どもであればあるほどロストワンになりやすい(ロストワンは末っ子に多い)」と考えられています。
なお、「『生まれ順が遅い子ども』がロストワンになる様子」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
- POINT「長男」は「ヒーロータイプ(英雄役)」で勉強やスポーツなどで優秀な成績を収めており、親から期待されている
- 「次男」は優秀な「長男」に対して劣等感を感じ、その影響で「スケープゴート(身代り役)」となって荒れており、親から心配されている
- 荒れている「次男」のケアに手一杯で子育てに余裕のない親は、「末っ子」のことを「おとなしい子・手の掛からない子」として扱うため、「末っ子」は親の言葉に従って「ロストワン(いない子)」となり、親の負担を減らすことで親の関心を引き、親の愛情を得ようとする
このように、親は子育ての負担を減らしたいがために「生まれ順が遅い子ども」を「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」として扱う場合があり、その影響で、ロストワンは「親の言葉」に従って「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」を演じるようになり、親の負担を減らすことで親の関心を引き、親の愛情を得ようとすると考えられています。
なお、「ロストワンが生まれる原因となる親の言葉」とは、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- わががまで手が掛かるあなたは、親に負担を掛けるとても悪い子ね!
- おとなしくて手の掛からないあなたは、親に迷惑を掛けないとてもいい子ね!
このように、ロストワンは「両親の負担」を減らそうと「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」を長く演じ続けることにより、次第に以下のような「人生脚本」を身に付けていきます。
POINT
- 周囲に負担や迷惑を掛ける自分はわがままでダメな人間だ!
- 周囲に負担や迷惑を掛けないおとなしい自分はいい人間だ!
- 周囲に負担や迷惑を掛けてしまう自分には存在価値がない
- 周囲に負担や迷惑を掛けないよう、常に自分の存在感を消す(自我を抑える・一人で過ごす)ことで自分には存在価値が生まれる
- だから自分が存在し続けるためには、自分の存在感を消し続けなければならない
このように、「インナーチャイルドセラピー」によって、目を閉じながらゆっくりと「チャイルドの自我状態」に戻ると、上記のような「書き換え前の「人生脚本(無意識の思考パターン)」の存在をはっきりと感じることができます。
とはいえ、「チャイルドの自我状態」に戻る作業は、専門知識と専門技術を必要とする難しい作業ですので、心理カウンセラーなど専門家の協力が必要です。
新しい「人生脚本」へと書き換える
「書き換え前の「人生脚本(無意識の思考パターン)」を感じて、自分にはどのような「生きづらい思考パターン」が存在しているのか?を理解できたら、「チャイルドの自我状態」のまま「人生脚本の書き換え」を進めていきます。
ここでは、「交流分析」の「4つの人生態度」の中から「自他肯定(自分のことも、他人のことも肯定できる人)」に沿って「人生脚本の書き換え」を進めていく「一例」を解説します。
なお、「『自他肯定』に基づく『人生脚本の書き換え』」とは、以下のようなイメージです。
書き換え前
POINT
- 周囲に負担や迷惑を掛ける自分はわがままでダメな人間だ!
- 周囲に負担や迷惑を掛けないおとなしい自分はいい人間だ!
- 周囲に負担や迷惑を掛けてしまう自分には存在価値がない
- 周囲に負担や迷惑を掛けないよう、常に自分の存在感を消す(自我を抑える・一人で過ごす)ことで自分には存在価値が生まれる
- だから自分が存在し続けるためには、自分の存在感を消し続けなければならない
書き換え後
POINT
- 今までは、周囲に迷惑を掛けないように自分の個性(気持ち・意見・価値観)を内面に隠し続けてきた(自分の存在感を消し続けてきた)
- 同時に、周囲に自分の個性を「否定・無視・干渉・詮索」されて心を傷つけられることが怖くもあった
- だから、自分の個性を内面に隠すことで安心していた自分がいた
- 同時に、今までは自分の個性を内面に隠し続けることが苦しくもあった
- だから、自分の個性を隠さずに表に出して安心したいと感じる自分もいた
- だとしたら、自分の個性を内面に隠しても、自分の個性を表に出しても、どちらも安心できるのでどちらもOK
- だからこれからは、自分の個性を内面に隠してもOK、自分の個性を表に出してもOK
- だからこれからは、自分の個性を内面に隠しても、隠さなくても、自分は存在し続けてOK
このように、書き換え前の「人生脚本)」を感じつつ、新たな「人生脚本(思考パターン)」を目を閉じながら「言葉」で復唱していくと、徐々に、新たな「人生脚本(思考パターン)」へと書き換わっていきます。
とはいえ、「チャイルドの自我状態」を保つことも、新たな「人生脚本(思考パターン)」へと書き換えることも、専門知識と専門技術を必要とする難しい作業ですので、心理カウンセラーなど専門家の協力が必要です。
インナーチャイルドセラピーの効果とその後
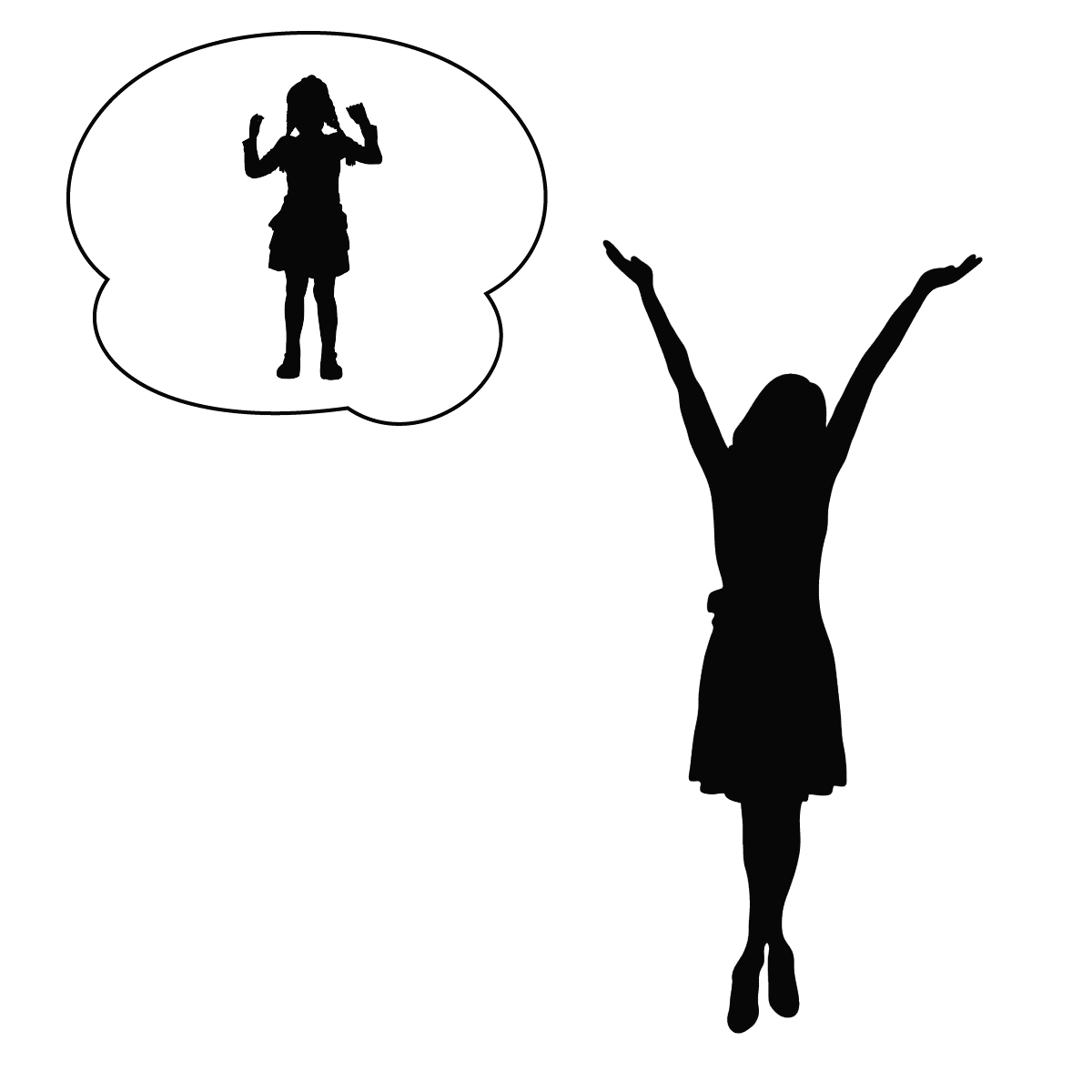
このように「インナーチャイルドセラピー」は「アダルトチルドレンの克服」に非常に効果的です。
なお、「インナーチャイルドセラピーの効果」をまとめると、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- ロストワン(いない子)の根本原因である「幼少期のトラウマ」を「安全・確実」に癒すことができる
インナーチャイルドセラピー後は、特に何もしなくても「幼少期のトラウマの自然治癒」が進み、ロストワン(いない子)の症状は自然と治まっていく - ロストワン(いない子)の症状が再現する原因である「人生脚本」を「安全・確実」に書き換えることができる
インナーチャイルドセラピー後は、特に何もしなくても「新しい人生脚本での生活」が続き、ロストワン(いない子)の症状は自然と治まっていく - 「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)」は、「幼少期のトラウマの癒し」と「人生脚本の書き換え」を「2つ同時」に取り組むことができる
このように、「インナーチャイルドセラピー」が終わった後は、特に何かをしなくても、ロストワン(いない子)の症状は自然と治まっていきます。
そして、ロストワン(いない子)の症状が治まっていくと、子どもの頃に体験できなかった「楽しいこと・嬉しいこと」を新たにやってみたいと感じたり、子どもの頃に諦めてしまったことを再びやってみたいと感じたり、自分らしい人生を自然に取り戻していきます。
また、「アダルトチルドレンを克服することで生まれる変化」は、主に以下の「具体例」があげられます。
POINT
- 親からの自立
- 自己肯定感が高まる
- 適正な人間関係が築ける
- やりがい・生きがいを感じられる
- 恋愛・結婚・子育てに自信が生まれる
なお、「アダルトチルドレンを克服することで生まれる変化」については以下の記事で詳しく解説していますので、必要な方は参考にしてください。
ロストワン(いない子)克服のお手伝い
ロストワンは「周囲に負担や迷惑を掛けたくない、自分が我慢をすることで周囲に掛ける負担や迷惑を減らさなければ」という真面目な性格である方が多く、子どもの頃から「大切な家族とみんな一緒に笑顔でいたい」「大切な両親と一緒に笑顔でいたい」という大切な望みがあったからこそ「いない子」を演じ続けてきました。
このように、長年、「おとなしい子・手の掛からない子(いない子)」を演じることで家族の負担を減らし続けてきてくれた「インナーチャイルド」を、大人になった自分が癒してあげることで、自分で自分を安心させることができ、あなたが笑顔になることで、親や家族も笑顔になっていくでしょう。
当社メンタル心理そらくもは、本記事で解説した「インナーチャイルドセラピー(退行催眠)による「ロストワン(いない子)」の克服」を、「半日セッション(3~4時間)」もしくは「1日セッション(6~7時間)」という「解決志向(短期療法)による対面カウンセリング」でお手伝いをしています。
いつの日か、あなたがより安心して過ごせるようになっていくお手伝いをさせて頂けると嬉しいです。
なお、当社メンタル心理そらくもの「解決志向(短期療法)による対面カウンセリング」については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、当社メンタル心理そらくもは、「インナーチャイルドセラピー後のアフターフォロー」も行っておりますので、以下にあわせて紹介します。
「アダルトチルドレンタイプ」それぞれの「克服方法」
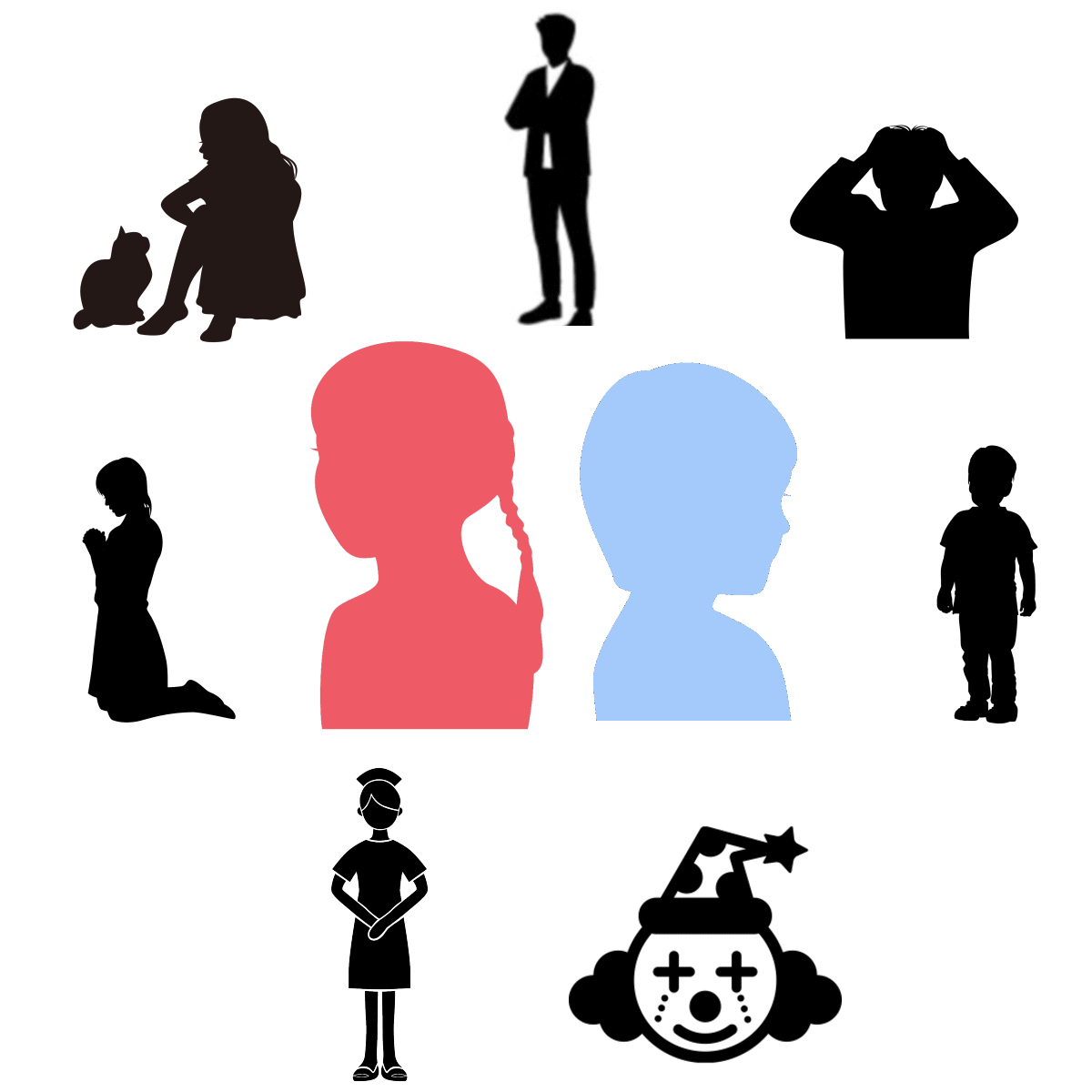
アダルトチルドレンが、子どもの頃に身に付けた「機能不全家族での役割」を、アメリカの心理療法家「ウェイン・クリッツバーグ」は「アダルトチルドレンタイプ」としてまとめました。
そして、「ロストワン(いない子)」とは、「ウェイン・クリッツバーグ」がまとめた「アダルトチルドレンタイプ(機能不全家族での役割)」のひとつにあたります。
なお、「ロストワン(いない子)」以外の「アダルトチルドレンタイプ」それぞれの「克服方法」については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事
まとめ
さいごに、本記事の重要ポイントをまとめます。
- POINTロストワンの克服は、「感情面」と「思考面」の「両方の取り組み」が必要
- 目を開けて行う「対話型のカウンセリング」では、ロストワンの克服がうまく行かない場合がある
- 目を閉じて行う「インナーチャイルドセラピー」は、ロストワンの克服に非常に有効
- ロストワンの克服は、「幼少期のトラウマの癒し」と「人生脚本の書き換え」が必要
- 「インナーチャイルドの概念」を用いることで、「幼少期のトラウマの癒し」と「人生脚本の書き換え」が「安全・確実」に行える
- 「インナーチャイルドセラピー」は、「幼少期のトラウマの癒し」と「人生脚本の書き換え」を「2つ同時」に取り組むことができる
- 「インナーチャイルドセラピー」後は、特に何もしなくても、ロストワン(いない子)の症状は自然と治まる
また、本記事に関する関連記事を以下に紹介します。
是非、あわせてお読みください。
関連記事
なお、本記事に関する関連情報は、以下のページでもまとめていますのであわせて紹介します。
関連情報まとめページ
以上、「ロストワンの克服:インナーチャイルドセラピーによる克服方法」という記事でした。